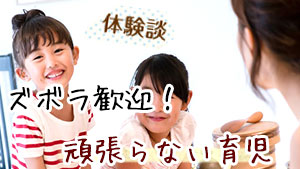子供の口答えや屁理屈にイライラするのは損!ユーモアでかわす7つの神対応と自立を促す叱り方
子供の口答えや屁理屈にイライラしてしまい、つい言い返したり、強く叱ってしまったりするパパやママは多いものです。年中・年長と子供の年齢が上がるにつれて、言葉遣いや口答えのレベルもエスカレートしがちです。
しかし、口答えはコミュニケーション能力や自己主張が発達している成長の証であり、自立に向けて親子の境界線を探っている通過点でもあります。イライラや落ち込みを吹き飛ばす「神対応」を身につけ、ユーモアを忘れずに対応することで、親も子も安定し、健やかな成長をサポートできます。
ユーモアでかわす!子供の口答えへの7つの神対応
子供の口答えを真正面から受け止めてムキになると、親子ともに疲弊してしまいます。ここでは、ユーモアと愛情を込めて口答えをヒラリとかわすための具体的な神対応を7つご紹介します。
1「ママもじゃん」VS「そのとおり!ママも寝るね」

子供の口答えに多い「ママもじゃん」は、親の行動を客観的に見ている証拠でもあります。これにムキになって怒るのは逆効果です。プチ反抗期の子供には、好ましいお手本を見せ、後に引けない状況を作ってしまうのが神対応です。
母:「早く寝なさい」
子:「やだ、ママだって起きてるじゃん」
母:「そのとおりだね!疲れたからママも寝る。お休みなさい」
「そのとおり!」と子供の指摘を肯定し、即座に実行することで、子供は口答えすらできなくなり、親の行動に巻き込まれる形で寝るしかなくなります。イライラは体調不良の元にもなりますので、ぶつからない神対応を心掛け、親も健康的に過ごせるようにしましょう。
どうしてもその日のうちに片づけなければならない仕事がある時は、子供に協力をお願いするのも効果的です。
母:「早く寝なさい」
子:「やだ、ママだって起きてるじゃん」
母:「そのとおりだね、ママもう寝る。ママの代わりに食器洗いしておいて、お願い。」
子:「えぇぇぇ!いやだよ」
母:「そんなこと言わずにお願い。ママもう寝たいからお願いね」
2「わかってる!」VS「わかってたのね!さすがだね」
良かれと思って教えたのに、「わかってる!」という生意気な口答えが返ってくるのは、4~5歳のプチ反抗期からギャングエイジにかけての「あるある」です。大人が感情的に怒っても、子供がやる気にならなければ問題は解決しません。
ここは一歩引いて、子供の「わかっている」という主張を尊重して対処しましょう。子供の主張を認め、やるべきことをしないとどんな結果になるかをさりげなく伝えるのが親の神対処です。
母:「出かける前に、歯磨きしなきゃダメよ」
子:「わかってる!」
母:「そう、わかってたのね。さすがだね!良かった~。やらないと公園に行って遊べないものね」
時間が差し迫っている時は、やらなかった時の結果ではなく時間を示し、親がいそいそと自分の支度を進めるのも良い対処です。親が着々と予定を進めていく気配を敏感に察知して、子供が自発的に動き出しやすくなります。
母:「出かける前に、歯磨きしなきゃダメよ」
子:「わかってる!」
母:「そう、わかってたのね。じゃ、時計の長い針が12を指したら玄関ね。ママはこれからお化粧です。」
子:「ええっ、間に合わないよ!」
母:「今から始めれば、大丈夫。」
子:「わかった。」
ネチネチと念押ししたり、うるさくお尻を叩いたりせず、早めに切り上げて放っておくのがイライラしないコツです。
3「今やろうとしていたの!」VS「気づかなかったわ、お願いね」

「今やろうとしていたの!」という逆ギレは、「自分一人でもできるという気持ちを認めてもらいたい」という子供の自主性の表れです。大人が先回りして余計な指摘をしている場合は、一旦は子供の自主性に任せましょう。
母:「お片付けしなさい」
子:「今やろうとしていたの!」
母:「あ、そうだったの?気が付かなかったわ。じゃ、お願いね。」
「ほら、やってないじゃん!」と追い打ちをかけるのはNGです。あくまでも子供の自発的な行動を待つのが神対応です。幼児の場合は、どうすればいいか考えていることも多いので、パパやママは様子をみながらフォローしてあげると良いでしょう。
その際、「〇〇しなさい」という命令ではなく、「〇〇してみたらどうだろう?」という提案にすることで、子供も口答えせずに大人の言葉を受け入れやすくなります。
母:「お片付けしなさい」
子:「今やろうとしてたの!」
母:「あ、そうだったの?気が付かなかったわ。じゃ、お願いね。」
子:「…」(動ごかない)
母:「ねえ、最初に絵本だけ戸棚に戻してみたらどう?スッキリして、おもちゃが片付けやすくなるんじゃない?」
子:「うん」
母:「一緒にやってみようか?(手伝うのは片付けの手順だけ)」
子:「うん、やってみる。」
親が代わりにやってしまう行動は、子供のやる気を台無しにし、怠け癖をつけさせてしまうきっかけになりかねません。「やるのはキミ。ママはお手伝いだけ」という態度を貫きましょう。
4「ママ、ウザい!嫌い!」VS「ひどい!こんなに好きなのに!」
「ママ、ウザい!嫌い!」といった乱暴な口答えは、大人の反応をうかがう「試し行動」の意味合いもあります。これを子供の本心だと思って深刻になっても、子供を意固地にするだけです。
ここは明るく笑い飛ばして、愛情をたっぷり伝えるぐらいが神対処です。
母:「〇〇しなさい」
子:「ママ、ウザい!嫌い!」
母:「そんな、ひどい!ママはこんなに好きなのに!」
大人の笑い飛ばす態度でも口答えを続ける場合は、子供が恐れるもの(例:節分の鬼、サンタクロース、大好きな先生)をジョークで出し、褒めてみるという選択肢も効果的です。他人を傷つけるような言葉を使って口答えをし続けるのは、まわりに認められたいという思いが隠れているものです。
母:「〇〇しなさい」
子:「ママ、ウザい!嫌い!」
母:「わかった、ママは節分の鬼に電話する。」
子:「ええっ!?」
母:「鬼さんはね、◯◯ちゃんはいつも頑張るいい子なんだから、ウザイなんて悲しい言葉は言わずに、やりたくないって言えばいいんだって言ってたよ。」
子:「うん、わかった」
子供を一旦落ち着かせ、「いい子だね、大好き!」と大人のほうから愛情を伝えることで、口答えを封じ込める効果があります。
5「イヤったらイヤ」VS「イヤなこと全部教えて、一緒に頑張るから」
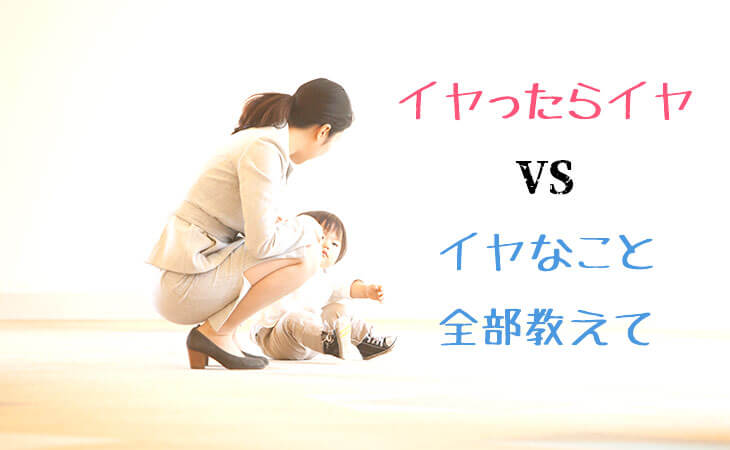
理屈も理由もない「イヤったらイヤ」という全否定は、小さな子供の口答えによくあるフレーズです。「ムカッと」きても、グッと飲み込んで、子供が何を嫌がっているのかをとことん聞いてみましょう。
小さな子供の「イヤ」という言葉には、「なんで、どうして?」という気持ちが隠されています。大人が自分の気持ちに理解を示してくれただけでも、子供の気持ちの大部分は満足し、素直な気持ちで言うことを聞けるようになってきます。
母:「〇〇しないと」
子:「イヤったらイヤ」
母:「じゃあ、イヤなこと全部教えて。ママもなんとか頑張ってみるから」
言葉で説明できない時は、パパやママのほうから一歩歩み寄って、気持ちを代弁してあげたり、別の提案をして気持ちをやわらげてあげるのが神対応です。ダメなことを覆して子供の機嫌を取るのではなく、大人が子供の気持ちを理解していることを態度で示し、自主的に出来る方法を根気よく一緒に探してあげる姿勢が大事です。
母:「〇〇しないと」
子:「イヤったらイヤ!」
母:「じゃあ、イヤなこと全部教えて!ママもなんとか、頑張ってみるから」
子:「…」(無言で抵抗)
母:「もしかして、お着替えするのがめんどくさいのかな?じゃあ、こんなやり方だったら大丈夫?(自分で着やすい服を提案する)」
子:「うん、やってみる」
6「ママがやれば?」VS「本当にやっていいの?お気に入りの服着ちゃうよ」
心配して声をかけた時に、女の子から言われることがある「ママがやれば?」という口答え。子供の口答えをそのまま逆手にとって返すことで、子供の変化を促して対処しましょう。冷たい口答えをされても、幼児のイライラを正面から返しても良いことはありません。
母:「早くお着替えしないと」
子:「ママがやれば?」
母:「いいの?お気に入りのあの服着ちゃうよ」
口答えは悪意のあるものではありませんから、軽いジャブで打ち返してみてください。それでも子供が意地を張って口答えを続ける場合は、実際に言ったこと通りになるとどんなことが起きるのか、具体的に説明してわからせてあげるのが神対処です。
母:「早くお着替えしないと」
子:「ママがやれば?」
母:「いいの?お気に入りのあの服着ちゃうよ」
子:「着れば?どうせ小さくて着れないでしょ!」
母:「いいの?ママのお尻パンパンで破けちゃうよ」
子:「ヤダ!着替える!」
パパやママが頭ごなしに怒るのではなく、お互いにクスッと笑える対処をすると、子供のイライラが引っ込みやすくなります。
7「ハイハイ」VS「わかればよろしい、助かるよ!」
何を言っても「ハイハイ」というカラ返事は、「わかっているから、これ以上言わないで」という意思表示が含まれる口答えの定番です。大人の意見を無視して試そうとする気持ちもあるため、子供の自主性を尊重して一歩引いてあげるのが得策です。
母:「お着替えしてね」
子:「ハイハイ」
母:「わかればよろしい」
返事を繰り返すだけで動こうとしない姿に、親は「聞いてるの!?」と怒ってしまいがちですが、イライラが限界値を超えてしまう前に、先手を打って褒めておだて、自発的な行動を促しましょう。
母:「お着替えしてね」
子:「ハイハイ」
母:「わかればよろしい!ママ助かるよ、いつもありがとうね」
子:「…うん」
子供は親が言い返してくることやもっと世話を焼いてくることを予想していますが、パパやママが子供の反抗をあっさりとスルーすれば、「何かがおかしいぞ!?」と不安に思い、思わず行動を起こしてしまうものです。実際に子供がアクションを起こしたら、さらに褒めてあげることで、無駄な口答えが次第に減ってきます。
口答えばかりする子供は賢い!自立への通過点と親の心構え

子供の口答えは屁理屈が多いため対処する親は大変ですが、会話やコミュニケーション能力が発達し、物事を客観的にとらえて自己主張をはじめている成長の証です。反抗期と同様に子供の成長の一過程として必要な行為ですので、パパやママは口答えを真正面から受けとめるのではなく、右に左に受け流して対処しましょう。
口答えをされるほど、「自分が言ってあげないと」と考えがちですが、一歩下がることを意識すると大人も気持ちに余裕がでて育児が楽になりますし、子供もアドバイスを素直に聞き入れやすくなります。
子供の口答えに効果的な「叱り方」とNG行動

口答えをする子供への対処法は、大人が感情的にならないこと、ムキになって言い返さないことが基本です。どうしてもイライラしてしまう時は、一度深呼吸をしたり、一旦子供から離れて頭を冷やしてから、冷静に気持ちを伝えることが大切です。
叱る必要がある時の原則:感情的にならず冷静に真剣に伝える
口答えは基本的に叱る必要がない自然な行為ですが、他人を傷つける言葉や社会のルールを破る行為など、状況によっては叱ってあげることが必要です。そのような場合は、次のポイントを意識し、真剣さを伝えましょう。
- よその子と同じ言い方で叱る: 子供の人格やプライドを傷つけない言葉を選び、相手の弱点を突かず追い詰めないのが大人としてのマナーです。親は我が子に遠慮なくズケズケと物を言いがちですが、これはお互いに感情的になるモトになります。
- 冷静に真剣に伝える: 真顔で、目を見て話すようにしましょう。「一度で効く叱り方」はありません。口答えする子供は、何が本当に正しいのかを体当たりで学んでいる最中です。感情的にならず、幸せに生きていくために必要なことを冷静に真剣に伝え続けることが重要です。
- 子供の主張は最後まで聞く: もし子供が自己主張してきたら、話をさえぎらずに黙って最後まで聞きましょう。その後に自分の主張を伝えた方が、子供は話を素直に聞きやすくなります。
真剣さが伝わる叱り方のポイント
- にらまない
- 笑わない
- 目を見る
- 話しをさえぎらない
- 言い切る
夫婦そろって叱る:親が統一した境界線を作ることが大切
子供を叱る時は、パパやママが統一して「絶対譲れない境界線」を作っておくことが大切です。夫婦でバラバラの叱り方をしていると、「パパはいいって言ったのに!」という新たな口答えのもとになります。しつけは、子供の感情を不必要にあおらないよう、ポイントを絞って行いましょう。
また、イソップ童話「北風と太陽」を意識し、脅しや強い態度で一時的な行動の改善を促すのではなく、褒めておだて、自ら行動を起こさせるのが一番効果的です。口答えや反抗の裏にある子供の要求に注目し、共感して自主的に行うように仕向けた方が、行動が身に付きやすいです。
口答えが悪化する!絶対にやってはいけない親の対応4つ(YMYL配慮)

子育てはバランスであり、多少の失敗は子供の社会に出た時の耐性となりますが、次の4つの対応は子供の心に深い傷をつけてしまう恐れがあるため、絶対にしてはいけません。
1脅迫や暴力(体罰・暴言)で子供を頭ごなしに押さえつける
体罰や暴言は、心や体を暴力で傷つける行為であり、子供の叱り方で最もいけない対応です。どんなにカッときても、一線を越えて子供に手をあげたり、怯えさせたりしてはいけません。子供は親から生きる術を学びます。暴力や脅迫が正しいことだと子供が勘違いをしないよう、言葉や態度で言い聞かせることを徹底しましょう。
2子供の主張や意見を全く聞かない
子供が屁理屈をこねて口答えをするのは、何らかの意見や主張がある時です。大人がこれに全く向き合わないのでは、解決の糸口がつかめません。親であっても、自分に悪いところがあったら謝るのがマナーです。
受け入れられない要求であっても、子供の意見だけはしっかりと聞き、「そう思っていたのね、分かったわ」と気持ちを受け止めたことを言葉や態度で示してください。その上で受け入れられないことを正直に伝えることが大切です。
3子供の人格を否定する
子供の屁理屈や口答えで大人の心が傷ついても、「ダメな子」や、「ママだって、あんたなんか嫌い!」と言い返して対処するのはNGです。これは子供の心を傷つけるだけでなく、言った自分自身の心も傷つけます。
子供の自立と成長には「パパやママに受け入れてもらえる」という自己肯定感が必要不可欠です。性格や容姿を非難する、他の子供と比較するなどの子供を否定する叱り方はやめましょう。
4子供の存在を無視する(ネグレクトを示唆する対応)
子供の口答えにイライラしたら一旦子供から離れることは必要ですが、生活の世話をしない、あるいはその場にいるのに子供がいないようにふるまうといった対応は、子供を傷つけたいと受け取られてしまいます。
しつけとは、幸せに暮らせる大人へと自立させるために行う家庭での教育です。自分一人の力で対処するのが無理な問題があるときは、パパや親族、園の先生などにも協力を求めて対処しましょう。
子供の口答えや屁理屈に負けないで!ヒラリとかわし、譲れない部分は毅然と
子供の口答えや屁理屈は反抗の表現方法の一つですので、その場で真に受けて反撃したり、やり込めたり、納得させようとする必要はありません。口答えを真に受けて叱ってコンプレックスを与えて意固地にさせるより、良い行いをしたくなるようにサポートし、できたら褒め、感謝の気持ちを伝える方が効果的です。
口答えをヒラリとかわす親の態度から、子供も反抗心や感情のコントロールを学べます。7つの神対処のようなユーモアを忘れずに、譲れない境界線は毅然とした態度で示し、子供の健やかな成長をサポートしましょう。