幼稚園の個人面談の内容は?何を質問すべき?手土産など注意事項

幼稚園の個人面談の時期が近づくと、「何を着て行けばいいか」「下の子は連れて行ってもいいのか」「何を話せばいいのか」など、ついついご自身の気持ちやお子さんの相談で頭がいっぱいになりがちですね。しかし、個人面談はその目的を理解して上手に活用することで、その後の園生活や子育てが円滑に進みやすくなる絶好の機会でもあるのです。
こちらでは、幼稚園の個人面談にまつわる保護者の疑問と回答、個人面談の目的と各学年での発達の目安、先生からのアドバイスを家庭での子育てに活かす方法などをご紹介します。落ち込んでしまったり不満を持ったりする保護者の方も多い幼稚園の個人面談ですが、捉え方が変わることで悲しみや苛立ちが解消されやすくなり、きっと心強い味方を得られますよ。
初めての幼稚園の個人面談Q&A
幼稚園の個人面談は、お子さんの園生活での様子を知り、家庭で見せる頑張りや不安を先生に伝え、お子さんの発達を園と一緒に適切にサポートするための環境作りをするための、またとないチャンスなのです。
「何か言うと、モンスターペアレントと思われそう…」などと遠慮せず、限られた時間を上手に使って先生とのコミュニケーションを図りましょうね。
こちらでは、保護者の方からよく聞かれる「手土産はいるのか」「服装はどうか」「どんなことを話したらいいのか」という個人面談にまつわる疑問とその対処法をご紹介します。
Q1手土産は必要ですか?
公立の幼稚園は、原則として手土産を受け取れません。また、私立の幼稚園は園によって方針が異なるため、園として手土産を禁止しているところもあれば、担任の先生に渡したり、園の先生全体への手土産として渡したりということもあります。どちらかわからない場合は、ママ友や先輩の保護者の方に確認してみると安心でしょう。
手土産なし
私立の幼稚園です。転園した経験があるので2つの幼稚園に通園経験があります。2つの幼稚園とも格式のある私立の幼稚園です。以前の幼稚園では面談で手土産を持参したことはありませんでしたし、持って行ったというママ友の話も聞いたこともありませんでした。
しかし、現在の幼稚園では面談前のプリントが配られて、注意書きに手土産禁止とありました。もしかしたら以前は手土産を持参する保護者がいたのかなと思っています。
Q2下の子は連れて行ってもいいですか?

じっくり担任の先生と話をしたい場合、下のお子さんを預けていくのが望ましいでしょう。下のお子さんが活発に動いたりすると、気がそちらに向いてしまい、話が進まないこともあります。もし、預け先がなかったり、預けた経験がまだなかったりするようであれば、連れて行ってもいいか事前に園に確認しましょう。
園によっては、他の先生が見てくれるところもありますし、特に問題なければ、面談している隣で遊ばせておくことができるところもあります。赤ちゃんであれば、面談の間、抱っこ紐などで寝かせられるように、お昼寝対策をしておくといいですよ。
下の子2人連れ
預け先がなかったことと、まだ預けた経験がない乳児がいたので、下の子二人も一緒に連れて行きました。面談の前に担任の先生には確認済みです。上の子たち同士は教室でお絵かきをしたりして遊び、一番下の子は抱っこ紐で抱っこしたまま面談を受けました。
上の子の様子を見ながらだったので、途中話が中断することがありましたが、問題なく面談を終えることができました。また、面談が幼稚園降園後ということもあり、乳児対策としては、面談時間を逆算してお昼寝をさせないようにして臨みました。面談中は、抱っこしている間寝てくれたので、先生ともしっかり話ができて下の子には感謝です。
Q3親や子供の服装は?

幼稚園の個人面談は下のお子さんを連れてくるご家庭も多いため、スーツでカチッと決めなくても、カジュアル過ぎない清潔感のある服装ならば特に問題はありません。ただし、極端に胸元の空いた服や、ダメージジーンズや丈の短いスカートなどは避けましょうね。どの程度フォーマルにするかは幼稚園の雰囲気によっても違ってきますので、事前に他の保護者の方に確認すると安心ですよ。
園児の服装は、面談の時間や順番によって違うご家庭もあります。登園後すぐに面談をする場合は制服のままであることが多いと思いますが、登園後から時間があれば、待ち時間の間に制服が汚れるため着替えさせる保護者もいます。
下のお子さんの服装は、普段着ている動きやすい服装でOKです。もちろん汚れた時の着替えは忘れないようにしましょうね。
また、個人面談で履くスリッパは、持参するようにお便りでお知らせがあることが多いです。小中学校でもスリッパを持参する機会が多いため、入園したら折りたたみ可能なMYスリッパを準備しておくと便利ですよ。下のお子さんの上靴も、忘れずに持って行ってあげましょうね。
Q4どんなことを質問すればいいですか?

「経験の浅い先生だから…」「厳しそうな先生だから…」と決めつけず、日頃からお子さんの様子について悩んでいることがあれば、思い切って相談してみましょう。集団生活での子どもの様子を教えてもらえますよ。
また、まだ経験の浅い先生には答えられないような範囲の育児に関する質問も、まずは担任の先生に相談してみましょう。「そうですねぇ。でも、◯◯ちゃんは頑張っていると思いますよ」「でも、私、◯◯くん好きですよ」など、あいまいな答えが返ってきて納得できない場合は、すぐに答えを求めていない姿勢を見せるのも一つの方法です。
例えば、「家庭でも対応に悩んでいて…。突然の質問では先生もお困りだと思いますので、多くの子供達を見ている先生方からのより具体的なアドバイスがあれば、次回のお迎えの時にでも教えていただけないでしょうか?」などと、さりげなく担任の先生がベテラン先生などからアドバイスをもらえるきっかけを作っておくなどの対応をすると、より良いアドバイスを得られることがありますよ。
Q5聞きたいことは何でも聞いていいですか?
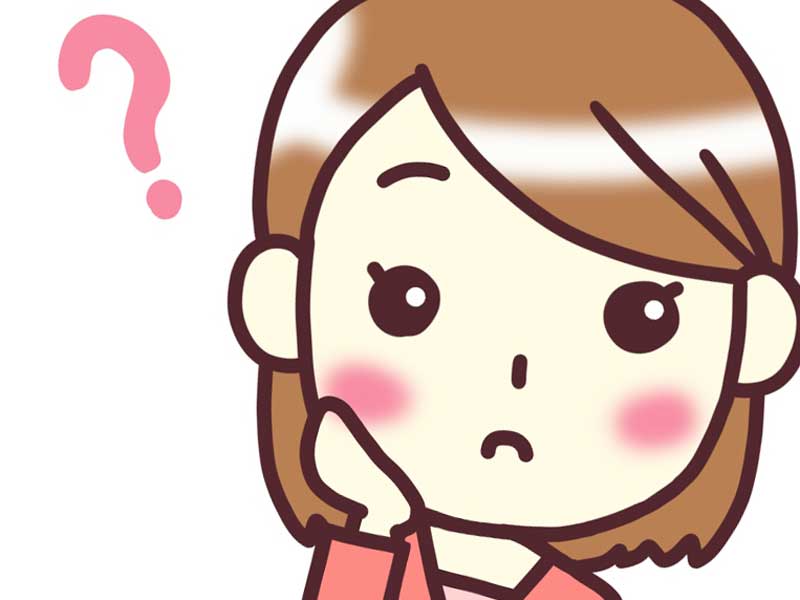
個人面談の時間は1人当たり15分~1時間と園によってばらつきがあります。限られた時間の中で質問するには、お子さんの様子を日頃からよく見て、「これ大丈夫かな」「どうしたら直してくれるかな」と思ったことなどをメモなどにまとめておくとよいでしょう。
「先生が話してくれるのに合わせてればいいよね」などと考えて、時間内に質問内容を考えようとすると、具体的にどうしたらいいかといった対策を話す貴重な時間が短くなってしまうこともあります。
幼稚園の個人面談では、まず「何かご家庭で気になっていることはありますか?」など、保護者の方に話をさせて、それに対して園での様子を伝えながら答えるという流れが多いようです。ですから、聞きたいことに優先順位をつけて「3つ質問があるのですが、1つ目が…、2つ目が…、3つ目が…」などとまとめて質問し、後の時間は先生に話してもらうと、時間内に上手くまとまり、伝えたいことを伝えられる満足度の高い個人面談になりやすいですよ。
幼稚園の個人面談での質問のまとめ例
- 性格面:友達と遊びたがらない、好き嫌いが激しいなど
- 生活面:一人で身支度ができない、歯磨きをしたがらないなど
- 行動面:落ち着きがない、かんしゃくが激しい、こだわりが強いなど
- 身体面:アレルギーで気を付けてほしいこと、視力・聴力への不安など
- 発達面:滑舌が悪い、読み書きがほかの子に比べて遅いなど
思いついたことを整理していくと、「あ、こんなこともあった」と思い出すきっかけになりますよ。また、初めにいくつ質問事項があるか先生に伝えておくと、先生も時間配分をしやすく、答え忘れなども少なくなりますし、途中で話しの流れが変わっても元にもどしやすく、聞き漏らしを減らすことができますよ。
Q6聞きたいことが多いときは?

聞きたいことが多く、あれもこれもと思いついたままを質問しても時間内に終われません。質問が多すぎると、一つ一つを丁寧に掘り下げて話すこともできなくなりますよね。さらには、次の人の時間にずれ込んで迷惑をかけてしまうこともあります。
時間内に聞けなかったり、質問事項が多かったりする場合は、先生に「質問事項が多いので、後日改めて伺いたいのですが」などと伝えたり、幼稚園の連絡帳などを活用して伝えたりすると、先生も時間の都合をつけて対応しやすくなります。
面談をきっかけに日頃から先生とのコミュニケーションを大切にしておくと、連絡帳やお迎えの時間を利用して不安や悩みなど相談しやすくなり、お子さんのより良い成長に役立てることができますよ。
Q7先生があまり話してくれない時は?
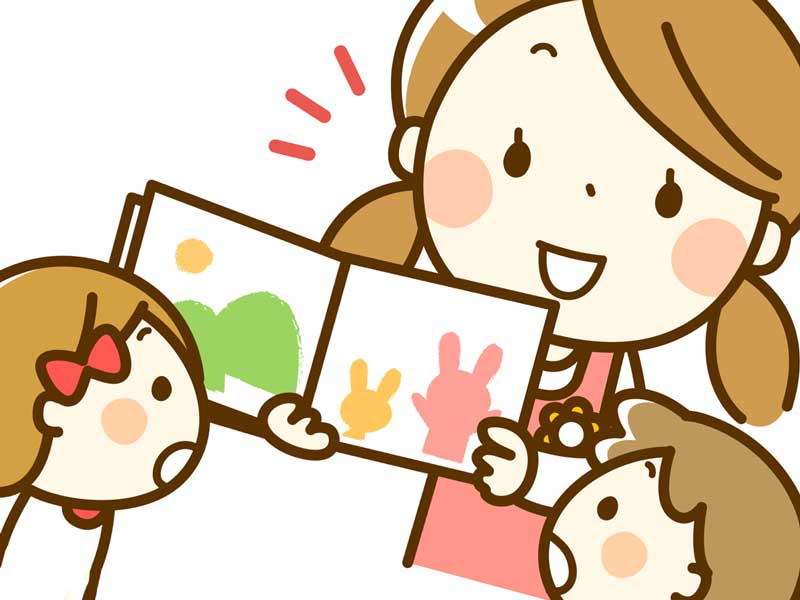
指摘されても心配、逆に何も言われなくても心配なのが親心。「本当に何もないの?見てないだけじゃない?」などと不安になる保護者の方は、実は意外と多いですね。
幼稚園の個人面談で特に指摘されないという場合、「問題なくその年齢での集団生活における発達の目安をクリアできている」と先生が判断しているケースが多いのですが、外で問題なく過ごしているお子さんに限って、家庭では「子トラちゃん」になって親を困らせていることもあります。そのため、親としては「でも…」と不安を抱えやすいのです。
もし、家庭生活において気になるところがあれば、遠慮せずに先生に伝えましょう。むしろ伝えた方が「園では随分頑張っていたんですね!教えて頂けて助かります」などと言われ、ケアしてもらえるためお子さんのストレスが減り、家庭でも落ち着いて過ごせるようになったり、園生活をより楽しめるようになったりすることが多いですよ。
Q8順番が最後なのは問題があるからですか?
幼稚園の個人面談は子どもによって順番を決めるというより、各家庭の都合を優先に順番を決めることが多いです。面談の順番を決める時は、あらかじめ各家庭に希望日時を聞いて予定を組む方法がとられる園もありますが、園によっては名簿順や地域別などで初めから順番を決めていることもあります。
ただし、中には「お子さんに問題があるというより保護者の不安が大きそうだから、時間をとってゆっくり話した方がいいかも」と、先生が保護者の子育てをサポートしたくて、最後にするケースもあるようです。
幼稚園の個人面談の意義
幼稚園では、年少児~年長児までのそれぞれの期間に身につけさせたい、発達の目安や目標に取り組んでいます。集団生活において能力を育み、適切な環境を与えるのが先生の仕事なのです。けれど、親が家庭の中だけでお子さんの全ての能力を把握できないように、先生も園の様子だけでお子さんの全ての能力を把握し、指導することはできません。
幼児教育は、家庭と園の両方で行うことで身に付きますので、個人面談には保護者との連携をとるといった大切な目的があります。個人面談前は、より話がスムーズに進むように、保護者として自分のお子さんの年齢ではどのような発達の目安があるのかを知っておくと、園と協力して子育てしやすくなりますよ。
幼稚園年少児の発達の目安

年少児は、入園当初の基本的な動きや行動がまだまだ未熟な状態から、園での一日の生活や遊びを元に、次第にスムーズな動きへと発展させることが大切です。特に、これまで家庭中心だった生活が、家庭と園という2つの場所での生活に対応しなければならなくなっているため、園での基本的な生活習慣を身につけ、集団生活に慣れ、一日の生活のリズムを整えることが大きな目安となります。
また、遊びや日常生活の多様な経験を通して健康な心と体を育むことも大切な発達の目安です。自ら何度も繰り返すほどの面白さを感じるような環境を、園や家庭で整えることが必要になります。例えば、体のバランスをとる「立つ」「座る」「起きる」「寝転ぶ」「回る」「転がる」「ぶら下がる」「渡る」といった動きや、「走る」「跳ねる」「のぼる」などの体を移動させる基本的な動きの経験を積ませる遊びなどですね。
幼稚園年中児の発達の目安

年中児になると、年少の時期に経験してきた基本的な動きが身に付いて定着しはじめていますので、次の発達の目安としてお友達との関わりを楽しむようになり、一緒に関わる楽しさや遊びの工夫などをして、さらに経験を積むようになってきます。自分達でルールを作り、大人のマネをしたがるようにもなります。
運動としては更にステップアップし、「持つ」「投げる」「運ぶ」「転がす」「押す」「引く」「掘る」「積む」「蹴る」「こぐ」など、道具を使った動きの経験をさせておきたい時期でもあります。
それまでは一人遊びが多かったお子さんも、身近な人との関わりを深めるようになるので、お友達と一緒に遊んでトラブルになることもありますが、それも成長の一環です。ぶつかり合いの経験が、お子さんの人間性を育みます。「叩かれるとどんな気持ちがするか」「嫌なことは嫌だと言う」「助けを求める大切さに気付く」「人を傷つけるとどんな思いをするか」など、頭ではなく心が様々なことを体得できる時期なのです。
保護者がクレーマーだと子供が歪む!?
お子さんは、自分の親が先生やお友達に文句を言う姿を見ています。トラブルがあればすぐクレームをつけ、相手のお子さんや保護者、先生の気持ちも考えずに謝罪を求めていると、お子さんも親と同じ問題解決方法を学び、相手の気持ちを考えて行動できなくなるケースがあります。トラブルが発生した時ほど、お子さんに大人としての思慮深い冷静な対応を見せてあげたいですね。
幼稚園年長児の発達の目安
年長児になると、無駄な力みや動きが減ってきます。目的に向かってクラス一丸となって行動をしたり、友達と力を合わせたり、役割を分担したりといった行動を、遊びを通して行うようになってきます。また、遊びの中でもこれまでの経験にさらに磨きをかけ、工夫を加えてステップアップしていく姿が見られます。
楽しく多様な経験を積むことも発達の目安となりますので、遊びの中では鬼ごっこやサッカーなど、集団でしかできない遊びを通して「走る、歩く、よける、くぐる」などの経験ができるようにすることが大切です。小学校入学に向けた文字や数への興味・関心も高まってくる時期です。
幼稚園3年間で身につけたい発達の目標
- 愛着を持てる心
- 他人への基本的な信頼感
- 基本的な生活習慣
- 他を受け入れ、自らの力を発揮することでの自己肯定感の獲得
- 子供同士の体験による道徳心や社会性のめばえ
幼稚園の個人面談は褒めるだけですか?
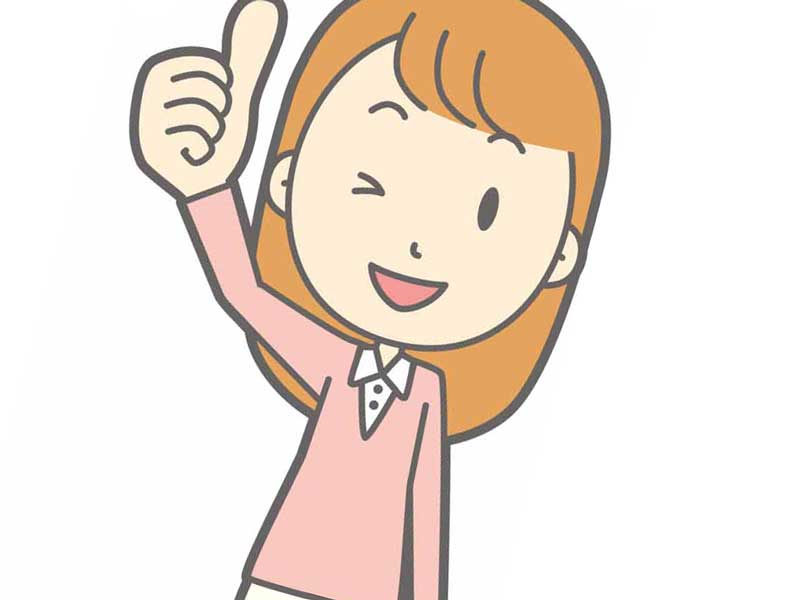
家庭や授業参観での様子から明らかに問題があると思われるのに、個人面談で褒めるだけの先生もいます。モンスターペアレント対策に苦労している園も多く、慎重にならざるを得ないため園長命令で褒めるだけにしている幼稚園もあります。
けれど、園ではお子さんへの指導を怠っている訳ではなく、むしろ保護者を追い詰めることで園でも家庭でも子供を追い詰めないようにという配慮のもと、個人面談では保護者に子供を褒めるだけになるといったケースもあります。
疑問に思う場合は、こちらから思ったことを伝えてみましょう。先生やお子さんの気持ちを考えられる保護者だと伝われば、先生も「実は…」と、園でどのように対応しているか話してくれるかもしれませんよ。
幼稚園の個人面談で発達面に関する指摘を受けたら?
幼稚園の先生も、園児の発達面に関する指摘にはとても慎重になっているはずです。もし、先生から集団生活におけるお子さんの様子について、専門的な視点からの相談を勧められた場合は、一度専門機関や児童相談所、市区町村の発達専門機関などに相談に行ってみることを検討するとよいでしょう。「まさか自分の子供に限って…」と、受け入れがたい気持ちになると思いますが、お子さんの発達に関する課題は、早期に専門的なサポートや適切な環境整備を行うことが大切です。
対応が遅れることで、二次障害(引きこもりや不登校など)をひき起こし、思春期は特に本人やご家族が無用な苦労をし、大切な親子の時間が苦しいものになるだけでなく、本人の才能や能力を引き出せなかったり、周囲の人も巻き込んだトラブルに発展したりする可能性もあります。
検査の結果、発達に関する課題以外の環境的な問題に気づくきっかけになるかもしれません。お子さんの不安の表し方はそれぞれですが、園で指摘されるということは、なんらかのメッセージを発している可能性があります。保護者の方が目を向けてあげることはお子さんへのマイナスにはなりませんので、頭ごなしに否定せず、まずは自治体の保健所や子育て相談窓口などに相談に行ってみましょう。
あながち間違えじゃなかった
うちの弟が幼稚園児だった時のことです。当時担任だった私立幼稚園のA先生。今は市内の幼稚園園長になっていますが、その先生が幼稚園の個人面談で母に「お子さん、専門機関に相談してみませんか?」と伝えたそうです。(元の文章の「発達の問題があるんじゃないですか?」は専門的判断であり、先生の立場として不適切と考え、表現を修正しました)
弟は確かに変わった子で、集団生活に向いていない性格でしたが、母は激怒して病院や専門機関には行かず「この子は理解されにくいけど、頭がいい!いつか凄い子になる」といつも言っていました。
中学生になった弟は勉強を全くせず吹奏楽にのめり込み、成績は1と2ばかり。受験の年に担任から「行ける高校がありません」と言われたそうです。母は何度も学校を訪ねて担任に頼み込み、どうにか市内で一番レベルが低い私立高校への推薦状を書いてもらい、弟を高校へ進学させました。
たまたまその高校の吹奏楽部の顧問の先生が、大学受験組の特進の担任だったため、弟は先生に頼み込んで自分の勉強も見てもらったそうです。3年後、弟は見事国立大学に合格。今は情報分野のスペシャリストとして活躍し、賞を受賞するほどになりました。
当時、発達に関する情報が少なかった時代ですが、今は多くの情報があり、様々なサポート体制も整ってきていますよね。もしあの時専門機関に相談していたら…弟はもっと才能を伸ばせたかもしれないし、母は進学であんなに苦労しなかったかもと思います。
幼稚園の個人面談で落ち込んだママへ

幼稚園の個人面談で、できないことを強く指摘されることはあまりないと思いますが、心配な点や伸ばしたい点を先生に言われることはあります。また、お子さんの成長に不安を感じている保護者の方は、先生に家庭でどのように教育していけばいいか指導されないことでさらに不安になることもあるでしょう。
けれど、園では親が思う以上にお子さんに指導を行っていることが多いです。お子さんによい変化が見受けられないのは、まだお子さんに受け入れる準備ができていないからかもしれません。家庭で幼稚園と同様に親がアレコレと言ってしまうと、お子さんのやる気を損ねてしまう恐れがあります。
多くの保護者の方は、お子さんが自分の目の前で問題行動をした時、善悪を教えて正しく導いているでしょう。ですから、幼稚園の個人面談で言われたお子さんの問題点を過度に気にし、家庭で保護者の方がお子さんを追い詰めてやる気を損なうことが無いように心掛けることが大切です。お子さんは本人が必要だと感じれば少しずつ身につけていくものですよ。
例えば、「少しマイペースな所がありますね。家庭でも指導して下さい」と先生から言われたら、保護者の方は落ち込まず「出来た時や頑張った時に褒めるポイントを教えてもらった」などとポジティブに捉えるようにしましょう。
家庭では見せない問題行動が幼稚園で見られることを指摘されたら、「親の前では我慢して見せなかったSOSサインを、園で教えてもらえた」と考え、親の気持ちや状況を気遣って我慢できる優しい子供に育ってくれたことを喜び、たっぷりと甘えさせてあげるとよいでしょう。
お子さんに寄り添い、愛情を伝え、「この子はいつか必要性に気づいて、自分で身につけることができる」と親が信じることで、お子さんは自ら問題を解決する力を持っているものですよ。そして、まずは親がお手本としての姿を見せてあげましょうね。



