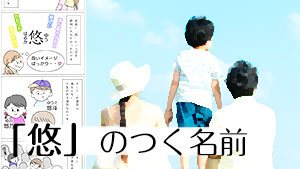新元号「令和」と名づけの傾向:漢字「令」の意味と活用法を徹底解説
2019年5月1日から始まった新元号「令和(れいわ)」は、元号として初めて日本の古典から引用されたことで大きな注目を集めました。特に、元号で初めて使われた「令」の字は、令和元年に生まれた赤ちゃんの名づけにおいて、人気の急上昇が予想されていました。
実際に、元号が変わる際には、その元号と同じ漢字が名づけで人気を集める傾向があります。例えば、大正元年には「正一」、昭和の時代には「和夫」や「昭子」、平成の時代には「翔平」や「成美」などが、その年の名前ランキングで上位にランクインする例が見られました。
ここでは、新元号「令和」の持つ意味や由来を深く掘り下げるとともに、名づけで特に注目される「令」という漢字の意味や読み方を詳しく解説します。大切な赤ちゃんに込める願いを考えるためのヒントとして活用してください。
新元号「令和」の意味と出典:日本の古典『万葉集』に由来
新元号「令和」は、2019年4月1日の発表時の会見で、当時の安倍首相により、「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つという意味が込められている」という談話が発表されました。これは、万葉集から引用されたことに由来しています。
新元号「令和」の出典元は、『万葉集』巻五の「梅花歌三十二首」の序文です。万葉集は、7世紀後半から8世紀後半にかけて編纂された日本最古の歌集であり、天皇や皇族、貴族から庶民まで、広い階層の人々が詠んだ約4500首の歌が集められている点が大きな特徴です。
新元号「令和」の出展元の万葉集の一節
「于時初春令月 氣淑風和」
初春の令月にして 気淑く風和ぎ 梅は鏡前の粉を披き 蘭は珮後の香を薫らす
「令和」は、従来の247の元号が全て中国の古典から出展していたのに対し、初めて日本の古典から引用された元号となりました。このことは、日本の文化を大切にするというメッセージが込められていると解釈されています。
「和」はこれまで19回元号に使用されていますが、「令」は初めて元号に使用された漢字です。そのため、令和元年以降に生まれた赤ちゃんへの名づけでは、「令」という漢字が持つ意味や読み方に特に注目が集まっています。
名づけで注目される漢字「令」の意味と読み方
「令」という漢字には、「言いつける」という意味から「命令の令」を思い浮かべる人もいますが、名づけの観点からは、「立派な」「優れた」といったポジティブな意味も持ちます。「令嬢」「令息」といった言葉にも使われているように、よい家柄や聡明な人といった気品あるイメージを連想させます。
「令」という漢字は、音が涼しげで響きや品がよいのが特徴です。名づけに用いる際には、「聡明で立派な人になってほしい」「信頼される清い心を持ってほしい」といった願いを込めることができます。
| 画数 | 5画 |
|---|---|
| 部首 | 入 |
| 読み方 | 音:レイ、リョウ 訓:おさ、よ(い)、いいつけ |
| 名のり 人名訓 |
なり、のり、はる、よし、れ ※人の名前の時のみ使われる読み方 |
| 意味 |
① いいつける ② 法令などを広く知らせる ③ (天皇や皇后などの)命令 ④ 法律や規範 ⑤ 教訓、いましめ ⑥ 長官や長 ⑦ 立派な、優れた ⑧ (他人の)親族の敬称 ⑨ 年を表す(例:年令) |
| 漢字の由来 | 頭上の冠の象形「亼」とひざまずく人の象形「卩」から成る会意文字で、神の言いつけを聞くという意味から、良いことが起きる「お告げ」といった意味合いにも解釈されます。 |
| 電話での伝え方 | 令和の令 |
一方、「和」という漢字には、「令」という漢字の持つ堅苦しさとは異なり、「やわらく」「なごむ」「のどか」「満ち足りた」「性質の違う物が混ざりあう」などの穏やかな意味があります。名前に使われることが男女ともに多く、協調性や平和を願う意味合いで広く親しまれています。
「令和」という名前の読み方:多様な組み合わせ例
新元号と同じ「令和」という漢字の名前には、一見「れいわ」という読み方しかないように思えますが、実際には様々な読み方が可能です。過去には、メディアで「れいわ」「のりやす」「のりかず」「よしかず」「れお」「れわ」といった読み方をする「令和」さんが取り上げられました。
特に最近は、愛知県の7歳児の令和(れお)くんや宮崎県の3歳児の令和(れわ)ちゃんのように、音数が少ない読み方が好まれる傾向にあります。これは、漢字の「名のり」の読み方を活用したり、漢字の読みの一部を省略したりすることで生まれるものです。ここでは、男の子と女の子それぞれの読み方の例をご紹介します。
男の子の「令和」という名前の読み方は豊富
「令」と「和」という漢字の組み合わせは、「和」の字の「あき、かず、かた、かつ、たか」といった名のりの読み方が数多くあるため、組み合わせることで非常に多くの読み方をすることができます。例に挙げたもの以外にも、多様な読み方のバリエーションが考えられます。
- おさあき、おさかず、おさかつ、おさたか、おさちか、おさとし、おさとも、おさやす、おさよし
- なりかず、なりかつ、なりたか、なりちか、なりとし、なりとも、なりやす、なりよし、なりより
- のりあき、のりかず、のりたか、のりちか、のりとし、のりとも、のりふみ、のりやす、のりよし
- はるあき、はるか、はるかず、はるたか、はるちか、はるとし、はるまさ、はるやす、はるわ
- よしあき、よしかず、よしかつ、よしちか、よしとも、よしまさ
- りょうか、りょうわ
- れお、れいわ
女の子の「令和」という名前の読み方は可愛らしく短くまとめやすい
女の子の場合も「令和」という漢字の名前の読み方は様々ですが、「和」という漢字は女の子の名前の最後に使われる止め字としても人気が高く、「あ・か・な・わ」といった最近流行りの可愛らしく短い名前にまとめやすいです。漢字の持つ上品さを保ちつつ、響きを現代的にできるのが魅力です。
- のりあ、のりか、のりな、のりわ
- はるか、はるな、はるわ
- よしか、よしな
- りょうか、りょうな
- れいあ、れいか、
- れな、れいな
- れわ、れいわ
ただし、漢字の読み方は多様ですが、戸籍上の読み方は親が自由に決められるため、読み方と漢字の組み合わせが一般的なものから大きく離れすぎると、読み間違いが生じやすくなる点には注意が必要です。
「令」や「和」を使ったおすすめの名前:男の子も女の子も「令」がポイント
新元号にちなんだ名前を付けたいと考えるママやパパのために、「令」や「和」の字を使ったおすすめの名前のアイデアを、男の子と女の子に分けてご紹介します。
新元号「令和」の一番の特徴は、これまで元号で使われていなかった「令」の文字です。「令」を名前に使うことで、新しい時代の始まりと、立派で聡明な人になってほしいという願いを込めることができます。
「令」にちなんだ男の子におすすめの名前5選
最近は音が2〜3文字の名前が人気ですが、「令」の字を組み合わせることで、賢さや落ち着きといった意味合いをプラスできます。特に、名づけで人気のある他の漢字と組み合わせることで、現代的な響きと伝統的な意味合いの両立が可能です。
- 令(れい):一文字で賢さと清らかさを表現できます。
- 陽令(はるよし、あきのり):近年人気の高い「陽」と組み合わせ、明るさと立派さを願う名前です。
- 令翔(はるか、はると):飛翔を意味する「翔」と組み合わせ、知性と飛躍を願う名前です。
- 悠令(ちかのり、ひさなり):ゆったりとした心を意味する「悠」と組み合わせ、穏やかな立派さを願います。
- 令桜(れお):春の象徴である「桜」と合わせ、新元号発表時の明るい雰囲気を思い起こさせる名前です。
「令」のつく名前には「人に信頼され慕われる人になるように」「信頼に足る真っすぐで清い心をもって欲しい」という願いが込められます。近年人気のある漢字「陽」「翔」「悠」などにプラスすることで、名前に落ち着きや品格もプラスされます。
また、新元号発表から改元までの4〜5月のウキウキ気分を思い出させる名前になるように、「桜」や「春」といった季節感を組み合わせるのも素敵なアイデアです。
「令」にちなんだ女の子におすすめの名前5選
女の子の名前として「令」にちなんだ名前を付けたい場合は、「レイ」という音が持つ可愛らしいイメージや、漢字の持つ上品なイメージを活かすのがおすすめです。短く、優しい響きにまとめる工夫をしましょう。
- 令菜(れいな):近年人気の「菜」と組み合わせ、清らかさとみずみずしい生命力を願います。
- 令心(れみ):心豊かに育ってほしいという願いを込めた、優しい響きの名前です。
- 桜令(さよ):春らしさと、品の良さを兼ね備えた、和風の響きが魅力です。
- 令花(れいか):立派な花のように、美しく華やかな人生を願う名前です。
- 令依(れい):人に慕われ、頼られる存在になってほしいという願いを込めます。
女の子の名前は近年、自然に由来する漢字(例:「菜」「桜」「花」)の人気が高い傾向があります。これらを「令」と組み合わせることで、柔らかさの中にある聡明さを表現することができます。読み方の響き、漢字の持つ意味、全体のバランスをよく考慮して決めることが大切です。
名づけの豆知識:「令」の書き方のコツと西暦・和暦の変換
名づけを検討する際、親御さんが気になる点の一つが、その漢字の書きやすさや覚えやすさではないでしょうか。「令和」の「令」は左右非対称であるため、バランスがとりにくいと感じる人がいるかもしれません。また、小学4年生で習う「令」という漢字は、下の部分を「マ」と習うことが多いため、大人が「マ」の形と縦棒で書く形(「フ」に似た形)のどちらが正しい書き方なのか混乱することもあります。
まず、下の部分の書き方について、文化庁では、「マ」の形にしても縦棒の形にしても、どちらも間違いではないとしています。名前に「令」をつける場合は、お子さんにいずれ書き方の違いがあることを教えてあげるとよいでしょう。
また、「令」の漢字をきれいに書くコツは、ひし形を意識して書くことです。幸い、「令」の書き方に悩む人は多いため、現在ではネット上で詳しい解説記事が豊富に出ており、他の漢字よりも逆に書き方のコツが探しやすい状況にあるといえます。
和暦・西暦の変換を覚えるための裏ワザ
新元号が「令和」に決まった際、多くの人が話題にしたのが、西暦から和暦への変換を簡単にするための覚え方です。令和が始まった年(2019年)は、西暦の下2桁の「19」から「18」を引くと「1」になり、令和元年となります。
この変換の裏ワザは、「西暦の下2桁から18を引く」というものです。例えば、2025年の場合、下2桁から18を引くと「25-18=7」なので、令和7年となります。「R18」という言葉は、一度覚えると忘れにくいため、この裏ワザは非常に便利です。
これから生まれるお子さんが成長し、新しい元号になっても、令和の年号は西暦に変換するのが簡単です。令和生まれのお子さんや、名前に「令」「和」がつくお子さんは、特にこの変換方法を忘れにくく、学校などで役立つ豆知識になるでしょう。