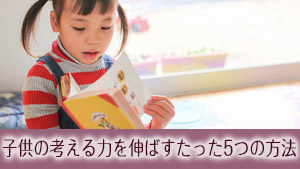子供との根競べに負けない・理屈を通す叱り方

子どもは親が本気で叱っているのか、それともゴネればあきらめる程度なのか試してきます。
大人が考えるより子どもは大人の対応をよく見ていて小中学生になれば矛盾点を突いてきます。
子どもが小さいうちから、本気で叱り、一貫して絶対に基準を曲げない体力、気力が親にも求められます。
特にかんしゃくを起こして火が付いたように泣いたり、だだをこねる場合は
まるで狂ったように手が付けられないほど大声で激しく泣くかもしれません。
公共の場所で子どもが火がついたように泣き出し、叫び始めたら親も恥ずかしさを覚え、一時も早くこの状態を治めたい、と思うでしょう。
まず、子どもの感情を沈める必要があります。泣き止まない子供を持つママはこの7つ方法と接し方を試してみてください。
1何でも言うことを聞いてくれていた親が思い通りにならないので子どもも戸惑っている
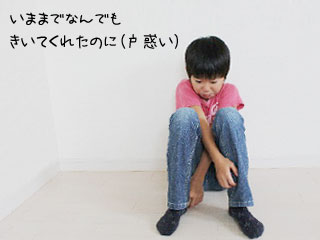
今まで泣けばオムツを変えてくれ、ミルクを飲ませてくれた親が、自分の思い通りのさせてくれないので子どもはそれを受け入れるまで激しく泣き続けるかもしれません。
そんな時は子どもの感情を沈めるため、優しく抱きしめてみます。
しばらくすれば手足をバタバタさせて暴れても無駄だ、ということが分かり、興奮が治まって来るでしょう。
言葉が喋れない時期でも子どもは言葉を理解しています。
なぜ泣いているのか説明しよう考えるとすると少し子どもも冷静になるものです。
2ウソ泣きにはだまされないよ、と思い知らせる
いくら泣いても暴れても「お母さんはあなたの言うとおりにはしないよ。
ゆずらないよ。」
ということを教えてください。
親のほうも子どもの泣き声を聞くのはつらいものです。
早く泣き止ませたいと思うでしょう。
この時、人前で暴れて恥ずかしいから、というような理由で子どもの言いなりになるならその後も同じ手で親を操ろうとしてきます。
「ウソ泣きをしてもだめ。
お母さんにはちゃんとわかっているのよ」とわがままが通らないことを思い知らせます。
3正当な理由で叱る

男の子は特になぜ叱られているのか、どうして悪いことなのか理由を説明してあげないと納得しません。
「こら!」とか「だめ!」だけではなく、なぜいけないのか説明し、これを守らないとどうなるか言って聞かせましょう。
その場合に「騒いだらバスの運転手さんに怒られるからダメ」とか「ほら、あのおばちゃんに怒られるよ」などという意味のない叱り方をしないようにしてください。
そのような叱り方をすると、「他人に見つからなければいいのだ」と子どもは思ってしまい、親をなめるようになります。
4お父さんとお母さんは言うことが違っていてはいけない
お父さんとおかあさんで言うことが違っていてはいけません。
子どもはお父さんとお母さんを仲違いさせて自分の思い通りにしようとしてきます。
子どもは大人が思うよりずっとずるがしこいのです。
子どもに対して夫婦は一枚岩のように絶対に崩せない確固とした存在であるべきです。
これが子どもに安心感を与えます。
5他の子と比べない
おねえちゃんでしょう?お友達の○○ちゃんはできていたよ?そんな叱り方をしていませんか?子供はほかの子どもと比べられると反発を感じます。
親の愛情が感じられないとひねくれて言うことを聞かない子に育ってしまいます。
あくまで子どもを個人として尊重して愛情を持っていることを感じさせてください。
できればほかの子どものいないところで、1人にして叱ってやってください。
子共にも自尊心があるのです。
人と比べるような叱り方をしていると、思春期に入った時「お母さんは私のことが嫌いなんだ」「弟の方がかわいいんでしょう?」と反抗し始めます。
6自分で叱られた理由と言いつけを守れなかったときの罰を考えさせる
ある程度大きくなってきたら「どうしてお母さんが怒っているかわかる?」「どうしていけなかったと思う?」と尋ね、自分で説明させましょう。
同じ失敗を繰り返さないように「今度こういうことがあったらどうしたら言いと思う?」「あなたはお母さんの言いつけを守らなかった。
どんな罰を受けるべきだと思う?」と自分で考えさせましょう。
そして子どもは自分で決めた罰なら守る傾向にあります。
この場合も親はどんなに押しても動かない壁のようにゆるぎない存在であるべきです。
子どものご機嫌を取ろうとしたり、押せば何とかなると思わせてはいけません。
7思春期以降は個性を認めて

子どもにも段々と自分で決める裁量を与えていきましょう。
子どもは親の希望通りの進路を選ぶわけではありません。
親のなりたかった職業、生き方を押し付けてはいけません。
親の期待に過剰に応えようとする子どもに育てるならその後、大人になってからの大きな反抗を始めるかもしれません。
決定的に親子の感情がこじれ、絶縁状態になる可能性もあります。
しかし、人間として間違ったことをしたとき本気で叱ってくれるのは親しかいません。
子どもの頃から愛情を受け、自分のことを一番に考えてくれていたのが親であることを理解してきたなら子どもも親の助言を受け入れるはずです。