子育て中の夫婦喧嘩の主な原因と解決策:産後・共働きで喧嘩が増える理由
結婚し、妊娠を経て、以前は仲の良かった夫婦でも、出産後に夫婦喧嘩の回数が激増したというお悩みを抱える方は少なくありません。「赤ちゃんが生まれて幸せなはずなのに、どうしてこんなにイライラするのだろう?」と悩むママ、そして「妻が急に不機嫌になったりイライラしだすのが理解できない」と感じるパパ、子育て中の夫婦喧嘩の原因は、お互いの状況への理解不足にあるかもしれません。
子育てが始まって夫婦喧嘩が増える原因は、女性側、男性側、双方に潜在しています。夫婦関係を良好に保ち、赤ちゃんにとって安心できる家庭環境を築くためにも、「自分にも相手にストレスを与えている原因がないか」を客観的に見つめ直すことが大切です。お互いの欠点を自覚し、許し合い、歩み寄ることで、真の家族の絆を築いていくことができます。この機会に、夫婦で一緒にチェックしてみてはいかがでしょうか。
子育て中の夫婦喧嘩!夫側(パパ)の主な原因4つ
「赤ちゃんも生まれたし、妻の分までしっかり稼ぐぞ!」と意気込んで頑張っているのに、家に帰れば妻は不機嫌。夜は子どもの夜泣きで眠れず、なぜ喧嘩ばかりなんだ!と感じるパパさんもいらっしゃるでしょう。負の無限ループに陥ってしまう原因は、パパの無意識な言動や行動にあるかもしれません。
1子育てを妻の「仕事」として丸投げしている

父親になったにもかかわらず、帰宅後も休日も子育てや家事を妻に「全て任せた」として、非協力的になる夫がいます。さらに、そのような自分に全く罪悪感を持たず、「子どものことはお前に任せた」と妻に言ってしまう夫もいるかもしれません。このような言動は、当然ながら妻の怒りを呼び起こします。
「男はお金を稼ぎ、妻は家事と子育てをするもの」という価値観は、現代社会ではもはや古いものです。特に、共働き家庭や核家族化が進む現代において、この考えは大きな摩擦を生みます。
仕事で疲れている旦那さんであれば、家にいる時間はゆっくりしたいと思う気持ちは理解できます。しかし、子どもが生まれて親になったということは、昼夜関係なく続く「育児」という共同プロジェクトが始動したということです。それまでの独身時代や夫婦二人の時と同じペースで生活しようとしても、上手くいくはずがありません。
育児は妻一人が担うべき「仕事」ではなく、夫婦が共同で取り組むべき「責任」です。この認識のズレが、喧嘩の大きな原因となります。
2家事・育児に口は出すが、自分は手伝わない
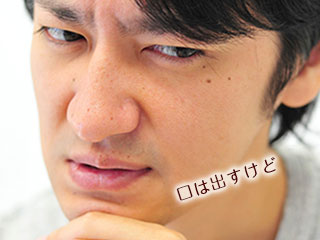
赤ちゃんのお世話で家事が進まず、食卓にスーパーのお惣菜が増えたり、洗濯物が溜まっていたりするのを見て、「一日家にいるのだから家事くらいできるだろう」「赤ちゃんの世話くらい楽なものだ」などと口は出すものの、自分はテレビを見ていて手伝わない夫がいます。このような夫の無配慮な一言は、妻を深く失望させ、夫の人格に疑問を抱き始める原因となります。
「えっ、この人はモラハラ気質だったの?」「少しは状況を想像してよ」「文句があるなら代わりにやって」と思い、愛が冷めていくのは、決して妻のせいではありません。社会で立派に働いているパパならば、部下や同僚を思いやる想像力の大切さは痛いほど分かっているはずです。
妻が猫の手も借りたいほど忙しくても、笑顔で健気に頑張っていることや、休みがなくフラフラなのに根性だけで乗り切っていることは、少し想像力を働かせれば分かるはずです。
頑張っている妻のモチベーションを低下させるような発言は、夫婦間の信頼関係を損ないます。妻が疲弊している時こそ、労いの言葉と具体的な行動によるサポートが必要です。
3子育て中のママの「休憩時間」への配慮がない

休日、妻と赤ちゃんを置いて独身時代のように自由に出歩いたり、頻繁に飲み会などで帰りが遅くなる日が続いたりする夫がいます。このような「父親の自覚がない」と取られかねない振る舞いは、妻の不満を爆発させます。もし妻があなたと同じように、あなたと赤ちゃんを置いて頻繁に外出したら、あなたはどのように感じるでしょうか。
仕事はオンとオフの切り替えがありますが、育児は24時間365日休みがありません。従業員をこれほど働かせる会社があれば、完全にブラック企業と言われるでしょう。頑張って働くためには休憩や気分転換が必要ですが、奥さんには子どもと離れて心身を休める「休憩時間」が自動的には発生しないのです。それは、旦那さんが意図的に作らなければないのです。
「赤ちゃんに泣かれたらどうしよう」と不安になる気持ちは分かりますが、それは妻も同じです。それでも毎日不安と闘いながら「私しかいないんだ」と自分に言い聞かせてお世話をしています。
妻の「一人になる時間」を作らずストレスを溜めさせていると、喧嘩になるのは当然です。奥様をねぎらい、短時間でも「リフレッシュの時間」を確保してあげることが、夫婦円満の鍵となります。
4「母親だから当然」と根拠なく決めつける
生まれたばかりの赤ちゃんのお世話に戸惑っている妻を前にして、「どうして泣いているの?」とただ聞いたり、すぐに赤ちゃんを妻にパスして逃げたりする夫がいます。「あなたは赤ちゃんが泣いたらあやすのは母親の役割だ。母親なんだからそのくらいできて当然だ」と思っていませんか?
泣く理由なんて、初めのうちはママにだって「おむつかな?ミルクかな?」くらいしか分かりません。そもそも、突然父親になったからといって、赤ちゃんの気持ちがテレパシーで伝わってくるわけではありませんよね。母親だって、赤ちゃんの気持ちが分かれば苦労しないのです。
赤ちゃんの泣き声から逃げたり、お世話を妻に一方的に押し付けたりしていると、「どうして私ばかり」「父親は何をしているの?」と妻の不満が限界に達してしまいます。夫婦で協力し、一緒に赤ちゃんのサインを読み解く努力が必要です。
子育て中の夫婦喧嘩!妻側(ママ)の主な原因4つ
赤ちゃんが生まれるまでは、旦那さんが大好きで、優しくてかっこよくて、一緒にいられるだけで幸せだったのに…。どうしてこんなに変わってしまったのだろう?と思っているママさん。パパを変えてしまったのは、もしかしたらママ自身の無意識な言動かもしれません。
1自分ばかりが大変だと主張し、夫を認めない
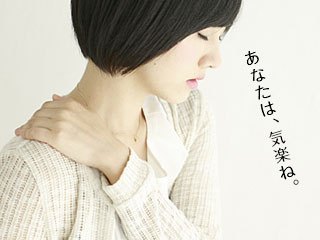
赤ちゃんのお世話は本当に大変です。寝不足になり、泣き声で近所迷惑を心配し、人とゆっくり話せず、自由時間もありません。「赤ちゃんのお世話をしている私の方が大変」「仕事がない時間は家事育児を全部してよ」と夫に過度に求めすぎてはいませんか?
「二人の子なんだし当然でしょ!」という気持ちは理解できますが、その気持ちを表に出して厳しい口調で伝えてしまうと、夫はイライラしてしまいます。自分ばかりを主張し、相手の気持ちを考えない言い方は、誰からも受け入れられないものです。夫だって、仕事で大きな責任を負い、毎日大変な思いで働いています。
一日仕事を頑張って家に帰った後も、あれこれと注文をつけられ、きつい口調で責められては、夫はいつ休めばいいのか分からなくなってしまいます。ねぎらいの言葉を忘れ、否定的な言葉ばかりかけていると、夫が家から足が遠のいても仕方ありません。
2家事や育児の「やり方」の細かな間違いを指摘する

夫が重い腰を上げて家事や育児に参加してくれたにもかかわらず、すぐに細かく間違いを指摘する妻がいます。「洗い物のやり方が違う」「たたむのはこうじゃない」「おしりはもっと丁寧に拭いて」など、あまりにも小言が多いと、せっかく芽生えた夫のやる気は失せてしまいます。
仮にあなたが姑さんから同じ言われ方をしたらどう思うでしょうか?確かに自分のやり方が悪いかもしれませんが、一生懸命やっているのにカチンとくるのではないでしょうか。
母親であり主婦でもある妻は、家では実力No.1で、夫が頑張ってもそうそう勝てる相手ではありません。妻が日頃から夫の努力や参加を認め、立ててあげなければ、常にNo.2の夫のプライドは傷ついてしまいます。
妻が一方的に指示を出し、「ほら、そんなこともできないの?」といった態度を取ると、夫は「どうせやっても文句を言われる」と感じ、家事育児から完全に手を引いてしまう可能性があります。
3友達の夫や周囲の家庭と頻繁に比較する
「友達の旦那さんは家事に協力的」「ご近所はいつも家族で出かけている」など、ことあるごとに周りの家庭と比べる発言をする妻がいるそうです。このような妻の発言に、夫はうんざりしてしまいます。かつて自分に夢中だった妻が、他人と比較して自分をけなす「小うるさい人」に変わってしまったと感じれば、夫だって内心がっかりするでしょう。
確かによその旦那さんは素敵に見えるかもしれませんし、理想と現実のギャップに悲しみを感じることもあるでしょう。しかし、目の前にいる夫こそが、あなたの人生のパートナーであり子どもの父親です。あなたが選んだ人であり、あなたを選んでくれた人なのです。
巡り会えた奇跡に感謝せず、夫に文句ばかり言い、自分の価値観や理想を押し付けてばかりいると、夫があなたを人生で唯一の運命の女性と思い大切にしようとする気持ちが薄れても仕方ありません。比較ではなく、「ありがとう」という感謝の言葉で夫を動かしましょう。
4子どもの教育方針について一方的に決める

幼児教育、習い事、お受験など、子どもの教育方針について夫婦間で考え方が違う場合があります。夫に相談なく一方的に決めてしまうことで、後からもめる原因となるかもしれません。
また、夫に相談せずに教育方針を決めてしまうと、夫が育児全体から「疎外感」を感じ、より非協力的になる、というケースもあります。夫婦共通の教育方針を持って子育てしなければ、子どもも迷ってしまいます。父親である夫を無視することは、子どもの教育や精神的な成長にも悪影響を及ぼす可能性があります。
教育方針が違うからこそ「あなたの考えを教えてほしい」と、参考に話を聞かせてほしいという姿勢を見せることで、夫の心がほぐれる場合があります。男性は、妻から頼られると嬉しいと感じる人が多いため、ぜひ相談する姿勢を意識してみてください。
「パパに話してもわからないから」「面倒くさいことになるし…」などと夫を無視して独断で進めていては、「俺はこの家に必要ないんだ」と寂しがり屋の夫が、家庭内で孤立してしまうかもしれません。
子育て中の夫婦喧嘩を減らすための具体的な解決策
子育て中は、パパもママも心の余裕がない状態です。夫婦喧嘩が急増してしまうのは、以下の要因が大きく関係しているからです。
- 産後のホルモンバランスの急激な変化: 特に産後の女性は、ホルモンバランスの乱れや睡眠不足のため、情緒が不安定になりイライラしやすくなるという身体的な影響を受けています。
- 育児の「不可視労働」による負担: 赤ちゃんのお世話は、授乳、おむつ替え、寝かしつけなど、時間外労働が多く、その多くが周囲に認識されにくい「不可視の労働」です。これがママのストレスを増大させます。
- リフレッシュ不足: 赤ちゃんがいると、時間の拘束が増え、パパもママもリフレッシュする時間がなかなか確保できません。お互いにストレスを溜め、ぶつかりやすくなってしまいます。
これらの状況を理解した上で、夫婦喧嘩を減らすために以下の対策に取り組みましょう。
1. 「労いと感謝」を具体的な言葉で伝え合う
不満や夫婦喧嘩が増えている時は、「相手に対する思いやりが欠けているかもしれない」と、お互いに振り返ることが大切です。妻は夫の仕事への努力を、夫は妻の育児への努力を、「お疲れさま」「いつもありがとう、助かるよ」といった具体的な言葉で伝え合いましょう。
2. 育児の「可視化」と役割分担の見直し
夫が育児の負担を理解できるよう、育児のタスク(例:授乳回数、おむつ替え、夜泣き対応時間)を共有するアプリやメモで「可視化」しましょう。その上で、「夫の担当領域」(例:お風呂、ゴミ出し、週末の朝食作りなど)を明確に決め、「妻の領域」に口を出さないルールを徹底することが有効です。
3. 外部の手やサービスを積極的に利用する
夫の手を借りられない時や、夫も休む必要がある時は、実家だけでなく、他人の手を積極的に借りるようにしましょう。例えば、各自治体のファミリーサポートセンター、一時保育、ベビーシッターサービスなどを利用することは、リフレッシュのための有効な手段です。
また、妻は美容院やショッピングなどのリフレッシュタイムを定期的にとったり、趣味や好きなことをする「自分時間」を作る努力をしましょう。自分への労わりが、結果的に家族への優しさにつながります。
夫婦は合わせ鏡です。労わりと感謝を忘れずに、協力して大変な育児期を乗り越えることで、もっと素敵な夫婦になれるはずです。





