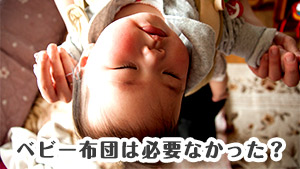赤ちゃんの寝汗は元気の証?体調の悪さが原因?着替えの頻度や汗対策
赤ちゃんが寝ている時やちょっと遊んだ時など、汗びっしょりでビックリすることはないですか?「赤ちゃんは汗っかき」とよく言われますが、どこまでが普通なのかわからないので、赤ちゃんが大量の汗をかいたり、頭だけが汗で濡れたりしていると「これって体調が悪いじゃないよね?」なんて不安になってしまうママは少なくありません。
そこで今回は、赤ちゃんが汗をかくことの重要性に触れながら、赤ちゃんの汗の原因や対策について体験談を交えて詳しくご紹介します。
赤ちゃんが寝汗をたくさんかく理由

赤ちゃんの汗で驚かされるのは、なんといっても寝汗ですね。特に頭や背中、手足の発汗がひどいと、夏の盛りにはお布団が湿ってグッショリになってしまうほどなのですが、心配しなくても大丈夫です。赤ちゃんが寝汗をたくさんかくだけで体調不良を疑う必要はありません。
睡眠中の人間の身体は活動量が少なく、体温を下げるために大人でも一晩でコップ1杯ぶんの寝汗をかくと言われていますが、赤ちゃんは大人よりも体温が高く基礎代謝も活発なので、大人よりも多く寝汗をかく必要があります。一説には赤ちゃんは大人の約2倍も汗をかくとも言われているんですよ。
赤ちゃんは体温調節の機能が未熟なまま生まれてきて、汗をかくことによって体温を調節することを覚えていきます。つまり、起きている時の汗も、寝汗も、赤ちゃんが成長するためには必要なステップなのです。
ただし…
- ここ数日で汗の量が急激に増えた
- 顔が赤くなっていて元気がない
- 汗がベタベタとしている
- 汗をかいているときに呼吸が荒く、熱がある
などの場合は、体調を確認する必要がありますよ。
大抵の場合は赤ちゃんが大量に寝汗をかくことに問題はありませんので、天気の良い時はお布団をしっかり天日干しして、赤ちゃんの寝具を衛生的に保ってあげましょうね。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 赤ちゃんの寝汗の特徴 | 特に頭・背中・手足から大量にかくことがあり、お布団が濡れるほどになる |
| 原因 | 大人より体温が高く基礎代謝が活発なため。寝汗も体温調節の一環 |
| 発汗量 | 大人の約2倍の汗をかくと言われている |
| 発汗の意味 | 汗をかくことで体温調節の機能を学び、成長に必要なステップ |
| 注意が必要な症状 | 急激な汗の増加、顔の赤み、元気がない、ベタつく汗、呼吸が荒く熱がある等 |
| 対策 | 基本的には心配不要。寝具を天日干しして衛生を保つ |
頭が寝汗でグッチョリになる理由は?
私たちの身体は寝入った直後に特にたくさんの寝汗をかく傾向がありますが、赤ちゃんをお昼寝させていると額に汗の大きな粒が次々に浮かび、頭の周りのお布団にグッチョリと汗のシミが広がっていく様子がわかりますね。赤ちゃんの頭が汗で濡れやすい理由としては、血流量が手足などに比べて多いため頭部の温度は高くなりやすいことや、汗が流れ落ちずに髪につくため見るからに濡れている様子が分かることなどが挙げられます。
また、脳はとてもデリケートな臓器のため、熱すぎると機能が低下し身体機能のコントロールが出来なくなってしまうため、赤ちゃんは汗をかいて頭を冷やし脳の温度を一定に保つ必要もあるのです。他にも、外気に触れる手足や頭以外は、服に覆われてなかなか熱を放出できないなどの理由もあり、頭部はとても発汗機能が活発で、身体の他の部分よりも汗をかきやすい構造になっているのです。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 寝汗のタイミング | 寝入り直後に特に多くの寝汗をかく傾向がある |
| 頭が濡れやすい理由① | 頭部は手足よりも血流量が多く、温度が上がりやすい |
| 頭が濡れやすい理由② | 汗が流れ落ちず髪につくため、濡れているのが目立ちやすい |
| 脳の温度調節 | 脳を冷やして温度を一定に保つために頭部から汗をかく |
| 熱放出のしにくさ | 服に覆われた部分は熱が逃げにくく、頭部の発汗が活発になる |
手足がビチョビチョになる理由

寝ている赤ちゃんはしきりに寝返りをうって手足をお布団の外に出してしまうので、ママやパパはひっきりなしに布団をかけ直してあげますが、こうした赤ちゃんの動きは手のひらや足の裏から熱を逃がして体温を調節しているからなのです。
特に赤ちゃんは体温調節を足の裏に頼ることが多く足の裏も大量の汗が出ますが、量が多いだけに放っておくと雑菌が繁殖しやすいという側面もありますので、あまりひどい時はタオルやガーゼなどで優しくぬぐってあげましょう。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 寝返りで布団から出る理由 | 手のひらや足の裏から熱を逃がして体温を調節しているため |
| 足の裏の役割 | 赤ちゃんは足の裏から体温を調整することが多く、大量に汗をかく |
| 雑菌繁殖のリスク | 汗の量が多いと雑菌が繁殖しやすくなる |
| ケアの方法 | ひどい時はタオルやガーゼで優しくぬぐってあげる |
赤ちゃんが汗をかかない2つの病気
赤ちゃんの大量の汗や頭の汗の臭いは気になるかもしれませんが、実は赤ちゃんが全く汗をかいていないということの方が心配なことなのです。汗をかいていないということは、身体の体温調節がうまくいっていないという証拠です。
汗をかけないということは体の中に熱をため込みやすいということなので、汗をかけない赤ちゃんはチョットしたことでうつ熱、めまい、動悸、倦怠感、意識障害などの重篤な症状に発展しやすくなります。赤ちゃんが汗をかかずにのぼせやすい症状が続いている場合には、皮膚科を受診して相談しましょう。
1先天性無痛無汗症
先天性無痛無汗症は、ごくまれに発症する遺伝性の先天性疾患で、身体の周りの熱の変動を察知したり痛みを感じたりする末梢神経が正しく機能せず、痛みを感じることもなく体温調節の必要性を知覚できずに汗を全くかかなくなる病気です。
先天性無痛無汗症の赤ちゃんは痛みを感じず汗をかくことがないので、怪我や骨折、中耳炎など痛みを感じる状況になっても泣かないため親が体の異常に気づくのが遅れる、気温の変動に対応できずうつ熱や低体温症になるなどのリスクが高くなります。
生まれたばかりの新生児の発汗異常は親では気づきにくいのですが、保育器内に入った赤ちゃんの体温が高くなりやすい、生後間もなく行われる先天性代謝異常スクリーニング検査で泣かないなどの様子から、産院で早期発見されるケースが多くなります。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 病名 | 先天性無痛無汗症 |
| 特徴 | 遺伝性のまれな疾患で、痛みや温度変化を感じず、汗をかかない |
| 症状 | 痛みを感じず、怪我・骨折・炎症でも泣かない。体温調節ができない |
| リスク | 親が異常に気づきにくく、うつ熱や低体温症の危険がある |
| 発見の経緯 | 保育器内で体温上昇や検査時に泣かない様子などから、産院で早期発見されることが多い |
2特発性後天性全身性無汗症
特発性後天性全身性無汗症は、遺伝によらず後天的に高温多湿な環境でも汗が出なくなってしまう病気です。発症のメカニズムはまだはっきりとは解明されていないのですが、エクリン腺などの汗腺機能の異常や、体温を調節する交感神経の乱れなどが原因となることがあります。
無汗腺症の治療方法はまだ確立されていないのですが、汗をかけないことで皮膚が乾燥してしまいアトピー性皮膚炎やコリン性じんましんを合併してしまうことがあります。肌荒れやフケのようなものがでてかゆみや痛みを訴えたり、入浴後や寝起きに汗をかかずじんましんがでたりしたら、早めに病院を受診して対処していきましょう。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 病名 | 特発性後天性全身性無汗症 |
| 特徴 | 遺伝によらず後天的に汗が出なくなる病気 |
| 原因と推定要因 | 汗腺機能の異常や交感神経の乱れが関与している可能性 |
| 合併症のリスク | アトピー性皮膚炎、コリン性じんましんを合併することがある |
| 主な症状 | 皮膚の乾燥、かゆみ、痛み、入浴後や寝起きにじんましんが出る |
| 対応 | 早めに皮膚科を受診し、症状の進行を防ぐ |
赤ちゃんは汗をかいている?確認しやすい部位

赤ちゃんが汗をかきやすい体の部位を知っていますか?手足が冷たいと「寒いのね」と心配して着せすぎたり布団を掛けすぎたりするパパやママはとても多いのですが、赤ちゃんが汗をかきやすい部分を触ってみると、薄ら汗で濡れていることが多いので、赤ちゃんの子育てでは汗をかきやすい部位を知っていることはとても大切です。
<赤ちゃんが汗をかきやすい部位>
- 頭や額
- 手の平
- 足の裏
- 背中
- 脇の下
着せすぎや布団の掛け過ぎは赤ちゃんの体温調節を難しくしてしまい、うつ熱や乳幼児突然死症候群の要因になりかねませんので、赤ちゃんが寒いのかもしれないと思ったら一枚着せたり掛けたりする前に、赤ちゃんの背中に手を入れて汗をかいていないかこまめに確認するようにしましょうね。また、室内でのミトンや靴下は赤ちゃんの体温調節の妨げになりますので基本的に必要ありません。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 注意点 | 手足が冷たいからといって着せすぎや掛けすぎはNG |
| 汗をかきやすい部位 | 頭や額、手の平、足の裏、背中、脇の下 |
| 確認方法 | 背中に手を入れて汗をかいていないかこまめにチェック |
| リスク | 着せすぎ・掛けすぎはうつ熱や乳幼児突然死症候群の要因になる |
| ミトン・靴下 | 室内では体温調節を妨げるため基本的に不要 |
赤ちゃんはいつから汗をかくの?
私達大人は暑いと無自覚のまま汗を出して体温の調節をしますが、これは体の中に備わった自律神経の一つである体温調節中枢が指令を出しているからです。ところが生まれたばかりの新生児は、この体温調節中枢の働きが未発達で、汗をかき始めるのは生後4~5日目と言われています。まだまだ汗をコントロールして体温調節をすることが難しく、新生児の発汗量はあまり多くはありません。
そのため、新生児は身体が小さいこともあり気温の影響を受けやすく、気温と一緒に体温が上がったり下がったりしてしまいますので、ママ達が衣類や布団を調節して赤ちゃんの体温調節を補助することが必要です。
寝返りからハイハイができるようになり全身に筋肉がつきはじめる生後8ヶ月頃になると、赤ちゃんは体温調節が少しずつできるようになってきます。とはいえ、大人と比べればまだまだ体温調節ができる状態ではないので、少なくとも2歳過ぎまでは大人がしっかりと体温コントロールを補助してあげましょうね。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 発汗の開始時期 | 生後4~5日目頃から汗をかき始める |
| 新生児の発汗量 | 体温調節中枢が未発達なため、発汗量は少ない |
| 体温の影響 | 体が小さいため気温に影響されやすく、体温が変動しやすい |
| 保護者の役割 | 衣類や布団の調整で赤ちゃんの体温管理を補助することが大切 |
| 体温調節の発達 | 生後8ヶ月頃から徐々にできるようになるが、2歳過ぎまでは補助が必要 |
赤ちゃんの汗腺の発達は3歳までが勝負
私たちの体温を調節する汗腺の発達は、赤ちゃん期の環境が大きく関係しています。暑い気候の地方で育った赤ちゃんは多くの汗をかいて体温を下げるために体の汗腺の数が多く、寒い地方で育った赤ちゃんはあまり汗をかく必要がないために汗腺の数は少なくなるなど、身体が環境に順応して汗腺の数が決まってしまうのです。
汗腺の発達は2~3歳頃までの生育環境によって決まり、その後増えることはないと言われています。汗腺の数が少なければ汗をかいて体温調節をすることが難しくなってしまうため、熱中症になりやすいいというリスクを背負っていくことになります。
「暑くてかわいそうだから」と空調が整った環境で赤ちゃんを育てると、赤ちゃんの身体は汗をかくことを学ぶことができず、汗腺も発達しにくくなってしまいますので、赤ちゃんが熱中症にならない範囲でできるだけ暑さを学ぶ機会を作り、たっぷりと汗をかかせてあげるとよいでしょう。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 汗腺の発達時期 | 2~3歳までの生育環境で決まる |
| 環境との関係 | 暑い地域で育つと汗腺が多く、寒い地域では少なくなる |
| 発達後の変化 | 3歳以降に汗腺の数が増えることはない |
| リスク | 汗腺が少ないと体温調節が困難で熱中症リスクが高まる |
| 対策 | 空調に頼りすぎず、適度に暑さを体験させて汗をかかせる |
赤ちゃんが汗臭いのは普通?

赤ちゃんの臭いというとミルクの甘い匂いを想像してしまいますが、赤ちゃんはとても汗っかきで皮脂の分泌も盛んなため、かいた汗を放置しておくと雑菌や細菌が繁殖してしまい、大人のような酸っぱい臭いや汗臭さを引き起こすこともあります。
また、新生児期~生後3ヶ月頃までの赤ちゃんは、母体から胎盤を通して受け取った男性ホルモンの影響で皮脂の分泌量が一時的に多くなりますので、たくさんの汗をかく頭部は特に脂漏性湿疹にもなりやすく、汗臭さを感じやすくなりがちですが病気ではありません。心配をせずにしっかりとシャンプーをして汚れや臭いを落とし、汗をかいたらすぐに拭いたり着替えたりさせましょうね。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 汗臭さの原因 | 汗や皮脂を放置すると雑菌が繁殖し、臭いの原因に |
| 皮脂分泌のピーク | 新生児期〜生後3ヶ月頃は母体の男性ホルモンの影響で皮脂が多い |
| 頭部の特徴 | 汗をかきやすく、脂漏性湿疹になりやすいため臭いやすい |
| 対策 | 清潔に保つ(汗を拭く・着替える・頭をしっかり洗う) |
| 病気かどうか | 臭いがあっても基本的には病気ではない |
赤ちゃんを着替えさせる頻度は?先輩ママの体験談
赤ちゃんはとても汗っかきですので、夏場や入浴後は特に着替えさせた直後からすぐ汗で濡れてしまうことも…。
先輩ママ達は赤ちゃんが汗をかくとどれぐらいの頻度で着替えさせているのでしょうか?着替えのコツや、肌トラブルの有無なども参考になりますよ。
着替&スキンケアが大事かと
女の子と男の子の双子のママです。二卵性という事もあり、うちの双子は肌のタイプが全く違い長女は肌が丈夫でトラブル知らず、息子はいつも肌がカサカサして新しい下着を着せただけでかゆがって「アーン!」と大泣きです。
新生児の頃は息子が寝汗でムズがって起きたら、その都度夜中に何度も着替えさせて夜泣きされるため、私はボロボロ…。その隣ですんごい汗をかいて、夜中に着替えなくてもあせも一つ作らずにグウグウ寝ている娘…。娘と息子を見ているとこまめな着替えも大事だけど、肌の調子を整えておくスキンケアも大事かなと思いました。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 投稿者 | ぽぽさん(34歳・双子のママ) |
| 双子の肌タイプの違い | 長女は肌が丈夫でトラブルなし。息子は肌が乾燥しやすくかゆがる |
| 寝汗による影響 | 息子は寝汗で不快になり夜中に何度も着替えさせる必要があった |
| ケアの重要性 | こまめな着替えと肌の調子を整えるスキンケアが大切 |
夏生まれは大変!
私自身は12月生まれで、小さい頃に肌トラブルを起こしたことはないそうですが、ウチの娘は6月生まれで、ちょうど肌トラブルが起きてくる生後1ヶ月から暑い夏になってしまったので、あせもが大変でした。おっぱいを飲むだけで洋服がビシャビシャになってしまったので、お着替え大変でしたよ。
気を付けていたつもりなのですが、やっぱり背中と手足のくびれを中心にあせもができてしまって、皮膚科を受診したら、着替える時に沐浴をさせたほうが良いと指導されて、昼間は汗で服がグッショリ濡れてしまったら着替えさせて一緒に沐浴もさせました。寝汗もひどかったため本当は夜も沐浴をした方が良かったのかもしれませんが、私が眠くてとっても無理でしたので、夜中の授乳の後に汗ばんだときは着替えて、濡れたタオルで体を拭いてさっぱりとさせてあげました。幸い秋になって涼しくなったらあせもが治まりました。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 投稿者 | とんこさん(31歳) |
| 状況 | 6月生まれの娘が生後1ヶ月であせもがひどかった |
| あせもの場所 | 背中と手足のくびれ部分にできやすかった |
| 対処法 | 汗で服が濡れたら着替えと沐浴。夜は授乳後に着替えとタオル拭きで対応 |
| 結果 | 秋になり涼しくなるとあせもは治まった |
夜中のお着替えは準備が大事です。
生後1歳6ヶ月の男の子の新米ママです。みなさんは夜中に寝汗をかいた赤ちゃんのお着替えをどうしてますか?うちの子の場合は特にあせもなんかはなくて、夜中に汗をかいているのに気づいても着替えさせずにそのまま朝まで過ごしていたのですが、生後6ヶ月過ぎの夏のある朝、起きると背中やおなかにびっしりと赤いプツプツができてしまって、慌てて夜中も汗をかいて服が湿ったと気付いた時にはお着替えをするようにしました(汗)
初めは面倒だなと思っていたのですが、主人のお姉さんから「夜中は枕元に肌着と乳児服を組んだセットを置いておいて、サッと脱がしてサッと着せて寝るのよ」と教えてもらい、実践してました。着替えたほうが気持ちいいのか、息子もすぐに寝付いてくれたので、着替えさせて正解でした。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 投稿者 | ひなままさん(36歳・生後1歳6ヶ月の男の子のママ) |
| 経験 | 夜中に汗で服が湿っても着替えさせず、朝に背中やお腹に赤い発疹ができた |
| 対応の変化 | 夜中も汗に気づいたらすぐ着替えさせるようにした |
| 工夫 | 枕元に肌着と乳児服のセットを置き、すぐに着替えられるように準備 |
| 結果 | 着替え後は赤ちゃんもすぐ寝つき、効果を実感 |
赤ちゃんの汗対策6つ!寝ているときや夏は要注意
赤ちゃんは私たち大人よりも体温が高くとても汗っかきです。汗をかくことは悪いことではありませんが、汗を放っておくと風邪をひいてしまったり、あせもができてしまったりとさまざまなトラブルが起きてしまいますので、適切に対処していきましょう。夏に役立つ、赤ちゃんのための汗対策を6つご紹介します。
1エアコンなどの空調機器を活用しましょう

汗対策だけでなく熱中症予防のためにも、夏場はエアコンなどの空調機器を上手に活用しましょう。赤ちゃんがいるお部屋でエアコンを使う場合の設定の目安は、室温28℃湿度60%です。赤ちゃんは寝入りばなに体温が上がって寝苦しくなりますので、お布団に入る20分前に設定温度を26℃にして一気に部屋を冷やし、お布団に入るときに28℃に戻して1時間タイマーで切れるようにすると、過ごしやすくなります。
赤ちゃんは風にあたり続けていると体力を消耗してしまいますので、扇風機やエアコンの風が赤ちゃんに直接当たらないように注意しましょう。扇風機を壁に向けて首振り運転をしてお部屋全体の空気を循環させて使うと、風がマイルドになって赤ちゃんでも安心ですよ。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 汗対策と熱中症予防 |
| 設定温度・湿度 | 室温28℃、湿度60%が目安 |
| エアコンの使い方 | 布団に入る20分前に26℃に設定し、一気に冷やす |
| 入床時の温度調整 | 布団に入るときに28℃に戻し、1時間タイマーで切る |
| 風の当て方 | 赤ちゃんに直接風が当たらないようにし、扇風機は壁に向けて首振り運転 |
| 注意点 | 直接風に当たると赤ちゃんの体力を消耗する |
2こまめに沐浴しましょう
赤ちゃんがたくさん汗をかいたなら、着替えだけでなく沐浴をさせてあげましょう。赤ちゃんがまだハイハイをしないうちであれば、洗面器でも十分に沐浴ができます。使うお水は冷水ではなくぬるま湯を使います。ぬるま湯で汗を流すだけでも気化熱で体温が下がり、汗が引くので赤ちゃんもご機嫌になりますよ。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 沐浴のタイミング | 赤ちゃんがたくさん汗をかいたときに行う |
| 沐浴方法 | ハイハイ前なら洗面器でも十分 |
| 使う水温 | 冷水ではなくぬるま湯を使用 |
| 効果 | ぬるま湯で汗を流すと気化熱で体温が下がり、赤ちゃんがご機嫌に |
3背中に挟むタイプのガーゼを活用しましょう
赤ちゃんの寝汗で「せっかくよく寝ているのに、着替えさせるのも…」なんて困ってしまったり、車でのお出かけで背中の汗が気になったりする場合は、赤ちゃんの背中にあらかじめ挟み込めるガーゼ布を入れておくと、濡れた部分だけをサッと引き出せるので便利です。
寝ているときは起きてしまうのが心配かもしれませんが、赤ちゃんは寝入りばなに汗をかきやすいので、ぐっすり眠ったらガーゼを抜き取るのがおすすめですよ。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 用途 | 寝汗で濡れた背中部分を簡単にケアするためのガーゼ活用 |
| 便利さ | 濡れた部分だけをサッと引き出せて着替えの手間を軽減 |
| 使い方の注意 | 寝入りばなに汗をかくので、ぐっすり眠ったらガーゼを抜き取る |
| 外出時の利点 | 車での移動時など背中の汗が気になる場面で便利 |
4ベビー布団を使って下にはバスタオルを敷いておきましょう
赤ちゃんは眠るたびにコップ1~2配分の汗をかきますから、シーツの下にあらかじめバスタオルを1~2枚敷いてから赤ちゃんを寝かせませよう。寝汗で湿ってしまったらシーツとバスタオルを交換すれば、天気が悪くてお布団を干せない日でもカラッとしたお布団で赤ちゃんを眠らせてあげることができますね。
ベビー布団を買わずに、大人用の布団で代用している人も多くいますが、赤ちゃんの汗が気になる場合にはベビー布団の方がオススメです。大人よりも寝ている時間が長く、汗を沢山かく赤ちゃんには、通気性がよく、乾きやすいベビー布団を用意してあげましょう。軽いから万が一、顔に布団がかかったとしても、窒息の危険性がないのも安心です。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 汗の量 | 眠るたびにコップ1~2杯分の汗をかく |
| 対策 | シーツの下にバスタオルを1~2枚敷き、湿ったら交換する |
| 天候の影響 | 天気が悪くてもカラッとした寝床を保てる |
| 布団の種類 | ベビー布団は通気性がよく乾きやすいのでおすすめ |
| 安全性 | 軽くて窒息の危険性が低い |
5クール素材を活用しましょう
最近はクール素材を使ったシーツやまくらカバーなどが市販されていますので、夏の暑い時期は赤ちゃんのお布団にも活用しましょう。ワッフル素材のパジャマなども皮膚にあたる面が小さいので熱がこもらずサラッと着ることができますよ。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 商品例 | クール素材のシーツやまくらカバー |
| 効果 | 熱がこもらずサラッと快適に過ごせる |
| おすすめ素材 | ワッフル素材のパジャマ |
| 特徴 | 肌にあたる面積が小さく熱を逃がしやすい |
6保冷剤などを活用しましょう
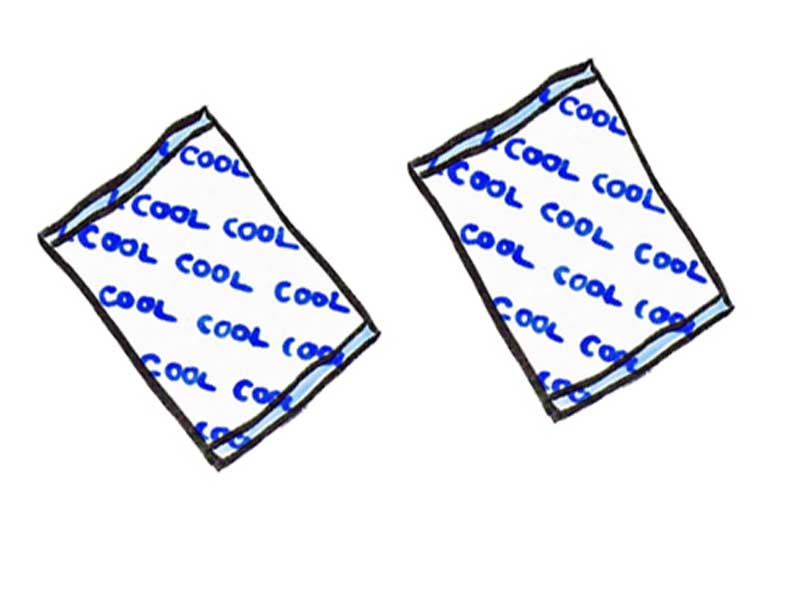
エアコンがなく、暑くて大変な時はアイスクリームやケーキを買った時についてくる小さな保冷剤をストックしておいて、タオルで包み赤ちゃんを冷やしてあげましょう。サイズにもよりますが、炎天下でも2~3時間は十分に冷たさを堪能できますよ。赤ちゃんの首元や脇の下のあたりに挟んであげると、効率よく体を冷やしてあげることができます。
また、大きめのペットボトルに水を入れて凍らせたものを扇風機の前に置くと、風が冷たくなりますよ。チャイルドシート用の保冷材もありますので活用するとよいでしょう。ただし、赤ちゃんが寒くなり過ぎないように、唇の色や背中の暖かさなどはこまめにチェックしましょうね。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 保冷剤の活用 | アイスやケーキの小さな保冷剤をタオルで包み赤ちゃんを冷やす |
| 冷却時間 | 2~3時間程度冷たさを保てる |
| 冷やす場所 | 首元や脇の下に挟むと効率的 |
| その他の方法 | 凍らせたペットボトルを扇風機前に置くと風が冷たくなる |
| 注意点 | 赤ちゃんが冷えすぎないように唇や背中の暖かさをこまめに確認する |
赤ちゃんの汗対策で成長をサポートしましょう!
何かとママを心配させる赤ちゃんの汗ですが、汗をかくことは生き物の正常な反応で、暑い盛りの赤ちゃんは汗をかくことを学んで一生懸命成長しています。着替えや洗濯、スキンケアなどママにとっては手間がかかることも多いのですが、おおらかな気持ちで赤ちゃんの汗ケアのお手伝いをしてあげてくださいね。
また、汗をかくということは赤ちゃんの体からどんどん水分が出ていっているということです。暑い盛りは汗対策と水分補給をセットにするとよいでしょう。