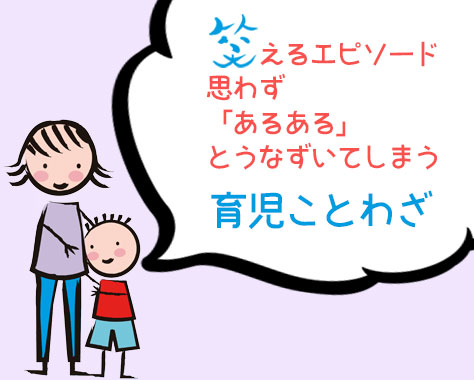トホホ…思わず笑ってしまう先輩ママの育児ことわざ15選!
Twitterで密かに話題になっている「#育児ことわざ」というハッシュタグをご存知でしょうか。育児ことわざとは、ママたちが日頃の育児の中で感じていることを、故事やことわざになぞらえて表現したものです。
そこで、今回は15人の先輩ママによるマーミー版育児ことわざをご紹介します。
「身から出たさび」や「蛙の子は蛙」「果報は寝て待て」など、みんなが知っていることわざをアレンジした、先輩ママたちのトホホな育児ことわざは、子育て中のママなら「あるある!」と、思わずクスっと笑ってしまうものばかりです。
子育てにちょっぴりお疲れのママは、これからご紹介する育児ことわざを読んで息抜きをされてはいかがでしょうか。
先輩ママが日頃感じていることを育児ことわざにしました
泣きっ面にハイハイン(泣きっ面にハチ)

このことわざは、「子どもが泣くと、泣き止ませるために、つい子どもが好きなハイハイン(おやつ)を出してしまう」という意味です。(元のことわざ:不幸や災難の上に、さらに悪いことが重なる意)
赤ちゃんがなかなか泣き止まないと、親の私たちも泣きたくなってしまいます。あやしても何をしてもダメな時は、結局お菓子でご機嫌をとってしまうんです。
そんな時に登場するのが、赤ちゃんの定番おやつ「ハイハイン」です。ハイハインはあまり甘くないので、少しくらいならいいかなと思っています。
今ではもう、子どもが泣き止む方法を家族みんなが知っています。
私の両親や義両親の間でも、「子どもが泣き出したらハイハイン」と言うのが、暗黙の了解となっているんです。
泣けば泣く、為さねば成らぬ同時授乳(為せば成る、為さねば成らぬ何事も)
このことわざは、「双子のうち一人が泣き出すと、寝ていたもう一人の赤ちゃんもつられて泣き出すため、ママ一人で二人同時に授乳しないといけなくなる」という意味です。(元のことわざ:強い意志をもってやれば、どんなことでも達成できる意)
我が家の男の子と女の子の双子の赤ちゃんは、一人が泣いたら必ずもう一人も同時に泣き出します。
そうなると二人同時に抱っこして、右の授乳とミルク、交代して左の授乳とミルクを同時に行わないといけません。双子のお母さんなら絶対に経験があるはずです。
一緒に手を握ってすやすや寝ている姿は本当に天使のようですが、一度泣き出すと小悪魔ちゃんに変身します。
息子にミキハウス(猫に小判)

このことわざは、「幼い息子に高価な服を着せても、その価値は分からないので、平気で泥だらけにしてしまう」という意味です。(元のことわざ:価値の分からない者に高価なものを与えても無駄になる意)
息子は、安い服を着ている時はそれほど汚さないのに、ミキハウスのような高い服を着せると、なぜか汚れるような遊びばかり。一切気にせず泥んこの山に突進していきます(泣)。
しかも、洗っても全然落ちないんです!お出かけ用に奮発して買ったのに。いつもの安い服が10枚は買えるお値段なのに、と悲しくなります。
そして、今ではサイズが合わなくなってしまい、着れないうえに泥んこの跡が残ってしまい、おさがりにもできません。
主人の子は息子(蛙の子は蛙)
このことわざは、「悲しいことや困ったことがあると、すぐに口をハの字に曲げる息子の仕草が主人にそっくりだ」という意味です。(元のことわざ:子は親に似るものだという意)
4か月の息子は、まだあまり動けませんが、体をバタバタ動かすことが大好きです。座っていても前に行ったり横に行ったりしようとしますが、思うように体を動かすことができません。
そうすると、動けないことが悲しいのか、口をハの字に曲げて困ったような顔をします。
また、おもちゃで遊んでいるときに、そのおもちゃが転んで行ってしまい、自分で取れない時も口をハの字に曲げて、「取って!」とアピールします。
それが、あまりにも主人とそっくりで、思わず笑ってしまいました。
同じ釜の飯は食わない(同じ釜の飯を食う)
このことわざは、「ご飯よりもパンが好きな息子が、一人だけ違うメニューを要求してくるので、手間がかかって面倒くさい」という意味です。(元のことわざ:共同生活を送った仲間として親しい関係にある意)
イヤイヤ期の息子は、毎回ご飯を「イヤイヤー」と、体全体を使って断固拒否してきます。その姿はまるで「家族とは同じ釜の飯は食わない!」と言っているようです。
イヤイヤ期の息子の心を簡単に動かすことが出来ずに、しばらく同じ釜のご飯は食べていません。いつか息子が、私たちと同じ釜のご飯を食べてくれる日が来ることを私は願っています。
洗濯機から出た石(身から出たさび)

このことわざは、「ポケットを確認せずに洗濯をすると、突然洗濯機からガラガラという音がしてびっくりする」という意味です。(元のことわざ:自分の犯した悪行の結果として自分が苦しむ意)
子供は石が大好きな時期で、公園に遊びに行ったり散歩をするたびに、石を拾ってはポケットに入れてしまいます。
ある日、それに気づかずに洗濯してしまい、ガラガラと変な音がしたので、確認してみるとポケットに入っていた石が、洗濯機の中で洗われていました。この時の驚きといったらありません。
それからは、洗濯をする前にはポケットをひっくり返して、石が入っていないか確認してから洗うようにしています。
もう少し大きくなると、中身が石から虫に変わる「ポケットから出た虫」状態になると聞いたので、今からヒヤヒヤしています。
子供から出たご飯つぶ(身から出たさび)
このことわざは、「ご飯を食べ終わった子供から、なぜかいろんなところからご飯つぶがポロポロ出てくる」という意味です。(元のことわざ:自分の犯した悪行の結果として自分が苦しむ意)
毎回ご飯を食べ終わった後、娘の口を拭いてきれいにしてあげても、いつも洋服や髪の毛、ひどいときには下着の中など、全く思いもしないところから、ご飯つぶがポロポロと出てきます。
ご飯以外にも、お菓子を食べるときなども、同様の状態が起こる「身から出たお菓子」もあります。
飯よりおやつ(花より団子)

このことわざは、「子供が祖母のくれるお菓子をこっそり食べてしまい、お腹がいっぱいで晩ご飯が食べられなくなる」という意味です。(元のことわざ:物事の本来の目的よりも実利・実益を優先する意)
うちの娘は夕飯前になるとお腹がすいて、おやつをあげるとお腹が一杯になり、ご飯を食べない時があります。
ご飯を準備しても、一口食べてもういらないと言うくらいおやつが大好きな娘です。
ある日、おやつをほとんど食べていないはずなのにご飯を食べなかったので、具合でも悪いかと思ったら、姑がこっそり娘におやつをあげていたことが分かりました。
娘はチョコレートやキャンディが大好きなので、虫歯にならないか毎日ハラハラしながら、娘の成長を見守っています。
花より小石(花より団子)
このことわざは、「きれいなお花よりも、道端に落ちている小石につい夢中になってしまう」という意味です。(元のことわざ:物事の本来の目的よりも実利・実益を優先する意)
買い物や散歩に行く道中、3歩歩けば小石を拾うことに夢中になる2歳の娘です。秋にはもみじ、春にはサクラなど、季節ごとにきれいなお花が咲いていてもほとんど興味を示しません。
とにかく、ひたすら小石を探してはいじっています。最近では拾った小石を、私や主人に「どうぞ」と満面の笑みで渡しにきてくれます。
こんなことをするのは今のうちなので、可愛いなと思う反面、もう少し女の子らしくお花にも興味を示してほしいものです。
触らぬ娘に祟りなし(触らぬ神に祟りなし)
このことわざは、「幼稚園から帰ってきた娘は、疲れているとものすごく機嫌が悪いので、何も言わないほうが喧嘩にならずに済む」という意味です。(元のことわざ:関わらなければ災いを招かずに済む意)
幼稚園から帰ってきた娘の制服を脱がせてあげようとすると、自分でやるからと不機嫌になり、「幼稚園どうだった?」と聞くと「ママはしゃべらないで」と言われてしまいます。
そういうときは、何を言っても反発ばかりなので、何も言わずにそっと見守るほうがスムーズにことが運びます。
三人寄れば良からぬイタズラ(三人寄れば文殊の知恵)
このことわざは、「子供が複数集まると、知恵を出し合って良からぬイタズラばかりする」という意味です。(元のことわざ:凡人でも三人集まって相談すれば、良い知恵が浮かぶ意)
我が家には2人の子供がいますが、1人ずつだと比較的大人しい方なのですが、2人にさらにいとこや友達などが加わると、「コラー!」と怒りたくなるようなイタズラばかりします。
普段はちゃんとトイレでするのに、みんなで裏庭で立ちションしたり、粘土で部屋中をベタベタに汚したり…ほとほと疲れてしまいます。
反抗期は寝て待て(果報は寝て待て)

このことわざは、「手を尽くして子育てしていても、反抗期というものは親の力ではどうにもできないものだから、あせらずに反抗期が過ぎるのを待つのが良い」という意味です。(元のことわざ:運は人の力ではどうにもできないので、あせらず時機を待つのが良い意)
「果報は寝て待て」は、人事を尽くした後は気長に良い知らせを待つしかないという意味が込められています。
そして、これは反抗期の子供を育てている親にぴったりだと思い、「反抗期は寝て待て」という子育てことわざにしてみました。
息子に腕押し(暖簾に腕押し)
このことわざは、「子供に何度注意をしても、すぐに忘れてしまい全く進歩しない」という意味です。(元のことわざ:手応えや効き目が全くない意)
小学生の息子は、着替えたパジャマや靴下は脱ぎっぱなし、脱いだ靴は揃えない、遊んだおもちゃは出しっ放しと、本当にだらしないです。
このまま、だらしない大人になったら困るので、毎回毎回注意するのですが、一晩経つと何故だか綺麗さっぱりと忘れています。
私は息を切らすほど毎回注意しているのに、息子に何も響かないこの無意味さ。あまりの無駄な労力に毎回へこんでしまいます。
子の上の祖母(目の上のたんこぶ)
このことわざは、「孫にとって、祖母が鬱陶しいと感じてしまうことがある」という意味です。(元のことわざ:邪魔で厄介な存在の意)
姑が、孫の学校や友人関係について何でも知りたがり、子供が友達を連れてくると、必ず部屋へ入り込みしばらく友達に質問攻めにします。
また、学校行事も全て出向いては、孫が帰宅してくるとグチグチ小言を言うので、子供が怒り出して姑を鬱陶しがるようになり、しまいには邪魔に感じているようです。
祖母対孫のトラブルが絶えないので、子供にとっては目の上のたんこぶのような状態です。
辛さ過ぎればいい思い出(のど元過ぎれば熱さを忘れる)
このことわざは、「どんなに子育てに悩んでいても、時が経つといつの間にか忘れてしまい、後から振り返ると、どうしてあんなに必死だったのだろうと不思議に感じてしまう」という意味です。(元のことわざ:苦しい経験も、過ぎてしまえばすぐに忘れてしまう意)
この間、息子が熱を出して寝込んだ際に、ベッドで吐いてしまいました。結局は、寝具を一式洗うハメに…。
思い返せば、うちの子が赤ちゃんの時は吐きまくりで、寝具を洗う毎日でした。
あの時は本当に大変だと思っていたけど、時間が過ぎれば忘れてしまうものだなと思いました。