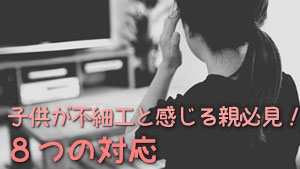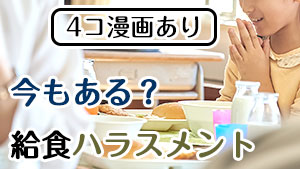育児疲れのママをサポートする方法:産後クライシスを防ぐ旦那さんがすべき具体的な行動7選
お子さまが産まれて幸せなはずなのに、奥さまが毎日イライラ・カリカリしていて戸惑っていませんか?「何をしたらいいか分からないから聞いているのに」と、よかれと思った行動が、かえって奥さまをイライラさせてしまうこともあるかもしれません。
このような状況は、ママの気持ちが分からないからすれ違っているだけであり、産後クライシスで夫婦関係が悪化する原因にもなりかねません。奥さまが心身ともに疲弊している今こそ、頼られ上手なイクメンになって、家族みんながハッピーに過ごせるよう、できることから始めましょう。
ここでは、育児疲れのママが本当に求めている、旦那さんがするべき具体的なアシストを7つご紹介します。これらの行動は、奥さまの負担軽減だけでなく、夫婦の絆を深めることにも繋がります。
育児疲れのママに有難い!旦那さんがするべき7つのアシスト
1お子さまの入浴を「自分の仕事」にする

なるべく早く帰宅し、お子さまと一緒にお風呂に入りましょう。とくに赤ちゃんのうちは「お風呂は俺の仕事だ!」と考え、入浴担当を確固たる自分のポジションとして確保することが重要です。帰りが遅いお仕事で毎日が難しい場合は、休日だけでも担当しましょう。
お子さまを一人でお風呂に入れるのは、特に首が座らないうちは体力勝負です。ゆっくり湯船に浸かることは難しく、上がってからも、赤ちゃんの着替え、自分の着替え、赤ちゃんの水分補給と大忙しで、冬場などは風邪を引かせないかという焦りもあります。
パパが一緒にお風呂に入り、上がった後のケア(着替えの準備など)を分担できれば、ママは本当に楽になります。また、パパが夕食の準備や後片付けをその時間に進めることで、さらに負担は軽減されます。
夫婦の絆を深めるメリット
ママが入浴でリラックスできる時間を作り出すことは、ママの心身の健康を支え、優しく穏やかなママでいてもらうことに繋がります。
2うんちのおむつ替えにも積極的に挑戦する

「おしっこは替えられるけど、うんちの時はお願い…。」こんなことを言っていませんか?おしっこだけのおむつ替えは簡単ですが、うんちの処理までできて初めて「おむつ替えができる」と言えるのです。
確かにうんちは臭いと感じるかもしれませんが、大人の介護でのおむつ替えに比べれば、赤ちゃんのおむつ替えは大変可愛いものです。汚れるのを避けず、率先して行うことで、ママの物理的な負担と心理的な負担を大きく軽減できます。
また、沢山のスキンシップと共に自分のお世話をしてくれるパパを、赤ちゃんは大好きになります。お子さまとの愛着形成を深める貴重な機会と捉えましょう。
夫婦の絆を深めるメリット
「大変なことからも逃げない」という姿勢は、ママからの信頼度を格段に高めることに繋がり、産後クライシスの回避に役立ちます。
3夜泣きの対応をママと交代する

やっと寝かしつけたと思ったら泣き始める夜泣き。眠い中、暗闇でトントンしたり抱っこしたり…。そんなときに、ふと横を見るとグーグー寝ているパパの姿が目に入ったら、ママは「2人の子供なのにどうして私ばかり…」と感じ、孤独感と不公平感からイライラが募るのは自然なことです。
女性は出産しますが、すぐにベテランの母親になるわけではありません。母親だって、眠気やつらさは男性と同じです。むしろ、出産による体力の消耗やホルモンバランスの急激な変化があるため、男性以上に辛いと感じることがあります。
「明日仕事だから無理」という気持ちは理解できますが、睡眠時間を確保することが最優先の仕事ではないママと、交代で夜泣きの対応をしましょう。「気付いた時には抱っこしたり、おむつ替えを手伝う」という姿勢が大切です。
夜泣きのお世話ができないパパも、「夜泣きのお世話を1人でさせてごめんね」「朝までぐっすり眠れなくて辛いよね」などと言葉でねぎらうだけでも、ママは気持ちが楽になり、パパへの愛情や信頼を維持できます。
夫婦の絆を深めるメリット
夜泣きという苦しみを共有したパートナーとして、ママはパパへの信頼感を増し、夫婦の連帯感が強まります。
4休みの日はママに「一人の時間」をプレゼントする

仕事には休みの日がありますが、子育てには休みがありません。ママが「疲れているな」「イライラしているな」と感じたら、「ママのリフレッシュタイム」を確保するために、お子さまを連れて外出しましょう。
近くのコンビニに行くだけでも、公園をぶらぶらしてくるだけでも良いのです。「ちょっと買い物あるから行ってくる」とさりげなく子どもと一緒に出かけるのがおすすめです。ママは思わぬ一人時間ができて、ちょっとゆっくりできるだけでも、気持ちが随分とリセットされます。
「物理的に距離を取る時間」を作ることが、育児疲れの回復には非常に効果的です。この時間は、ママの心身の健康を守るための投資だと考えましょう。
夫婦の絆を深めるメリット
「自分のことを気にかけてくれている」というパパの思いやりにママが気づき、パパへの感謝の気持ちが増します。
5ママの話を目を見てしっかり聞く(傾聴する)

赤ちゃんが小さいとき、ママはお出掛けもままなりません。一日中家にいることも多くなり、夜になって「大人とまともに話をしていない」ことに気づく人も少なくありません。育児は孤独との戦いでもあり、この状態が続くとイライラや不安が増大します。
帰宅したら、まずは手を止めて、ママの目を見てしっかり話を聞きましょう。赤ちゃんの様子や、今日一日の出来事を尋ねて、ママの孤独感を取り除く努力をすることが、夫婦間のコミュニケーションの基本です。
「ただ聞いてくれる人がいる」というだけで、ママの精神的な負担は大きく軽減されます。アドバイスは求められたときだけにし、まずは共感することが大切です。
夫婦の絆を深めるメリット
孤独を支えてくれたパートナーとして、ママからの精神的な信頼が深まり、夫婦関係がより強固なものになるでしょう。
6ママをねぎらい、感謝を言葉で伝える

「いつも育児と家事、本当に頑張っているね」「ありがとう。助かっているよ」などと、言葉で具体的かつ頻繁に伝えるようにしましょう。この一言があるだけで、ママはとても嬉しくなり、これからも頑張ろうと思うモチベーションにつながります。
仕事とは違い、子育てはすぐに結果が出るものではありません。「これでいいのだろうか」と迷いながら日々を過ごしているので、夫に認められることは、ママの自信にも繋がります。ねぎらいの言葉がないと、「自分の努力は無視されている」と感じ、不満が溜まってしまいます。
夫婦の絆を深めるメリット
パパがママをねぎらうことで、ミラーリング効果により、ママもパパをねぎらってくれるようになり、夫婦円満な関係を維持できるでしょう。
7産後のホルモンバランスの乱れを理解し、感情的にならない
奥さまのイライラや八つ当たりがあったとしても、「産後のホルモンバランスの急激な変化や、極度の睡眠不足・疲労が原因かもしれない」と理解を示しましょう。これは、出産後の女性の体に起こる自然な現象です。
旦那さんとしてもイラッとすることがあるかもしれませんが、感情的になってムキになって立ち向かうことは避けましょう。奥さまの精神的なストレスが軽減するように心掛けることが大切です。「俺だって一生懸命やってるだろ」と反論することは、産後クライシスの大きな原因になりかねません。
産後のイライラや情緒不安定は、ママも好きでなっているわけではありません。細切れの睡眠、授乳、抱っこ、家事…とやることは山ほどあり、ママは肉体的にも精神的にも疲労困憊しています。「産後、妻は変わってしまった」と感じる旦那さんも多いですが、これは一時的な体の状態が原因です。冷静に状況を理解し、優しく支える姿勢が求められます。
夫婦の絆を深めるメリット
この時期に医学的な知見に基づき理解を示し、冷静に対応することで、ママはこの困難な時期のパパの対応を「男としての器」として評価します。ホルモンバランスが元に戻ったとき、ママからの尊敬と愛情を得る絶好のチャンスです。