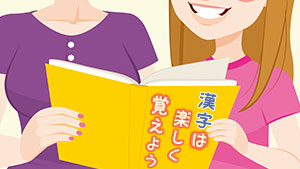学校のルールがちょっとおかしい…変だと思ったママの意見15
お子さんが通っている学校のルールに、「んっ、どういうこと?」と思ったことはありませんか。なんだか理解しがたいけれど、仕方がないから従っているというルールは意外と多いものです。
今回は、「校則がおかしい」と思っているけれど学校に言えないママ15人の意見をご紹介します。きっと「そうそう、うちの学校にも似たような校則がある」と思うママは多いはずです。あまりにも理不尽だと感じる場合は、PTA会議などでそれとなく意見を出してみてもいいかもしれませんね。
学校のおかしなルール15 ママが変だと思うこと
低学年の階段利用制限

私の子供は小学5年生の男子ですが、全校生徒が1000人近くいるマンモス校に通っています。校舎はかなり古く、私たちが通っていた頃とほとんど変わっていません。
そのためか、この学校には、1年生と2年生は階段を使って2階以上に行くことができないというルールがあります。もちろん、先生と一緒の時などは登れますが、休み時間などに自由に行き来することはできません。
明確な理由はわかりませんが、おそらく階段からの転落事故などを防ぐための安全対策ではないかと考えています。息子もルールを守っており、3年生になって2階の教室になったときは、うれしそうにしていました。
公立なのに年に数回しか着ない制服がある
もうすぐ卒業ですが、最後まで納得がいかないのが、公立小学校なのに制服があるという点です。しかも、強制購入なので困ります。
普段は私服登校なのに、制服を着るのは始業式や終業式など、年に数回だけです。それだけの日のために、中学校と同じくらい費用がかかる制服を購入しなければならないことに疑問を感じています。
さらに、小学校は6年間あるため、制服が小さくなり、最低でも1回は買い直す必要があります。中には、3回買い直したという人もいます。
これでは無駄な出費に腹が立ってきます。古き伝統を守っているという名目らしいのですが、伝統よりも家計を守ってもらいたいというのが本音です。また、制服のデザインが変更されると、お古すら使えなくなるので、どこまでも迷惑な田舎特有の学校のルールだと感じています。
誕生日の子がケーキを学校に持参する

息子が通う小学校は、田舎にあることもあり、クラス数も生徒数も少ないです。息子は今小学1年生なのですが、この学校には変わったルールがあります。それは、誕生日の児童本人が、当日またはその前後の登校日にケーキを学校に持っていくというものです。
ケーキは給食の時間まで職員室の小さな冷蔵庫に入れておき、給食の時間に、クラスのみんなで食べるそうです。息子は、教室にあるカレンダーで毎月誰が誕生日なのかを確認しており、自分の誕生日には「ママと手作りケーキを作りたい」と今から楽しみにしています。
祝われるはずの本人側が誕生日ケーキを持っていくなんてちょっと変わっているな、と思いますが、子供たちがお互いを祝えるイベントがあるのは良いことだとも思います。
男の子に対して「さん」付けで呼ぶ
子供は小学1年生なのですが、学校のルールとして、男の子を呼ぶときは「さん」付けにするという決まりがあります。一般的には「君」付けにするのが普通だと思うのですが、1年生の指導時から苗字に「さん」付けをするよう徹底されており、みんなルールを守っているようです。
ただし、休み時間などはお互いをあだ名で呼んでも良いことになっています。授業中や先生の前で、相手の男の子を指名するときだけ「さん」付けにしているようです。
このルール自体には特に不満はありませんが、他の学校の話を聞いたりすると、男の子を「君」付けで呼ぶ方が楽しそうだし、かわいらしいと思うので、なぜこのようなルールがあるのかは不思議です。
体育の授業は素足

子供は小学2年生です。学校の教育方針により、「素足教育」が行われており、体育の授業は基本的に素足です。息子は男子で、素足で走り回るのが好きなので喜んでいます。
私としてはこのルールに抵抗があります。運動場の土はきれいに整備されているようですが、尖った小石やゴミなどで足を怪我しないか心配です。また、足が砂で汚れるので、教室に戻る前に砂を払うのが大変なのではないかと思います。
本人はまだ幼いので汚れは気にしないようですが、体育のある日はいつも足が泥だらけです。また、真冬に素足はとても寒そうですし、夏も炎天下の土は熱くてやけどしそうなので、少し気の毒に感じます。
お昼休み後の着替えの時間がある

娘が4歳の頃に今の地域に引っ越してきました。今は小学2年生になりましたが、通う小学校では、お昼休み後に着替えの時間があります。
小学校は制服がなく私服通学なのですが、どうやら「汗をかいたら着替えましょう」ということらしいです。もちろん体操服は別にあります。
この地域性なのか、娘が通っていた保育園でも「1日に2回ほどのお着替えタイム」がありました。冬場も夏場も季節に関係なく着替えさせる保育園だったので、働いている私にとっては洗濯が大変で、着替えのために服を買い増ししなければならず、とにかく負担でした。「小学校になったら着替えなんかしないだろう」と思っていたら、まさか小学校でもあるなんて驚きです。
子供も、「着替える必要あるのかな?」と言いながらも、周りのお友達がみんな着替えているので、合わせて着替えています。昔はこんなルールはありませんでしたし、今は各教室に冷暖房も設備されている時代です。肌が弱い子に配慮してのルールなのかもしれませんが、正直、着替えの回数が多くて大変だと感じています。
スニーカーソックスが禁止
子供は小学6年生です。通っている小学校ではスニーカーソックスが禁止されています。スニーカーソックス以外であれば、ハイソックス、ミドル丈、ショート丈、柄もの、フリルなど、どのようなものでも全く問題ありません。
なぜスニーカーソックスだけがダメなのか、一度学校の先生に聞いてみたところ、「見た目がよくないから」ということでした。子供が通っている学校はブレザーと半ズボンの制服なのですが、靴はスニーカーであれば何でも良いのに、靴下だけは丈に制限があるのは不思議です。夏の暑い時は、履いてもいいのでは?と思ったりします。
子供はきちんとルールを守り、学校に行く時は長めの靴下、休みの日だけスニーカーソックスを履いています。確かに見た目、制服なのに素足でスニーカーを履いているようにも見えますが、色や柄が自由なのであれば、丈も特にこだわる必要はないかなと思います。
学区外への子供だけの移動が禁止

小学5年生の娘がいます。娘の通っている公立小学校は、市内の中心部にあり、全体の約30%が学区外通学です。
この学校には、「学区外に子供だけで行ってはいけない」「帰りにデパートに寄らない」というルールがあります。
校区内にデパートが4つあるため、学校にお迎えに行って一緒に帰る際、ついついデパートに寄ってしまいます。子供だけで帰る時も、トイレを借りるために寄ったり、デパートの中を通った方が自宅への近道になるお子さんもいるため、このルールは実質守られていない状態です。
もう一つの学区外への移動禁止も、学区外通学のお子さんが多いので、毎日の通学で学区外に移動してしまっています。これもまた、土地柄に合わず、形骸化しているルールだと思います。郊外の学校であれば有効かもしれませんが、都心部にある学校のルールとしては、実情に合わないと感じています。
髪留めのデザインに制限がある

小学校1年生の娘がいます。娘の通う小学校の変だと思うルールは、女の子の髪留めは小さいもののみとしているのですが、実際は「玉」が付いているようなシンプルなゴムはOKなのに、「いちご」や「キティちゃん」など、キャラクター的なデザインのものがダメとされている点です。
要するに、昔からあるようなデザインのゴムは良く、斬新なものはダメということです。先生方はこまめにチェックしているようなので、みんなそのルールを守っていますが、曖昧なルールに子供も親も疑問を持っています。
運動会の時には、ここぞとばかりに皆可愛い(ルールを無視した)髪留めをつけていました。この時ばかりは、注意されても変えることができないと皆考えたのでしょう。
校庭での雪遊び禁止
小学6年生になる子供がいます。もうすぐ小学校を卒業しますが、入学したころから不思議に思っていた校則があります。それは校庭での雪遊び禁止です。
都心のほうは、雪が降ること自体が珍しいですよね。ですから、雪が積もったら校庭で雪合戦をしたり、雪だるまを作ったりしたいと思うはずですが、禁止なのです。
雪が積もると校庭に入ることもできないそうです。私は雪国育ちなので、冬といえば校庭で毎日のように雪合戦をしていました。うちの子は、休み時間に校庭に入ると先生に注意されるということで、雪遊びはしていません。家に帰ってきてからやっています。
怪我や事故を防ぐ目的かもしれませんが、冬の時期にしかできない体験をさせるのも良いのではないかと私は思います。
遠足のおやつ禁止

小学校4年生の子供が通う小学校は、遠足のおやつが禁止されています。遠足といえば、普通「200円まで」などの制限があり、その範囲で駄菓子屋さんに買いに行くのが楽しみだったりするものですが、うちの小学校ではおやつを持っていくことができません。
うちの子供もほかの子供もちゃんとルールを守っていますが、みんな不満は感じているようです。親にとってもおやつは楽しみであると同時に、限られた金額でお菓子を選ぶことも教育のひとつだと思うので、このルールはおかしいな、と思います。
このルールができたのには理由があるそうです。うちの小学校の児童が遠足先でゴミを散らかし、行先の施設に迷惑をかけたことがきっかけでおやつ禁止になったと先輩ママから聞きました。それくらいの理由で…と、子供たちをかわいそうに感じています。
髪型は三つ編みか二つくくり以外禁止
小学校5年生の子供がいます。カトリック系の私立の小学校に通わせており、校則は比較的厳しい方だと思います。小学校入学当時にびっくりしたのが、女の子の髪型に関するルールです。
髪が肩を超えるとくくらなくてはならないのですが、その髪型で認められているのが三つ編みのお下げか、高すぎない位置での二つくくりのみなのです。それ以外は一切禁止です。
長い髪をくくるのは理解できるのですが、ポニーテールがダメなのには正直驚きました。一度先生に理由を質問したことがあるのですが、「ポニーテールだと、後ろを振り向いたときにお友達の顔に髪があたる可能性が高く危険だから」だそうです。
初めて聞く理由で驚きましたが、確かに言われてみて、髪が顔にあたったところを想像してみると、子供だととても痛みが強いかもしれません。
髪飾りも華美なものは一切禁止で、黒か茶色のシンプルなゴムのみです。もちろんルールなので子供には守らせていますし、私も納得しています。
幼稚園児の親にも旗当番の義務がある
私には小学3年生の子供がいるのですが、学校のルールに疑問を覚えたことがあります。週に何度か旗当番と言って、登校時に所定の場所で生徒たちが安全に通学できるように親が見守る当番があるのです。
その当番は、年に数回順番が回ってくるのですが、私には幼稚園に通う小さな子供もいます。小さな子供がいる母親でも旗当番をしなければならず、幼稚園に送る時間と重なってしまうのです。
以前にもクラスの会合で、小さなお子さんがいる家庭には、旗当番を回さないでほしいとお願いしていたのですが、意見は通りませんでした。
同じように幼稚園に通っているお母さんたちと話し合い、PTA会長に意見をぶつけたのですが、それでも旗当番は回ってきたのです。子供は旗当番のルールを知らないのですが、「お母さんはしなくていいよ」と言ってくれます。このルールは少しおかしいと感じています。
保護者全員に下校当番が回ってくる

子供は、小学6年と小学3年と小学1年にいます。学校のルールでPTAの活動として、全員の保護者に下校当番が回ってきます。
下校時間に合わせて、低学年の親は集団下校の際に先頭と後方に付き添い、安全に帰れるように声掛けをしながら帰ります。高学年の親は、危険箇所と思われる交差点に旗を持って立ちます。子供たちは、親が来てくれるので喜んでいる部分があり、よく理解しています。
大切なことかもしれませんが、他の学校にはないため、そこまでしないといけないのかという声も多いです。しかし、この活動は交通事故の防止に役立っていると思います。
先週、残念ながら当番を守らない保護者がいて、その場所の付近で事故が起こってしまいました。この件をきっかけに、改めてこのルールは大切なことだと実感しました。
授業中の挙手が「グー」から始まる
小学校の子供が通っている学校では、授業中に手を挙げる時、最初は「グー」の形で上げます。そして、授業が進んでくると次第に人差し指や、二本指(ピースの形)、三本指になったりします。
授業参観でこの光景を見た時、何を意味しているか全く理解できず、普通に手を挙げてはいけない理由があるのかと驚きました。改めて子供に意味を聞いてみると、なんと「挙手して発言した回数」を表しているんだそうです。
なるほど、最初は「グー」なので0回、そして「人差し指」で1回、「ピース」で2回…となっていくわけですね。先生から見たら、発言していない子がひと目でわかり、次の問題は当たってない子にしようと意識できるルールだと思います。また、子供も競争心からか、回数が多い子に負けじと頑張る気持ちになるようです。