3歳児の叱り方に悩むママへ:効果的な伝え方と先輩ママの具体的方法12選
「七五三」という言葉があるように、3歳は心と身体の発達において最初の節目の時期といわれています。できることが増え、日々の成長に喜びや驚きを感じているママは多いはずです。
しかし、成長の裏側で、それまでは見られなかった自己主張や反抗的な行動が増え、ママを困らせることも少なくありません。そんな時のママの大きな悩みの一つが、「叱り方」ではないでしょうか。
どのような叱り方が子供に効果的で、逆にどのような叱り方をしてはいけないのか、疑問に感じている方もいるでしょう。
ここでは、3歳児の心理や発達を踏まえた叱り方のポイントに加え、先輩ママが実践している効果的な叱り方の体験談をご紹介します。
お子さんの心にママの言葉をしっかりと届けるためには、どのような叱り方が良いのか一緒に見ていきましょう。
第一反抗期真っ只中!3歳児の心理と発達の特徴
一般的に2歳頃から始まる「イヤイヤ期」は、第一反抗期とも呼ばれ、子供の自我(自分自身)が芽生え、自律性が発達している証拠です。この時期の子供は、様々な行動を通して自分の「やりたい」という気持ちを主張するようになります。
毎日のことでイライラすることもあるかもしれませんが、第一反抗期は子供の成長のプロセスとして、温かい目で見守ってあげたいですね。この時期は一般的に4歳頃まで続くとされています。
第一次反抗期とは?
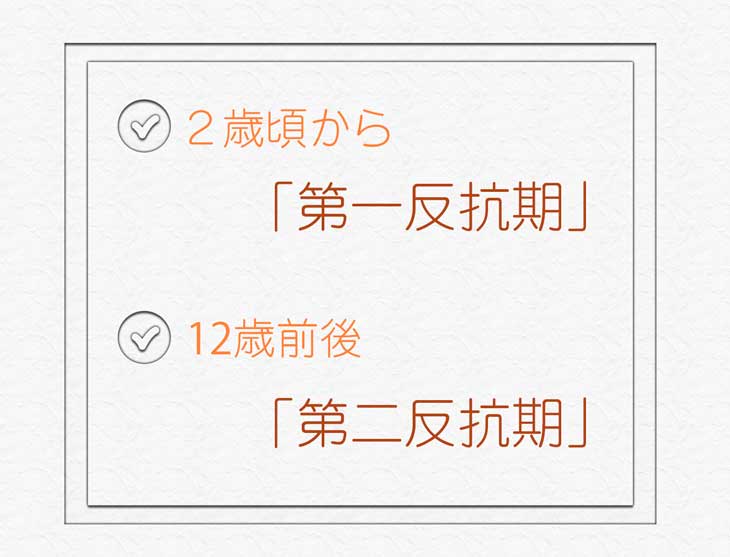
2~3歳頃の幼児期にみられる「第一反抗期」は、自律心が芽生え、親の手を借りずに何でも自分でしたがる「自己主張の増加」が主な特徴です。一方、12歳前後におとずれる「第二反抗期」では、親からの精神的な自立を目指し、反抗的な態度をとることが多くなります。
そんな反抗期真っ最中の3歳児には、自己主張の増加以外にもさまざまな面で成長が見られます。ママは効果的な叱り方を身につけるためにも、3歳児の発達の特徴について知っておくことが大切です。
それでは、3歳児の発達の4つの特徴について具体的に見ていきましょう。
1言葉の理解力・表現力が豊かになる
3歳頃は「言葉の爆発期」を迎え、語彙数が飛躍的に増加します。感情を言葉で表現できるようになり、「嬉しい」や「悲しい」など、感じたことをママに話してくれるようになります。
また、新しい言葉を覚える中で、悪い言葉を試すような「試し行動」を行うこともあります。このような場合は、ママがあまり過剰に反応せず、冷静に注意することを心がけましょう。
2相手の言葉を理解し、会話が成立しやすくなる
おしゃべりが上手になるだけでなく、相手に言われたことを理解できるようになるため、徐々に会話が成立するようになります。
相手の目を見て話を聞けるようになり、「なんで?」「これ何?」と質問攻めにすることもあります。
ただし、子供は遊びに夢中になると、ママの声が耳に入らないことがあるため、叱る際は子供の注意をママに向けさせることが必要です。
3他者の感情を理解し、共感できるようになる
3歳頃になると、他者の立場で考えを理解したり、感情を読み取ったりする心の働きが発達し始めます。この時期は、ケガをして痛がっている相手に対して、いたわりの気持ちを向けたり、困っている人を助けようとしたりする共感的な行動(向社会的行動)が見られるようになります。
他者の気持ちを推測する「心の理論」の発達は、ママとの愛着形成が土台となるため、乳幼児期からしっかりと愛情を注ぎ、信頼関係を深めておくことが重要です。
4お友達との協調性のある遊びが増える

2歳頃は、他の子供と一緒にいても各自がバラバラに遊ぶ「平行遊び」が中心でしたが、3歳になると、おもちゃを共有したり、共通の目的を持って遊ぶ「連合遊び」ができるようになります。
とはいえ、まだまだおもちゃの独り占めや、他の子からおもちゃを奪い取るなどして、ケンカになることもあります。
公共の場所で他の子と一緒に遊ぶ際は、マナーやルールを守らせる必要があるため、「貸して」「どうぞ」「ありがとう」などの社会的な言葉を練習しておくことが大切です。
効果的な叱り方の基本ルール
子供を「叱る」目的は、ママの感情をぶつけることではなく、あくまでも子供の行動を正し、社会的なルールや善悪を教えることです。そのため、怒りにまかせて「怒鳴る」のではなく、冷静に「叱る」ということを心がけることが大切です。
さらに、子供を叱る際は、次のようないくつかの基本ルールに注意しましょう。
- いけない行動をしたらすぐにその場で叱るようにします
- 叱る時間はだらだらと長くかけないようにします
- 大声や暴力で子供を脅さないようにします
- 叱る内容や基準に一貫性を持たせるようにします
叱り方に一貫性がないと、「この前は叱られなかったのに…」「どうして今日だけ叱られるの?」と子供が混乱してしまい、何が正しいのか分からなくなってしまいます。夫婦間や家族間でも、叱る基準を話し合って統一することが重要です。
先輩ママ12人の3歳児の叱り方の具体的方法
「わがままがひどい」「ママの言うことを聞かない」など、子供の困った行動にどのように対処したらいいのか分からない…というママは、先輩ママの具体的な叱り方を参考にしてみてはいかがでしょうか。
先輩ママが実際に実践し、効果的だと感じた叱り方は、大きく次の4つのタイプに分けることができます。
- 叱られている理由を分かりやすく説明する
- 感情的にならないように気持ちを落ち着かせる
- 子供がママの話を聞ける状態になるまで待つ
- 子供がすべきことを明確にして分からせる
ここからは、先輩ママがどのような叱り方をしたのか、4つのタイプ別にご紹介します。具体的な叱り方が知りたいというママは必見です。
タイプ1-理由が分かるように叱る
叱られている理由がわかるように説明します
3歳の娘はかなり反抗的で、口もよく回ります。ちょっと叱ったくらいでは、反対に言い返されてしまうことも多いです。
とても我が強い子なので、少しでも自分の思い通りにならないと、泣きわめいたりもします。ですので、ほとんどの場合、わがままをたしなめるために叱っています。
たとえば、「食べたいメニューじゃないからごはんを食べない」とか「出掛けたくないから着替えたくない」といったケースです。
私が家事をして遊んでくれないから、部屋じゅう滅茶苦茶に散らかしたこともありました。
叱るときは、最初は感情的に怒鳴って威嚇することもあるけれど、必ずなぜ叱っているのか、どうすればママは叱らないのかを伝えるようにしています。
分かるまで何度も伝えて、娘が分かったと言うまでは怖い顔は崩しません。娘が納得したようなら、笑顔で抱き締めてあげています。
娘は、「怖い顔のママが嫌い」「かわいく笑ったママでいて」と言い、笑顔のママでいてもらうために努力しようと心がけてはいるようです。
良いことと悪いことの違いが分かりにくい時期でもあるので、「良いことをしたらママが笑顔」「悪いことはママが怖い顔」ということを、少しずつ理解はしているようです。
子どもといえども、思考能力は大人並みに発達していると感じることがあるので、ただ叱るだけでなく、必ず叱られるには理由があるということを理解してもらうようにしています。
理由をしっかりと教えてあげるようにしています

うちの子は3歳の女の子なのですが、最近よく悪さをします。最近、特に多いのが、1歳になったばかりの弟に意地悪をして泣かせることです。
何度言っても、弟が使っているものを取り上げたり、足で蹴ったりします。
そういうことをすると私は叱るのですが、ただ頭ごなしに叱るのではなく、ちゃんと「なぜダメなのか」を教えるようにしています。
3歳ごろは、物事の理由を聞いてくるし、理解しようとしてきます。なので、ダメだというだけでは納得しないのです。そのため、子供に分かるように必ず理由を教えています。
弟に意地悪をしたら「自分がされたらどうする?お友達に同じことされたら嫌でしょ?悲しいでしょ?だから意地悪したらダメなんだよ」と伝えます。
このように、叱るときは絶対、子供が理解してくれるまで理由を説明するということを心がけています。
すると、娘も理解して意地悪をしなくなります。その後、弟に優しくしている姿を見て、効果的だったんだなと実感します。
なぜ叱られているか理由が分かるように説明します
3歳の娘がいます。上に長男がいて、長男と一緒に成長してきたため、長男よりはしっかりしていますが、負けず嫌いで、長男とよく喧嘩しています。
長男の物をとったり、遊んでいると暴力的になったりします。そんなときは、目を見て話すようにしています。なぜダメなのかを話し、今後こうした方がいいよと教えます。
また、遊び食べをする時は、「お姉さんだよね。座って食べれるね」「これ美味しいよ。ママと一緒に食べよう」「これは何の食べ物かな?これすごいね、こんな形してるよ」と、娘を喜ばせながら食べさせています。
ママが近くにいると安心するようで、一緒に食べてくれます。どうしても時間がなかったり、イライラしてしまいますが、なるべく近くにいるようにしています。
悪いことをして叱るときはママの前に来て、目を見て叱る。そして、どうして叱られているかを教えて、納得してもらうようにしています。
叱る理由をきちんと教えています
3歳の次男です。3つ違いのお兄ちゃんがいるのですが、特にケンカをするわけでもなく、しょっちゅう長男を叩いては泣かせています。
最近は力もついてきたのか、手加減なしで長男を叩くので、いつか怪我をするのではないかとハラハラしています。
叩く事が日常茶飯事で、じゃれている時以外で本気で叩いている時は、部屋の中だろうと外だろうと、その場で叱るようにしています。
子供と一緒の目線に合わせて、両手を握って、どうして叩いたらいけないのかを教えるように叱っています。
叱る時は、どうしてママが叱っているのかを次男に復唱させる事で、次男も怒られた理由を理解できているようです。それでも叩く事を止めないので、根気強く叱ります。
そして、叱った後は、長男と次男お互いを抱きしめ合わせて、仲直りさせます。私も叱った後は必ず次男を抱きしめるようにしています。
とにかく、ママが叱るには理由がある事を、息子には理解させるようにしています。
タイプ2-感情的にならないように叱る
頭ごなしに叱らないようにしています
我が家の息子が3歳を過ぎた頃、お話が活発になり、言っていることもかなり分かるようになると、わざといけないことやいたずらをするようになりました。
例えば、「長椅子の上で飛び跳ねる」「ご飯を食べずにお菓子ばかり食べる」「突然叫び出す」などです。
基本的に言うことを聞かないので、毎日毎日声を張り上げて叱っていました。しかし、頭ごなしに叱ると子供は反発し、泣きます。そして、何度も同じことを繰り返します。
そこで、私が実践したのは子供のやりたいことを認めることです。「○○くん、これがやりたいんだ?」「そうだよね、やりたいよね?」と、子供のやりたいことに理解を示します。
すると、子供は「うん。やりたいの。そうなの」と返事をしてくれます。
そのあとで、「でもね、これは○○だからいけないんだよ」と、ワンクッション入れてから説明すると、比較的高い確率で理解しようとしてくれます。
もちろん、いつもうまくいく訳ではありませんが、大声で怒鳴ったりするよりは、言うことを聞いてくれることが増えました。
できるだけ子供に恐怖を与えずに、お互い笑顔でいられる叱り方をすることで、子供と親である私たちの両方の笑顔が増えると思います。
感情的にならないように心がけています
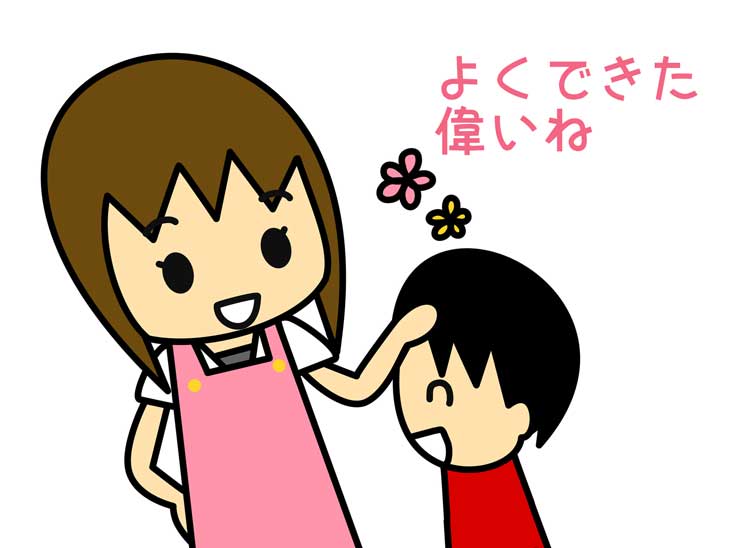
三歳の長男は男の子にしては大人しい方です。でも、やはり怒ることはありました。おもちゃ屋さんに行った時に、おもちゃが欲しいと泣く事が多くとても困りました。
叱る時にまず心がけるのは、絶対に感情的にならない事です。そして、目線は子供に合わせてゆっくり話す事、落ち着かせる事が大切だと思いました。
最初は子供も泣いているので、聞く耳を持ちませんが、泣いているのも疲れてくるので落ち着いてきます。落ち着いてきたらゆっくり話をします。
落ち着いてきたら、もう三歳なので話はきちんと聞いてくれるので、諦めたらきちんと褒めてあげて、時にはお菓子やジュースを一つだけ買ってあげても良いと思います。
感情的になってしまうと、子供が余計に泣いてしまったり、話せる状態ではなくなったりしてしまうので、落ち着かせてあげるときちんと話が出来て、理解もしてくれます。
タイプ3-ママの話を聞ける状態になってから叱る
子供の言いたいことを代弁してあげます
3才の男の子を育てています。怒りたくないなと思っていても、毎日怒ってしまいます。怒る理由は、他の子にすぐに手をあげることです。
児童センターでお友達と遊んでいて、気に入らないことがあれば叩き、私に叱られれば叩き、小学生のお兄ちゃんにまで叩きます。その都度怒っても、効果がありませんでした。
最近、効果的だと思った叱り方は、その場で怒った後に、家に帰ってからも今日あった事を話すという方法です。
怒るというよりは、まずは「お友達に手をあげちゃったのは、○○だからだよね?」と一旦、子どもの気持ちを代弁します。
その後に、「でも、叩くのはダメだったよね、痛いもんね」と言い聞かせます。そうすることで、少しずつ、手をあげなくなってきました。
冷静になって、その時の気持ちを思い出させるのが効果的だったと思います。叱るときはこちらも感情的にならないように気を付けています。
まずは落ち着かせてから話をします
うちは男の子です。よくあるのは、遊びに出かけて帰らないと泣いてしぶる時です。泣いて話を聞かない時は一旦落ち着かせてから、しっかり同じ目線に合わせて話をします。
その時は必ず、正面に座って手を握って話をします。何かやりながら、目線を合わせない状態で話をしても説得力がないからです。
「嫌だ!嫌だ!」と暴れ出したら、いつもこの方法で叱ります。3歳だと言葉を理解しているし、ちゃんと話すと分かってくれます。
急いでいると、つい抱き上げて無理矢理あきらめさせようとしてしまいがちですが、ちゃんと話をするとわかってくれます。
「今日の遊びはここまで。また来ようね」と普通の言葉ですが、目を合わせて話すと案外すんなり帰ってくれて、無理矢理抱き上げるより時間がかからず、私も楽です。
両手を握って目線を合わせます
私には子供が3人いますが、3歳の1番下の娘は色々な事に興味を持ち始め、言葉もどんどん吸収しています。
この年頃はワガママになりやすく、自分の思い通りにならないとごねるので、ダメなものはダメだと叱っています。
その時はかならず、前を向かせ両手を握り、娘と同じ目の高さで叱るようにしています。上の2人を育ててきて、それが1番効果がありました。
子供は、したいことがあると気持ちがそちらに向いてしまうので、分かっているようで理解出来てない時は、今は大切な話をしているのだと分かってもらう事が必要だと思います。
私が心がけているのは、忙しいからといってただ怒鳴るのではなく、ちゃんと言えば小さい子供でも分かってくれるので、理解するまで話すという事です。
タイプ4-子供がすべきことを明確にして叱る
子供の自主性を尊重することが大切です

現在3歳の息子のしつけで悩んでいました。遊びたい物を次々に出して、お片付けをしません。
以前までは「何でお片付けしないの?」「片付けなさい!」など、きつく言葉で伝えていましたが、息子は動くどころか「バイバイ」と逃げて行ったり、怒っている私から逃げようとしたり…。まるで、私の顔色をうかがっているような様子でした。
でも、この方法では、私が感情的に大人の都合を言っているだけだな…と、反省する日々でもありました。
それが、友人ママのお家に遊びに行き同じような状況になった時のこと。友人は叱るどころか、「このおもちゃどこにあったの?ママに教えて!」と、子供に言っているのです。
すると、子供は「僕!知ってる!」「教えてあげる!」と言ったご満悦の様子で、どんどん片づけていきました。もちろん、友人の作戦ではありますが、お見事だと思いました。
さっそく帰宅後、私もその方法で息子にお片付けを促してみると、これまで悩んでいたのが嘘のように片づけてくれるのです。
その様子を見て、ただ大人の意見を言うのではなく、子どもが自主的にやりたくなるような言い方をすることが大事なのだなと思いました。
おだてるとお片付けしてくれます
我が家の3歳児は男の子です。とにかくやってねと言ったことを、ことごとくやりません。本当にやらないのです。
そのくせ、返事だけは一丁前です。「分かった!」と言うくせに何もやらない。おもちゃを片付けるように言ってもやりません。
最初は、とにかく「早くやりなさい!」「なんでやらないの!」と怒鳴ることが多かったのですが、全く効果なし。そして、ある時気づきました。おだてると何でもやるという事に。
「◯◯君のやるところ見てみたいなー」とか「お片付けが上手だって知ってるよ」とか、「優しいからお友達叩いたりしないよね?優しいからごめんねできるよね?」等々。
その際、子どもの目を見てちゃんと伝えることを心がけています。
今までは叱った後、また同じ事の繰り返しでしたが、この方法だと繰り返し同じ事で叱るという事がなくなりました。かなり効果的だと思います。
相手の立場に立って考えさせます
私には3歳の娘がいます。3歳児ともなると口も達者になり、良い言葉もあれば、使って欲しく無い言葉まで、色々なところで言葉を吸収します。
私が娘を叱るのは、妹やお友達に使って欲しくない言葉を言っている時が多いです。
娘はもともとあまのじゃくな性格なのか、機嫌が悪い時や意地悪をされた時に、思ってもいない事を言ってしまいます。
例えば、「○○ちゃんとは遊びたくない!」「○○ちゃん嫌い!」「ぶっ飛ばしてやる!(戦隊モノの影響で…)」などです。
こうした時、私も感情的に「コラ!ダメでしょ!」とどうしても言いがちですが、なるべく落ち着いて娘と同じ目線になり、「お話聞いてくれる?」と声をかけます。
そして、「ママやお友達に嫌いって言われたらどう思う?」と問います。機嫌が悪かったり泣いたりしている時は、少し落ち着くのを待つと「嫌な気持ちになる」と答えてきます。
「じゃあ、どうしたらいいかな?」と、自分で答えを考えるような質問の仕方をすると、自分がしてしまった行為に対して素直に謝ることができます。
もちろん、私もついつい感情が先走り、大きな声で注意してしまいますが、子供から答えを引き出すような質問を心がけ、最後に「もうしないね?」と約束させます。



