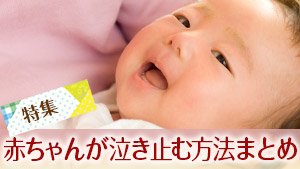【集合住宅の騒音対策】赤ちゃんの泣き声トラブルを避ける7つの方法と近隣住民への適切な対応
アパートやマンションといった集合住宅にお住まいの親御様は、赤ちゃんが生まれると泣き声が周囲に響き、騒音トラブルに発展するのではないかと心配されることが多いでしょう。
実際に、赤ちゃんの泣き声が原因で近隣から苦情を受け、引っ越しを余儀なくされたというケースもあります。「赤ちゃんは泣くのが仕事」と言われるものの、トラブルになる前にできる限りの具体的な対策と、誠意ある近隣対応をしておくことが重要です。
ここでは、騒音トラブルを未然に防ぐための7つの実践的な対策と、万が一クレームを受けた際の適切な対処法について詳しくご紹介します。
1住居選びの基準を見直す:防音性の高い物件を選ぶ

住む場所がファミリー向けか単身向けかによって、苦情の発生率は変わってきます。また、建物の造りが木造か鉄骨造か鉄筋コンクリート造(RC造)かといった構造上の違いからも、音の伝わり方は大きく変わります。
一般的に、RC造(鉄筋コンクリート造)のマンションは、木造や軽量鉄骨造のアパートと比較して防音性が高いとされています。そのため、妊娠中に産後の暮らしを考えて、少しでもトラブルを気にせず、安心して暮らせる住宅に引っ越すカップルも少なくありません。住居選びの際には、建物の構造を必ず確認しましょう。
また、人によって音の感じ方には違いがあり、赤ちゃんの泣き声のような仕方のないケースでも、騒音トラブルに発展するかどうかは、騒音を発している側だけでなく、受ける側の生活環境や子育て経験の有無によっても変わります。子育て経験のある人は比較的寛容に受け止めやすい傾向がありますが、独身の方や年配の男性などは、赤ちゃんの泣き声が不快に感じることも多いということを理解し、配慮することが大切です。
2近隣住人へ事前に挨拶し、配慮の姿勢を示す

赤ちゃんを出産する前、もしくは退院してくる日までに、必ず両隣、上下階の近隣住人に挨拶をしておきましょう。特に、夜泣きでご迷惑をおかけする可能性があることを、具体的な言葉で丁寧に伝えることが重要です。先に挨拶をしておくことで、トラブルをぐんと減らすことができます。
新生児の赤ちゃんは昼夜を問わず泣きますので、どんなに防音対策をしても、泣き声が響いてしまうことがあります。特に夜間は周りが静かなため響きやすく、隣近所の住人にとっては「うるさい」とイライラしたり、逆に「親が赤ちゃんを放置しているのではないか」と心配する人もいます。
ところが事前に挨拶をすることによって、「知らない隣人」から「顔見知りの隣人」へと気持ちが変化し、親近感が湧くためイライラや心配も減ってくるのです。さらに、普段から外ですれ違った時に挨拶をしたり、「いつもご迷惑をおかけしてすみません」などと声をかけることで、こちらが配慮している気持ちが相手に伝わり、その結果相手のストレスが和らぎ、温かい気持ちで見守ろうという配慮を持ってもらえるようになります。このように、コミュニケーションによってトラブルを未然に防ぐことができるのです。
お隣さんからはこんな意見も・・・
赤ちゃんが生まれる前に、お菓子を持って挨拶に来られました。その時に、「泣き声などでご迷惑をおかけするかもしれませんが、できるだけ気を付けます」と一言ありました。
赤ちゃんが生まれてからも、すれ違うたびに「いつもご迷惑をおかけしてすみません」などと挨拶をされるので、こちらも少しくらいうるさくても「子育てがんばってください」という気持ちになります。知らない赤ちゃんが泣くよりは気になりません。
赤ちゃんの泣き声に!3つの物理的な防音対策
経済的にも負担にならない、すぐできる範囲の防音対策を3つご紹介します。防音対策には、音を反射して跳ね返す「遮音」と、音を吸収する「吸音」の二つの考え方があります。
3壁際に高めの家具を置き「遮音効果」を高める
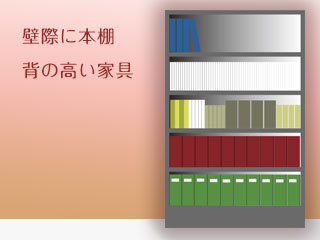
壁越しに音が伝わるのを防ぐために、隣の家と境になる壁に高さのある家具を置くようにしましょう。特に、本棚は本自体に音を吸収する吸音効果があるので、防音対策として非常に有効です。ただし、家具を置く際には、転倒防止のための耐震対策をしっかりと行うことが、家族の安全のために最も重要です。
さらに、市販の遮音シートや吸音材(スポンジ状のものなど)を家具の裏や壁に貼り付けることで、さらに防音性を高めることができます。高価な工事をしなくてもできる、賃貸住宅でも実践しやすい方法です。
4窓やドアの隙間をふさぎ「音漏れ」を防ぐ
ドアや窓の隙間を隙間テープでふさぎましょう。音はわずかな隙間からも漏れていくため、隙間をなくすことで、赤ちゃんの泣き声が外部に漏れにくくなります。隙間テープはホームセンターなどで安価に売られており、手軽に実践できます。
また、基本ですが、赤ちゃんが泣き始めたら、窓と換気扇を閉めましょう。窓を閉めると一定の音は防ぐことができます。盲点になりやすいのが換気扇です。換気扇の通気口からも家の中の声が漏れることが多いので、回していたら必ず閉めるようにしましょう。
5「防音カーテン」に変えて音の出入りを防ぐ
カーテンを厚手のものや、遮音・吸音の効果があるものに変えるのも一つの方法です。外部から入ってくる音だけではなく、中の音が漏れだすことも防いでくれます。
赤ちゃんの夜泣きは、ママも近所の人の迷惑が気になりストレスを溜めがちですが、防音カーテンが閉まっていることで、心理的な安心感を得ることができ、精神的なストレス対策にもなります。厚手のカーテンは断熱効果も期待できるため、冷暖房費の節約にも繋がり一石二鳥です。
6日中の過ごし方によるトラブル対策(泣き声の軽減)

赤ちゃんの脳は、夜にその日1日の出来事を整理していると言われています。時々思い出したかのように激しく泣き出す夜泣きは、昼間の体験が元となっていることも多いのです。そのため、昼間や寝る前に、過度の刺激を与えるのは避けましょう。
赤ちゃんの泣き声による騒音トラブル対策は、何と言っても赤ちゃんを泣かせないことが一番の根本対策です。夜泣き対策をしっかり行い、ママの負担軽減と近隣住人のためにも、夜はしっかり泣かずに寝てもらえるよう、生活リズムを整えましょう。
<夜泣き対策の基本的な生活リズム>
- 昼寝は夕方5時までに切り上げる。
- 入浴は夜7時までに済ませ、スムーズな就寝に繋げる。
- 日中は適度な光を浴びさせ、体内時計を整える。
- 寝る前の授乳やスキンシップで、赤ちゃんに安心感を与える。
7クレーム発生時の「冷静な対応」と「第三者への相談」
どんなに気をつけていても、クレームを受けてしまうことはあります。ポストに手紙が入っていたり、不動産会社を通して苦情が来たり、ひどい場合は壁を蹴られるといった経験をすることもあるかもしれません。こうしたクレームを受けると、家に居づらくなったり、ちょっとでも赤ちゃんが泣けば過敏に反応して抱っこしたり…と、ママが精神的に追い詰められてしまうことがあります。
そんなときは、決して一人で抱え込まずに、パパ(配偶者)にSOSサインを出して相談しましょう。焦る気持ちは赤ちゃんにも伝わり、さらに泣き止まなくなるという負のループに陥ることもあります。相談を受けたパパも、ママの苦悩をしっかりと受け止め、冷静に対処しましょう。
<クレームを受けた際の適切な対処法>
- 感情的にならず、すぐに謝罪する: まずは迷惑をかけていることに対して、誠意をもって謝罪し、配慮していることを伝えましょう。
- 管理会社や大家に相談する: 直接トラブルが深刻化する前に、第三者である管理会社や大家に状況を報告し、間に入ってもらうことで、冷静な話し合いの場を持つことが重要です。
- 一時的に実家などに避難する: ママの精神的な負担が大きい場合は、しばらく実家に帰ったり、環境を変えることも選択肢の一つです。
- 最終手段としての引っ越しを検討する: 近隣住民との関係が修復不可能だと判断される場合は、無理せず子育てに適した環境への引っ越しも視野に入れましょう。
赤ちゃんの泣き声は生活音であり、完全にゼロにすることは不可能です。過度に自分を責める必要はありません。できる限りの対策をした上で、「お互い様」の精神で理解し合えるよう、近隣の方との良好な関係構築を心がけましょう。