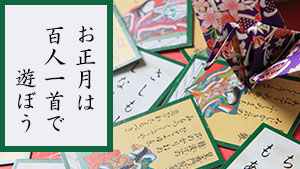お手玉の遊び方を覚えよう!2個や3個を使った練習方法と上達のコツ
小さい頃、お手玉の遊び方を祖父母から教えてもらったという人も多いのではないでしょうか。しかし最近では、お手玉で遊ぶ機会が減りつつあります。日本に古くから伝わる遊びは文化として、これからも大切に受け継いでいきたいものです。
本記事では、お手玉の由来や歴史、種類などの知識に加え、基本的な練習方法をご紹介します。ぜひ、昔を思い出しながら、ご自身のお子さまにも教えてみてください。
お手玉とは?その種類

お手玉は、使う道具は違うものの、世界各地で古くから親しまれている遊びで、大きく分けて二種類の遊び方があります。日本で一般的に行われるのは、いくつかのお手玉を手で投げて遊ぶ「曲芸(振り技)」と、奇数のお手玉を床にまき、その中の親玉を投げながら残りのお手玉を拾い集める「座敷遊び(拾い技)」の二つです。
まずは1個で基本を練習してみよう
最初から2個や3個使ってのお手玉は難しいため、まずは1個での練習から始めましょう。上達への道はここから始まります。基本をしっかり覚えることが上達への近道です。
片手から反対側の手へ投げて受け取る

まず右手にお手玉を持ち、頭の上ぐらいの高さまで投げ、それを左手でキャッチします。次は、左手で頭の上ぐらいまで投げ、右手でキャッチします。この行ったり来たりを繰り返して、お手玉の軌道(放物線)に慣れましょう。
慣れてきたら、お手玉を投げた手と同じ手で受け取る練習をします。右手にお手玉を持ち、目線の高さぐらいまで投げて、右手でキャッチします。左手も同じように練習します。利き手と逆の手で投げてキャッチするのは案外難しいので、何度も練習して手に覚えさせましょう。
手の甲と手のひらを使ってはじく
手をパーにして、手のひらを上に向けてお手玉を乗せ、上にはじき上げたら手の甲でお手玉をキャッチします。手の甲に乗ったお手玉を上にはじき上げたら、手のひらでキャッチします。手を交互にひっくり返しながら、お手玉をポンポンとリズムよくはじき上げるのを繰り返します。
まずは利き手から練習を始め、慣れてきたら利き手と逆の手で練習します。うまくできるようになったら、歌に合わせてやってみると楽しいですよ。
お手玉が上達するコツ

きれいな円を描きながらお手玉を続けるコツは、右から左、左から右へと一定の「リズム」にのることです。一定の速さで体でも同じリズムをつけて動くとよいでしょう。
また、お手玉をするときは手元ばかりを見るのではなく、投げたお手玉が一番高く上がったところを見るようにしましょう。どこに落ちるのかを予測して、手の位置を素早く変えてキャッチできるようになります。
歌に合わせて遊ぶと楽しい
お手玉は、歌に合わせて遊ぶと楽しいですし、リズムにのりやすいのでおすすめです。お手玉遊びをするときによく歌われる曲をいくつかご紹介します。他にも自分の好きな曲で練習すると、早く上達するかもしれませんね。
あんたがたどこさ~
この曲は、さまざまな遊びで使われるためご存じの方も多いと思います。ひとりでお手玉をするときにも、歌に合わせて遊ぶことができますが、大人数で円になって「さ」のタイミングで隣の人に回していくという遊び方もあります。
もしもしカメよ~カメさんよ~

この曲に合わせる遊びはお餅つきです。2人組でお互いの左手のひらを上にして重ねてお手玉を1個乗せます。左手が「臼」でお手玉が「お餅」ということにして、この曲を歌いながら右手で2人交互にお餅をつく動作をします。これを繰り返しながら、好きなタイミングでどちらかがお餅を取ります。取られた人は右手をグーにして、臼の上に置くというものです。
一番はじめは一の宮~
明治時代から歌い継がれてきた曲で、手まりやお手玉の歌として有名です。軍歌「抜刀隊」のメロディが転用されています。東海地方では、ラジオCMのBGMでもあることから、今でも広く知られています。
一かけ二かけ三かけて~
若い女の子が西郷隆盛のお墓参りに行くという内容で、細かい歌詞は全国各地で様々なバリエーションがあります。時代劇の口上や、阿波踊りの囃子ことばとしても使われているため、ご存じの方も多いかもしれませんね。
お手玉を複数使った曲芸(振り技)の遊び方
お手玉を1個使っての練習やコツを学んだところで、2個以上の難易度の高いお手玉の遊び方をご紹介します。いきなりうまくできるとは限りませんが、上手になるともっと楽しくなるので練習してみましょう。
お手玉を2個使った遊び(同時投げ)

お手玉1個で慣れたら、次は2個使って遊んでみましょう。最初は難しいと思いますが、ゆっくり練習していると上達してきますよ。動画を見たり、祖父母に教わったりするといいかもしれません。
両手に1個ずつ(クロス投げ)
2個のお手玉を、左右の手で同時に投げ、互いの手のひらで受け取る練習です。振り技(ジャグリング)の基本となる「カスケード」の練習に繋がります。
- 両手に1個ずつお手玉を持つ
- 両手のお手玉を同時に、左右にクロスする軌道で上に投げる
- 右手が投げたお手玉は左手で、左手が投げたお手玉は右手で受け取る
- これを繰り返す
片手に2個(垂直投げ)
1個を投げて落ちてくるまでにもう1個を投げる、「交代投げ」の練習です。
- 右手に2個お手玉を持つ(左利きの人は左手に持つ)
- 手前のお手玉をまっすぐ上に投げる
- 投げたお手玉が落ちてくるまでに、手元に残っているもう一つのお手玉を投げたお手玉よりも高くまっすぐ上に投げる
- 最初に投げたお手玉を右手で受け取る
- これを繰り返す
お手玉を3個使った遊び(カスケード)

お手玉2個で上手に遊べるようになったら、3個使って遊ぶ、「カスケード」に挑戦してみましょう。できるようになるととてもかっこいいです。最初に投げるのは2個持っている手のほうからで、投げた手と逆の手で受け取ります。コツは、お手玉の軌道をクロスさせ、次の玉を投げる瞬間を待たないことです。
- 右手に2個、左手に1個お手玉を持つ
- 右手のうち、手前のお手玉を左手の方向へクロスする軌道で投げる
- 最初に投げたお手玉が最も高くなる前に、左手のお手玉を右手の方向へクロスする軌道で投げる
- 最初に投げたお手玉を右手で受け取る
- 右手で受け取ったお手玉を左手の方向へクロスする軌道で投げる
- 左手に残っているお手玉を右手で受け取る
- これを繰り返す
みんなで楽しめる座敷遊び(玉入れ)
お手玉は、一人で遊ぶものだと思っている人もいるかもしれませんが、みんなで一緒に楽しむ座敷遊びもあります。歌に合わせたり、みんなで掛け声をかけて遊ぶと楽しいですよ。
ここでは、お手玉を拾い集める「玉入れ」の遊び方をご紹介します。
- みんなで丸くなる
- みんなの真ん中にお手玉を10個くらいかためて置く
- 遊ぶ順番を決める
- まず、お手玉を1個高く上に投げる(これが親玉となる)
- 親玉が落ちてくる前に、かためておいてあるお手玉を投げた反対の手でできるだけたくさん握る
- 投げた親玉を投げた方の手で受け取る
- 順番に繰り返す(何週してもよい)
- 親玉を受け取れなかったり、握った玉を落としたりした場合は0個
- お手玉をたくさん握れた人の勝ち
お手玉は世界中にある

お手玉は日本古来の遊びですが、世界中に似た遊びがたくさんあります。アメリカには、コマのような心棒から数本の棒が立体的に飛び出たもの8~15個とゴムボールを使うジャックスという伝統的な遊びがあります。
イギリスにはファイブストーンという石のお手玉があり、女の子の遊びとして親しまれています。丸い石1個と四角の石4個を使い、丸い石を投げている間に四角の石を取るという遊び方です。
ウクライナには楕円形の木をビニールでおおったもの、カナダには木綿の糸で編んだもの、韓国には陶器でできたものなど、国によってさまざまなお手玉が存在します。
お手玉の歴史
お手玉の歴史には、いくつかの説があります。どれが本当かは定かではありませんが、代表的な説をご紹介します。
- 紀元前5世紀に発明されたのが世界最古のお手玉遊びで、その後シルクロードを通ってインドや中国に伝わり、東へ西へと広まっていったという説。
- 古代エジプト中王国時代の王子のお墓にお手玉のことが記されていることから、4000年の歴史を持つという説。
- 黒海周辺の遊牧民から始まる3000年の歴史説。
- 聖徳太子が使っていた「石名取り玉」が起源となり、お手玉になったという説。
これらの説から、お手玉遊びは人類の歴史とともに長く存在してきたことが分かります。
日本のお手玉のかたち
一言でお手玉といっても、世界にはさまざまな種類のものがあるのがわかりましたね。日本にも伝統的なものとしてたわら型、ざぶとん型、かます型、まくら型の4種類のお手玉の形があります。新しいものも合わせると、もっとたくさんの種類がありますが、ここでは伝統的な4種類をご紹介します。
たわら型
一番シンプルなのがたわら型のお手玉です。中には小豆やペレット状のプラスチックなどが入っています。たわら型のお手玉は着物の端切れなどを筒状にし、両端を絞って留めるだけで作ることができます。
ざぶとん型
たわら型のお手玉の次にメジャーなのがざぶとん型です。一般的に売られているお手玉はざぶとん型のものが多いです。
かます型
片側が空いた袋型のお手玉をかます型といいます。袋型のものの中では一番古いお手玉で、穀物を入れる袋として使っていた「かます」に形が似ていることから、この名前がつきました。
まくら型
見た目が四角いまくらの形をしているのがまくら型お手玉です。これも他のお手玉と同じ材料で案外簡単に作ることができます。
お手玉はどこで買える?

お手玉は、大きなスーパーや百貨店のおもちゃ売り場に売ってあることがあります。百貨店の和風雑貨を取り扱っているお店などにも高い確率で置いてあります。近くのお店で見つけられなかった場合は、インターネットでも買うことができますよ。
また、お手玉は簡単に手作りすることもできます。祖父母なら作り方を知っていることもあるので、聞いてみてもいいかもしれませんね。
たわら型のお手玉を縫ってみよう
お手玉の楽しい遊び方がわかったところで、自分でもお手玉を作ってみましょう。難しいように見えるかもしれませんが、布を縫い合わせて中に小豆などを入れるだけと簡単なのでぜひやってみてくださいね。
用意するもの(1個分)
- 縦10cm×横17cmの布を1枚
- 針
- 糸
- 小豆・大豆や米など軽く一握り程度
たわら型お手玉の縫い方
- 布を半分に折り曲げて、縦10cm×横8.5cmにします
- 柄を内側(中表)にします
- 縦10cmの辺を縫います
- 次に8.5cmの1辺を縫い、ギュッと絞って玉止めします
- 反対側の8.5cmの辺は、2枚重ねないで縫います
- この時、玉止めはしないで針と糸をそのまま残しておきます
- 布をくるっとひっくり返し柄を表にします
- 閉じていない8.5cmの辺から小豆などの中身を入れます
- 糸を引っ張って口を閉じ、玉止めを内側にもぐらせて完成です
お手玉の日がある
「○○の日」はさまざまなものがありますが、実はお手玉の日もあります。1992年9月20日に第一回全国お手玉遊び大会が愛媛県で開催されたことを記念して、9月20日を「お手玉の日」としています。お手玉の日には、祖父母や両親と一緒に、お手玉をして遊ぶのも楽しそうですね。