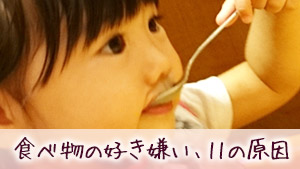食べるのが遅い子供を急かすべき?食事に1時間以上かかる子への対処法

食事をとるのに時間がかかる子っていますよね。家族がみんな食べ終わっているのに、いつまでもゆっくりもたもたと食べていると、ママのイライラも募り、ついつい「早く食べなさい!」と叱りたくなってしまいます。特に朝なんて、1分1秒単位で動いているからこそ、さっさと食べ終わって欲しいという気持ちを抱いてしまいがちです。
一方で、食事くらいゆっくり好きなように食べさせてあげたいと、心の隅では感じているでしょう。ただ、もう少し大きくなった時、例えば、給食が始まると本人が困るのでは?と親として心配ですよね。
昔のように、みんなが他の活動に移行している中で、残されて1人食べさせられるといったことは少なくなっていますが、食べるのが遅いと時間内に満足な量を食べられず、午後の授業や活動に影響を及ぼす可能性も確かにあります。
果たして、食事のスピードはアップさせるべきなのでしょうか?また、ペースを早くすることは可能なのでしょうか?
食べるのが遅い原因や無理なく試せる改善方法を知りつつ、食べるのが遅い子供のメリットにも目を向けていきましょう。
食べるのが遅い7つの原因
食べるのが遅いのには、以下のような原因が考えられます。食生活から性格的な原因までピックアップしてみました。
原因1. 空腹感が少ない
食事の時間があまりにも遅かったり、間食してから時間が経っていなかったりすると、十分な空腹感を感じられませから、必然的に食事が進みません。
子供は単純なので、お腹が減ると欲求を満たすためにしっかり食べることができますが、そんなにお腹が空いていない時には食事自体に興味を示さないことも少なくありません。
原因2.食事の量が多い
食事における適量は、一応の基準はあったとしてもその子によって違うものです。理想とする食事量や摂取カロリーにとらわれていると、その子供には食事量が多すぎるといった事態になかなか気づくことができません。
食事を開始して20分~30分が経過すると、満腹中枢が働き始め、人は「お腹いっぱい」と感じます。食べるのが遅い子は、食事の途中で満腹中枢が働きはじめているため、更に食べるのが遅くなるという悪循環に陥っている可能性があります。
1回の食事量を、約20分、長くても30分くらいで食べきれる量に調整してみましょう。
原因3.食事よりも遊びを優先したい

「ご飯よりも遊びたい!」と言わんばかりに、食事の途中で立ち歩いてしまう子が幼児期には大勢います。その度にママは注意をして座らせますが、少し時間が経つとまた集中力が切れて遊びの方へ気が向いてしまいます。
保育園での1歳、2歳の食事風景を見ればわかりますが、先生が「〇〇くん、△△ちゃん、お皿に残っていますよ」と頻繁に呼びかけていることがあります。立ち歩くまではいかなくても、手元で手遊びをしたり、お口を拭く布巾で遊んでみたりと、隙あらば遊びに向かう子供たちを食事に集中させるのは、大人の声掛けや働きかけが必要と考えましょう。
原因4.唾液の量が少ない
もともとの体質で、唾液の量が生まれつき少ない子がいます。赤ちゃんの頃から、よだれかけを使わなくても過ごせた子供は、唾液の分泌量が少なめの可能性があります。
唾液は、咀嚼と消化の潤滑油として機能します。大人でも起床してすぐは、パサパサのパンが食べにくいですよね。少し飲み物や果物を摂取し、唾液の分泌を促すと、咀嚼しやすくなります。
食べるのが遅い子供は、唾液の量が少ないために、他の人よりも咀嚼に時間がかかっているのかもしれません。体質なので、劇的な改善は難しいかもしれません。お茶や味噌汁、スープなどの水分を取りながら、食事をするように促してあげましょう。
原因5.咀嚼回数が多い
原因4と関連しますが、生まれつき唾液の量が少なかったり、なんらかの原因によって、咀嚼回数が人よりも多いため、食事に時間がかかっていることがあります。
「よく噛んで食べましょう」「30回以上噛みましょう」と言われるように、過食を防止し、消化器官に負担をかけないためには、咀嚼回数が多いのは本来良いことです。子供の喉は細いので、詰まらせる心配も減ります。
咀嚼回数が多い子供の多くは、単なる癖のようなもので、成長とともに適切な咀嚼数に移行しますが、あまりにも咀嚼回数が多い子は、飲み込むことに恐怖心を感じているなど、心の問題が関係する場合もあります。
「もういい加減飲み込みなさい!」と叱るのではなく、お肉はそぼろを使う、とろみをつけるなど、まずは咀嚼が少なくても済むような食事から慣らして、その子が納得する大きさ、咀嚼回数で食べられるように少しずつ促しましょう。
原因6.乳歯が生えそろっていない・噛み合わせが悪い
乳歯は3歳までに生えそろうのが一般的ですが、個人差があります。また、嚙み合わせが悪いと、咀嚼に弊害が出るのは無理のないことですよね。歯の状態で気になることがある場合は、早めに歯医者を受診しましょう。
「噛む」練習をさせることは大切ですが、身体的な発達段階に適していない食事内容では、食べるのに時間がかかってしまいます。
離乳食を終えた1歳半~2歳代の子供の場合、肉や野菜を歯ごたえのある大きさに切って噛む力をつけさせるのは大切ですが、喉に詰まりやすい繊維部分は断ち切るように包丁を入れましょう。
原因7.マイペースな性格
周囲がどんなに急いでいても、それに釣られることなく、自分のペースを維持して食事をする子が存在します。
この場合は、性格によるものとして半分諦めた方がママのイライラも減ります。本人なりに一生懸命食べているのかもしれませんので、特にふざけている様子もなければ、見守る方が良いでしょう。
もともとのんびり屋だったとしても、人の目が気になる年齢になったり、環境によって改善されることは十分にありますので、「今だけのこと」と受け入れましょう。
食べるのが遅い子が普通に食べられるようになるきっかけ
食べるのが遅いのは、成長や環境の変化によっても自然に改善されることもあります。どんな時に、食べるスピードが上がるのでしょうか?
乳歯がすべて生えそろう
3歳を過ぎると、奥歯を含めて乳歯がすべて生えそろう子が大半です。繊維質なものでも嚙み潰せるようになるので、咀嚼も早くなります。
幼稚園・保育園への入園

やはり幼稚園や保育園へ入園すると、子供は環境に適応しようとします。集団生活での食事は、家庭での食事とは違った雰囲気があり、互いに刺激をしあって良い方向に進むケースはよく聞かれます
家ではこんなにスローペースなのに、集団生活で困っていないだろうか…と案じていても、特に先生から何も指摘されていないなら心配ありません。好き嫌いもそうですが、保育園や幼稚園だと家よりも食べられる子も多いものです。
小学校への入学
幼稚園や保育園でも、食べるのが遅い子はいますが、小学校へ上がると食べる速度が上がる子は大勢います。身体が大きくなり、咀嚼力が上がったり、一度にまとめて食べられる量が増えたりすると、自然と食べるスピードは上がっていくものです。
そして、もう一つの要因として、良い意味でのプレッシャーがあります。小学校での集団生活は、遅れてしまうと少し恥ずかしい思いをすることがありますよね。それを防ぐ気持ちが、食べるスピードをアップさせるのでしょう。
食べるスピードを少しでもアップさせる改善方法
食事に対して負のイメージが湧いてしまわないように、負担なく食事のペースを上げられる方法をご紹介します。
1.原因行動を見極めよう
「食べるのが遅い」と単純にくくってみても、一体どの場面が原因で遅くなっているのでしょうか?原因行動がわかれば、親としても的確なアドバイスや言葉がけをすることができます。
お子さんによってどのシーンでつまずいているのか、一度よく観察してみてください。
- 食べ始めが遅い
- 一口に食べる量が少ない・多い
- 咀嚼時間が長い(異常にモグモグしている)
- 箸を置いている時間が多い
2.テレビなど気が散る原因は取り除いておく
食べ始めが遅い、よく箸(スプーン・フォーク)を置いてしまう、とにかく遊びたがっているなどの原因がある場合、まずは食事に集中する環境を整えましょう。
テレビやおもちゃは子供の気が散る元です。「なんとなく食べている」「味がわからないままただ咀嚼しているだけ」、このような「ながら食べ」にならないようにしましょう。
3.一口の適量を教える
一口に入れる量が少ない子には、はじめはスプーンですくってあげながら適量を覚えてもらいます。一口の大きさを正しくスプーンですくえるようになれば、改善が見込めますよね。
また、箸を置いている時間が長い子には、口の中のものがなくなった頃を見計らって、次の一口を促す言葉がけをしましょう。「次は何食べようか?」といった具合です。
4.一回の食事量を減らす
毎回のように、食事に集中できない子供には、思い切って食事量を減らしてみましょう。だらだらと食べて食事への意欲を低下させるよりも、短時間で少量でもきちんと完食をして達成感を得ることを優先させましょう。
「もう少し食べてみたいな」「おかわりしたいな」そう思ってもらえれば大成功です。
5.箸の練習は焦らない

自分でスプーンやフォーク、そしてお箸を使って食べるのが下手な子は、食事への意欲も低下しがちです。お箸の使い方の練習は必要ですが、食事そのものがストレスになってしまうのは好ましくありません。
最初はお箸で頑張らせても、満腹中枢が働く前に、スプーンやフォークに変えてみましょう。忙しい朝は、手づかみで食べられるもの、スプーンで食べるものを中心に食事の支度をしてみましょう。
6.丼やワンプレートで食べやすくする
食べるのが遅い子に少しでも早く食事をしてもらうには、丼ぶりものなど、ご飯とおかずがセットになった料理がおすすめです。ビビンバや具材をたっぷりのせたオープンサンドイッチなら、野菜もたくさん摂れます。
7.時間が来たら切り上げる
遊び食べが激しい、ふざけて食事が進んでいない場合には、あらかじめ決めた時間で区切って食べさせる練習をするという方法もあります。少々荒療治ではありますが、体質に問題がなく、本人の努力で改善が見込める場合には効果を発揮するでしょう。
教訓的に空腹を感じることができたなら、食事は集中してしっかりと食べなければならないと理解してくれるはずです。
食べるのが遅い子供は、将来的なメリットも大きい!

食べるのが極端に遅い場合、無理のない範囲で改善を目指すことは大切です。しかし、どうやっても食べるのが遅い子供を、無理やりにでも早く食べさせる必要があるかというと、答えはNOです。
食べるのが遅いというのは、健康面を考えると、実はメリットも大きい生活習慣です。
早食いと肥満に相関関係があるのはよく知られている通りで、厚生労働省などの国の機関でも「ゆっくり噛んで食べること」は肥満の治療としても有効だと示しています(注1)。また、名古屋大学院で行われた研究によると、食べる速さが早い人ほど肥満度が高いだけでなく、インスリンが正常に働かなくなるインスリン抵抗性が高いというデータが出ています(注2)。
食事を摂ると、血糖値が上がりますので、通常は膵臓からインスリンを分泌させ、糖分を全身の細胞へ運ぶことで、血糖値を正常値に戻します。このインスリン分泌が上手くいかないのが糖尿病で、血糖値を下げるために、インスリン注射を打つなど、外からインスリンを摂取する必要が出てきます。
子供の一生涯に及ぶ肥満や糖尿病などの生活習慣病といったリスクを考えると、食べるのが遅いことを無理に改善するべき理由はありません。
「集団生活で不利なのでは…」という心配も理解できますが、幼児期は、その後の人生の食生活の基礎を培う大切な時期ですし、無理に速く食べさせると、未発達な消化器官に負担をかけることになります。
楽しくおいしく食事を摂れているのなら、スピードに関しては、今すぐに無理に取り組むべき課題ではないと考えましょう。