鍵っ子は何年生から?情緒不安定になる?安全な鍵の持たせ方と小学生の留守番対策
子供の小学校入学を機に働きに出るママは多く、放課後子供だけが留守宅で過ごす「鍵っ子」が増えています。家庭をもった女性の社会進出がますます推進され、今後も増加が見込まれる鍵っ子。特に小学校低学年のお子さんをお持ちのご家庭では、子供だけで留守番させることに問題はないのか、安全面や情緒的な影響について心配になりますよね。
今回は、現代の鍵っ子事情、鍵の紛失を防ぐ安全な持たせ方、起こりやすいトラブルへの対策、そして鍵っ子は何年生から始めるべきかといった問題について、体験談なども交えながら詳しくご紹介していきます。鍵っ子のママの不安を和らげてくれる、おすすめの留守番対策もご紹介しますので、ぜひ参考にして下さいね。
鍵っ子の意味と現代の背景

「鍵っ子」とは、父親や母親が日中自宅外で働いている家庭の子供で、自分のカギを与えられて持ち歩き、小学校から帰宅した時などに自分で鍵を開けて留守宅で過ごす子供を指す言葉で、「留守家庭児童」とも呼ばれます。
家族の形態やライフスタイルは時代によって大きく変わり、現代において鍵っ子が増えている背景には、主に次の社会的な変化があります。
- 都市部への人口集中による住居形態の変化(集合住宅の増加など)
- 核家族化の進行(祖父母との同居が減少)
- 共働き世帯および女性の社会進出のさらなる推進
鍵っ子が全国にどれくらいいるのか、詳しい統計データはありませんが、政府をあげての女性の社会進出の推進ムードが高まっていることから、近年母親の就業率は徐々に向上しており、学童保育の需要の伸びとともに鍵っ子も増え続けていると予想されています。
鍵っ子はいつから始めても大丈夫?年齢の目安と学童保育の現状

「鍵っ子」はその名の通り、自宅の鍵を子供に持たせなくてはいけません。そのため親としては、「子供だけで留守宅で安全に過ごせるか」と「家族の財産が保管されている自宅の鍵を子供が責任をもって管理できるか」といった二重の不安があり、鍵っ子は何年生から始めるかについては、小学校入学前後の多くのママが悩むポイントでもあります。
一般的に、何歳くらいなら安全にお留守番ができて、安心して自宅のカギを子供に預けることができると考えられているのでしょうか。
学童保育の利用状況と鍵っ子の年齢
「◯歳になれば鍵っ子になっても大丈夫」という明確な線引きがあるわけではないのですが、以前は学童保育(放課後児童クラブ)の利用年齢が小学校3年生までとされていた地域があったため、一般的に鍵っ子になる子供は小学校4年生以降が多いという傾向がありました。
しかし、現在は児童福祉法の改正により、学童保育は小学校6年生まで利用できることになっています。ただし、施設や地域の定員の問題から、特に小学校4年生以降の高学年になると、待機児童が多くなったり、低学年が優先されたりする結果として、利用できずに鍵っ子にせざるを得ないケースも依然として存在します。
子供の精神的な成長には個人差が大きく、小学校4年生になったからといって安心して自宅の鍵を預けたり、大人の目のない場所で留守番をさせたりすることができるとは言い切れません。鍵っ子にする年齢は、あくまでもその子供の性格や能力をよく見極めて判断していく必要がありますね。
鍵っ子になる条件と親の準備
放課後一人で自宅に帰り、鍵を開閉して、親が帰宅するまで数時間を子供だけで過ごすのであれば、少なくとも次の約束事やルールが守れること、そして段階的な練習ができていることが条件になるでしょう。
- 自分で鍵の開け閉めができる、大事に保管ができる
- 遊びに出かけるときには自宅の鍵をかけるという、防犯上の取り決めを守ることができる
- インターフォンや電話が鳴った時の対応の取り決めを守ることができる
- 火や刃物など、危険なことをしないという取り決めを守ることができる
- 万が一の時は、親や近所の人に知らせるという緊急時の取り決めを守ることができる
- 親に言われたことを守れる自制心がある
特に、初めて鍵っ子になる場合は、最初は数十分から、親が近くにいる状態でのお留守番練習から始め、徐々に時間を延ばすなど、段階を踏んで慣れさせることが大切です。子どもがルールをきちんと守れているか、冷静に評価してから本格的に鍵っ子生活を始めましょう。
鍵っ子への憧れと現実

今小学6年生の男の子と、小学4年生の女の子がいる母親です。私は子供を産んでからも仕事を続けていますので、2人の子供は小さな頃から保育園、学童に通わせています。
うちの地区はお兄ちゃんが小学校3年までは学童で預かって貰えましたが、その後は鍵っ子になりました。下の娘はとてもしっかりしていて、小学2年生頃から「あたし、お留守番してる」なんてことをよく言うようになったので、鍵っ子にしても大丈夫かなと考えて、練習のために一人でお留守番をさせることにしました。
もちろん、まだ不安な年齢なので、私が出かけた振りをして近くで様子をうかがうという偽外出だったのですが、「約束はまもるから、絶対大丈夫!」とニコニコと私を見送った10分後に、娘がいそいそと鍵もかけずに勝手に公園へ遊びに行ったのを目の当たりにし、やっぱり信用できないと思って、小学2年生での鍵っ子デビューはあきらめました。
子供にとって親の目のない留守番は「あれもやってみたい、これもやってみたい」という好奇心を掻き立てられることで、分別がついていないととんでもないことをしでかすものだと実感しました。自制心がつくまでは、親の見極めが大切だと感じました。
日本と海外の鍵っ子事情の違い(法的なリスク)
一定の年齢になれば、日本ではごく当たりまえの子供だけのお留守番や鍵っ子。実は世界を見渡すと、日本のように子供を一人にする先進国って珍しいんです。例えばアメリカの一部の州では、法令で「13歳未満の子供を留守番させてはいけない」と明確に定められている地域もあり、アメリカ、イギリス、カナダなどでは、子供を一人で留守番させることが、状況によってはネグレクト(育児放棄)と見なされ、保護者の責任を問われる法的リスクがあるんですよ。
一方、お隣の韓国では鍵っ子が増えてその危険性が社会問題化し、中国では両親が長期間留守にする「留守児童問題」が深刻化するなど、子供の鍵っ子事情は国や地方によっても扱いが違います。
比較的治安の良い日本だからこそできる子供の鍵っ子ですが、日本でも鍵っ子を狙った悪質な犯罪の事例もありますので、安全だと頭から思い込むのではなく、子供に危険があるかもしれないと考えて、防犯対策を徹底することが大切ですね。
鍵っ子は寂しがり?性格や情緒への影響と安心感の確保
家に帰っても「ただいま」と大人が迎えてくれない鍵っ子は淋しいのではないかと、性格や情緒への影響が心配になるママも少なくありません。その反面、子供が早いうちから自立心を身につけ、責任ある行動がとれるようになるという指摘もあり、賛否両論で意見は分かれます。
鍵っ子になること自体が、直ちに情緒不安定につながるわけではありませんが、孤独感や不安感が強くなると、精神的な負担となる可能性があります。親が日頃から心のケアを意識し、安心感を確保することが極めて重要です。
実際に鍵っ子であることが子供の性格などにどのような影響を与えるか、体験談を見てみましょう。
電話嫌いになりました…
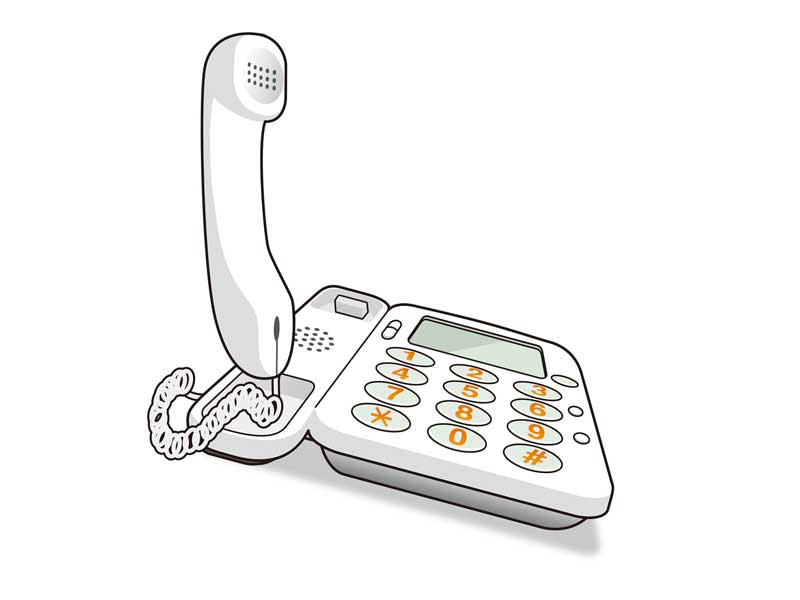
私には現在小学校5年生の娘がいますが、娘は小学校4年から鍵っ子になりました。娘の友達にも鍵っ子はいて、年齢的にも安心でしたし、しっかりしている子だったので特に不安はなかったのですが、一度留守をしている時に大人の男性から不審な電話があったらしく、娘は怖くて電話を切れず、私が帰宅した時には布団の中に入って泣いていました。
大人がいるときには電話を受けて取り次ぐことも出来たので、私も油断していたのですが、それ以来娘は電話が苦手になってしまいました。この経験から、不審者対応の具体的なルールを教え、緊急連絡先をすぐ確認できる場所に貼っておくなど、安心できる環境づくりの重要性を痛感しました。
失敗から学ぶ責任感
私の姉はシングルマザーで、うちの近くに住んでいます。そのため、甥っ子(姉の子供)はうちの子供達とも兄弟同然で生活をしているのですが、小学校1年生の頃から鍵っ子になりました。
当初は落ち着きがなく、1年間に5本鍵をなくしたり、鍵を家に忘れて家に入れずにランドセルを玄関前に放置して遊びに出かけたりと、親がいないときにやりたい放題でした。
そんな困った甥っ子ですが、小学3年生になるとようやく落ち着き、ちょうど2歳下のうちの息子が同じ小学校に入学したので、送り迎えをしてくれたり、息子よりも先に帰宅して、息子を出迎えて宿題をやらせたりするようにまでなってくれました。
落ちつきがない甥っ子ですが、失敗を繰り返したことで学び、鍵を持つ責任を理解し、一人で過ごす自信がついてきたようです。しばらくは大変でしたが、鍵っ子も子供の自立と成長には悪くないんじゃないかと思います。
【親ができる心のケアと対策】
鍵っ子生活を円滑に進め、子供の心の安定を保つために、親は次のことに配慮しましょう。
- 帰宅後にはコミュニケーションの時間をしっかり確保し、その日の出来事をじっくり聞く。
- 留守番中に不安や寂しさを感じた時の具体的な対処法(連絡方法、連絡先など)を明確にしておく。
- 「鍵をなくさない」「ルールを守る」ことに対して過度に叱責しない。信頼していることを伝え、責任感を育む。
- おやつや宿題の準備など、居心地の良さと規則正しい生活を送れるよう環境を整える。
鍵っ子のカギの保管方法3つ:紛失・盗難を防ぐために
子供に自宅の鍵をもたせるにあたって気になるのは、「鍵をなくさないかどうか」(紛失リスク)と「鍵を使って安全に自宅に入れるか」(防犯・安全性)の2点ですね。そのため、鍵の持たせ方が非常に重要になってきます。
鍵の持たせ方としては、玄関近くの安全な場所に置き鍵をするか、子供に携帯させるかの2つの方法が多いですが、最近は最新型のカギの導入も増えています。こちらでは、3つの方法のメリット・デメリットと注意点をご紹介します。
1置き鍵は防犯リスクを検討しましょう

子供がうっかり屋さんで鍵をなくしそうだからと、家の外側にこっそりと鍵を隠しておくという家庭も多いですね。しかし置き鍵は、第三者による発見や盗難のリスクがあるため、防犯上のリスクが非常に高い方法です。空き巣のターゲットになりかねません。
どうしても行う場合は、ポストや玄関近くの植木鉢の下などの定番の隠し場所は避け、家族だけが知る暗証番号でしか開かない固定できるキーボックス(南京錠式)などを使って、できるだけ安全に鍵を保管するように検討しましょう。
ただし、この場合は子供が鍵を取り出すまでに時間がかかってしまいます。鍵を取り出すときには周りをよく確認し、人目に触れないよう気を付けさせるほか、暗証番号を他の人にしゃべらないよう、子供にはよくよく指導しておきましょう。暗い場所での操作の難しさも考慮が必要です。
人目につかない場所は暗い!
息子の友達のことなのですが、A君は鍵っ子で、ある日の夕方A君を自宅に送っていきました。ところがまだ家の人が帰ってきていなくて、A君は置き鍵を使って自宅に入ろうとしました。A君の家は、エアコンの室外機の土台にワイヤーをつけて、暗証番号付きのキーケースを置いているそうなのですが、その時すでに暗くなっていて、暗証番号が全く見えなくて…。
その時、私は懐中電灯を持っていなかったので、通りかかる車のヘッドライトを利用して10分くらいかかり、何とか暗証番号を合わせました。置く場所は人目につかない方がいいですが、暗い場所は子供の帰宅時に危険が伴うこと、そして鍵開けに時間がかかるところを不審者に見られるリスクがあることも考慮すべきだと感じました。
2キーケースやキーチェーンで安全に携帯
大人のようにただキーホルダーにつけて鍵を子供に与えてしまうと、子供は自分のポケットに入れたり、カバンにしまったりして紛失してしまう可能性が高いので、好ましくありません。かといってネックストラップで首からぶら下げて肌身離さず持たせていると、遊んでいるときに遊具にひっかけてしまって危険な面もあります。
鍵の紛失を最も防げるのは、キーチェーンやコイルチェーンをつけてランドセルや服に結び付けておく方法です。ただし、この場合にでも、鍵を結びつけてあるランドセルを体から離さないように指導は必要です。上着も遊ぶときに脱いでしまうことが多いので、できるだけ脱ぐことのないズボンやスカートにキーチェーンをつけるように工夫をしてあげましょう。
もちろん、鍵を持っていることはできるだけ人目に触れない方が安全なので、ポケットに隠すよう指導をします。ズボンやスカートにポケットがない場合は、簡単に取り付けられる「取り付けポケット」を活用するといいでしょう。ベルト通しなどのキーチェーンを取り付ける部分がない時は、ポケットの内側に大き目の安全ピンを取り付けて、ピンの部分にチェーンを結びつけると安心です。
ランドセル用キーケースの活用

ベルメゾンのような、ランドセルのストラップ部分に固定できるキーケースは、鍵を取り出すときに鍵全体が人目に触れにくいよう配慮されたリール式やマジックテープ式のものを選ぶと、紛失リスクと防犯リスクの両方を軽減できます。
ランドセルに多い黒や赤、ピンクや水色などの4色から選べて目立たないので、いかにも鍵っ子のようには見えません。暗いトコロでも光る夜光反射材付きで、鍵の紛失を防いでくれる商品もありますよ。
3最新型KEY!デジタルロックの導入
近年、子供のスマートフォンやキッズ携帯の普及率が急上昇していますが、その背景には子供の安全への不安もありますよね。そこで、子供にデジタルデバイスを持たせているご家庭向けに、便利な最新型の鍵が開発され、導入する家庭が増えています。鍵の紛失という根本的な不安を解消できる可能性があります。
現時点では、小中学校では、学校へのスマホや携帯電話の持ち込みが原則禁止の地域も多いです。そのため、登下校時に利用できない場合もありますが、長期休暇中や高学年の鍵っ子のママ達のお悩みを解決できる機能満載ですので、検討してみてはいかがですか?
Qrio Smart Lock (キュリオスマートロック) Q-SL1(旧モデル)

Qrio株式会社などから発売されているスマートロックは、スマートフォンアプリや専用のリモコンキー、あるいは暗証番号で鍵のロックを解除します。設定に応じてスマホを近づけるだけでロックを解除することもできますので、低学年のお子さんでも安心して使えます。
オートロック機能もありますので、お子さんの鍵のかけ忘れへの心配も不要です。SONYの特許技術により商品化された安心セキュリティにプラスして、業者を呼ばなくても自分で取り付けできる手軽さも魅力的ですね。ただし、電池切れや機器の故障など、万が一の際の代替手段(従来の鍵やキーボックス)も必ず用意しておく必要があります。
鍵っ子は安全?起こりやすいトラブルと具体的な防犯対策
鍵の紛失だけでなく、大人の目が届きにくい鍵っ子には、さまざまな不測の事態が起こることがあります。万が一のときにはすぐにパパやママに連絡ができるよう対策を整えておきましょう。また、近所のお宅と日頃から良い関係を築き、子供が困ったら助けてもらえるように日頃から挨拶をしておくことも大切ですね。
1カギを忘れて家に入れない!待ちぼうけ対策

カバンや服を変えたときに鍵を移し替えるのを忘れてしまい、子供が帰宅しても家に帰れないといった事態は、結構な割合で起こります。暖かい時期であればよいのですが、寒い時期、特に東北、北海道などの雪深い地域だと危険が及ぶこともあるので、朝は子供が出かける前に必ず「鍵は持った?」と確認の一声をかける習慣をつけましょう。
また、万が一カギを忘れた場合は、早いうちに小学校に戻って担任の先生に相談し、学校の公衆電話を借りてパパやママの携帯電話に連絡するなど、緊急時の対処法を子供に教えておくようにしましょうね。キッズ携帯やGPS機能付きのデバイスを持たせることも有効な対策です。
2留守宅が子供のたまり場に!トラブル防止策

鍵っ子の家は、親が帰宅するまで数時間大人の目が届きません。そういった状況は子供達もよく知っていて、鍵っ子の家が子供のたまり場になってしまうことがよくあります。特に子供の大好きなゲーム機などがある場合は、勝手によその子供があがりこんでしまうリスクも高いため、子供だけで集まって危険なトラブルを引き起こすことも…。そのため、留守宅に子供だけで集まるのは好ましくありません。
<留守宅で実際に起こった危険やトラブルの例>
- 火遊び、水遊びによる事故
- 屋根に上るなど、危険な遊び
- 家の物を壊す、家具を傷つける など
中には、自分の子が友達に押しかけられているケースもありますので、「留守宅には絶対にお友達をあげない」ということを、子供にも、周りの子供にも徹底して教えておくことが重要です。帰宅後、すぐに親に連絡を入れるルールなども有効です。
帰宅してビックリ!
2年前から仕事を始めて、中学生1年の息子が鍵っ子になりました。
もう中学生なので、鍵を持たせることには特に不安はなかったのですが、先日忘れ物をしていつもよりも早く帰宅したところ、見たこともない高校生の大きな男の子が家に居てビックリ!
部活の先輩に押しかけられてしまったようなのですが、その子たちは勝手に冷蔵庫を開けてアイスを食べるなどやりたい放題でした。しかもなかなか帰ってくれなくて…。中学校を卒業した部活の先輩なのだそうですが、その子たちには「留守宅に入らないで」と説明して追い返し、学校にも「子供に指導をしてもらいたい」とお願いしました。中学生でも、留守番中のルールは徹底しなければならないと痛感しました。
3不審者や悪い大人に狙われる危険性への対応

鍵っ子を一番脅かすのは、不審者や犯罪者です。大人の目が届きにくいことで、留守宅は泥棒や悪質な訪問販売、不審者などに狙われやすいので、鍵っ子にさせる前に子供には鍵を開けるときの注意点をしっかり教え込みましょう。
自宅の中に不審者に侵入されるケースで一番多いのは、帰宅直後の鍵を開けている最中です。鍵を取り出している一瞬の間に不審者が背後にいることが多いので、鍵を取り出す時には周りに充分注意をするように子供に教え込みましょう。家に入るときに、大きな声で「ただいま!」と言わせると、大人が家に居るように見せかけることができるので、不審者から狙われにくくなりますよ。
玄関前にブロック塀などがあって周囲の目から遮られていると、不審者が潜みやすくなりますので、家の周りの安全を整備しておくことも大事ですね。防犯ブザーやGPS機能付き端末の携帯も、緊急時の対策として有効です。
鍵っ子は子供の成長のワンステップ!親のサポートが不可欠
昔は鍵っ子というと、「子供に鍵を持たせてまで、母親が働かなくても…」なんて否定的な目で見られることもありましたが、子供にとって鍵を持つことは、「ちょっと大人になった」とか、「パパやママに信頼されている」というちょっと誇らしい気分にさせてくれる自立へのワンステップです。
人は誰でもいずれ鍵をもち、自分の城を築いていくもの。鍵っ子になることはそのための第一歩です。将来独り立ちすることに不安を持たせることがないよう、鍵を子供に預ける場合には事前準備とルール作りをしっかり行い、子供が安全に、そして安心感をもって留守宅で過ごせるように大人が配慮とサポートをしてあげましょうね。心のケアを忘れずに、子供の成長を支えていきましょう。



