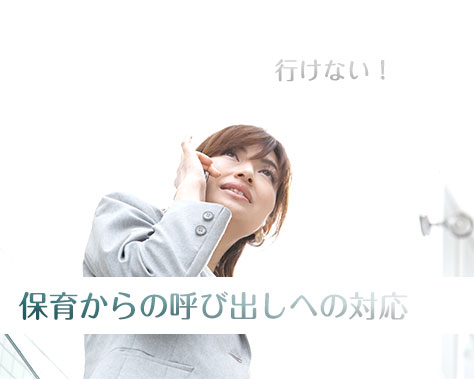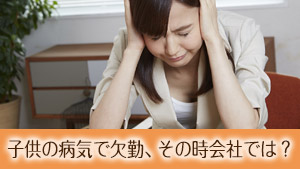保育園からの急な呼び出し!ビクビクしないための備えと職場対応

保育園に子どもを預けて働くママにとって、「ドキッ!」とするのが突然かかってくる保育園からの呼び出し電話。
子供も心配だけど、中途半端になってしまう仕事も悩みのタネだし、職場の同僚や上司の冷たい目やクビも気になるし。頭が真っ白になったり、やり場のない憤りを感じてイライラしたり。
そこで今回は、保育園からの急な呼び出しの実情についてご紹介しながら、呼び出しがあっても慌てずに対処するコツについて、保育園歴15年以上の先輩ママの目線で解説していきます。今現在保育園の呼び出しに怯えている働くママだけでなく、これから保育園を利用して復職を考えるママも、急な呼び出しがあることを前提に、子育ての体制を整えておきましょう。
保育園からの呼び出しの理由
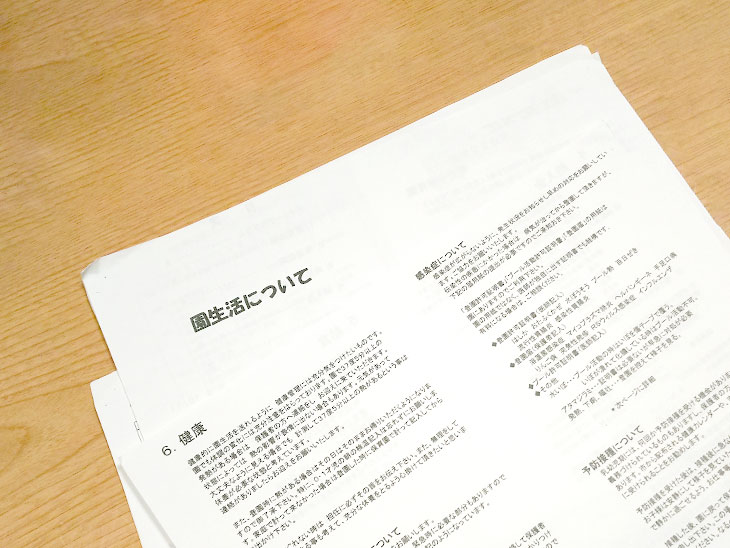
保育園からの呼び出しとは、何らかの事情があって保育を中断するため、予定の時間よりも早くお迎えに来ることを求められることですので、一般的には次の理由があげられます。
- 急に熱が出た
- 繰り返して下痢便がでた
- 繰り返して嘔吐した
- 皮膚に発疹がある
- 災害で避難指示がでた
- 保育園の近所で重大事件が起こった
いずれも、保育園側の事情ではありません。預かっている子どもの健康と安全を守るために、スムーズに家庭に子どもを引き渡して必要な処置をとらせることが、呼び出しの目的なのです。
入園の際に園からも説明がありますが、保育園では「38.0℃以上の体温がある場合」等、子どもを受け入れることができない場合の基準は、各園が厚生労働省のガイドラインを元に定めています。
インフルエンザなどの感染症が流行している時期には、基準に達する程ではないものの気になる症状があることを理由に呼び出しがきて、自宅に戻って休養するよう促されることもあるのですが、まずは保育園から呼び出される基準をしっかりと承知しておきましょう。
保育園からの呼び出しの捉え方

保育園を利用する理由は家庭によってさまざまですが、一番多いのは、パパだけでなくママも仕事を持ち、忙しく働いて家計を支えている家庭。
ということは、急な呼び出しは働くママや家族だけでなく、職場や仕事関係の相手にまで大きな影響を与えてしまうこと。仕事でさまざまな人と繋がっている以上、仕事を放りだすことはできません。
そのため「面倒を見られないから、子どもを保育園に預けているのに!」なんて保育士さんに反発心を持ってしまいがちなのですが、呼び出しは保育士さんや保育園のせいではありません。
呼び出しはやむを得ず行う保育士の仕事!
保育士さんもあなたと同じように仕事を行っているだけです。電話をかけてきた保育士さんが、国のガイドラインや保育園の規定を決めたわけではありません。
体調が急変するのは子どものせいでも、家庭で面倒を見ているパパやママのせいでもありません。やり場のない怒りでイライラしてしまいがちですが、保育園からの呼び出しで仕事の中断を迫られたら、とりあえず大きく深呼吸をして冷静になり、前向きに受け入れましょう。
保育園の呼び出し前に行う5つの対応

子どもは環境の変化で体調を崩しやすく、保育時間開始直後や給食の後、昼寝の後には呼び出しがくる可能性が高い危険な時間帯。いきなり職場に電話が来てもスムーズに対処していけるよう、次の5つの対応で体制を整えておきましょう。
1夫婦でルールを決める
保育園からの呼び出しは、「ママにとってもお休み」と割り切って考えられると良いのですが、ママばかりが休みを取っていては育児の負担が大きくなってしまいます。「今回はママ、次はパパ」というように、呼び出しの対処は夫婦でできるだけ平等になるよう、話し合っておきましょう。
呼び出しは夫婦平等に対応するという意識を持つことで、ママのイライラは和らぎます。どうしても仕事を休んで呼び出しの対処ができないパパの場合には、そのぶん家事などの負担を増やす、週末などに子育てを一気に引き受けるなどで、ママへの負担を減らしてあげてください。
2子どもの体調管理はしっかりと

年齢が小さな子供ほど急な体調変化を起こしやすいので、未満児のママは呼び出しが多いことを自覚しておきましょう。もちろん体調管理は、しっかりしておく必要があります。
毎日気をつけよう!子供の体調管理
- 子どもの夜更かしを大目に見るのはもってのほか!
- たっぷりと休息させる
- 栄養のある食事を摂らせる
未満児の場合は保育園側の体調チェックも厳しいので、保育園出発前は熱がないか、食欲はあるか、顔色が悪くないか、下痢をしていないかなどをチェックしてから通園させると安心です。
いちいち体温計を取り出さなくても、「大体これぐらいが平熱」と手のひらをあてて覚えておけば十分ですし、日頃から子供のおでこや手を触って体調を確認するのは、親子の良いスキンシップになって子供の心を落ち着かせる効果も期待できます。
3保育士さんとの良好な関係を築いておく

保育園が呼び出しをする発熱の基準は園によってさまざまで、38.5℃まで大丈夫な園もあれば、37.0℃で呼び出しをする園もあります。
ただし子どもの平熱には個人差があり、体温の変動も頻繁なので、子育て経験のある熟練保育士さんの中には、すぐには呼び出しの連絡をせず、様子を見てくれるなどのフレキシブルな対応をしてくれる保育士さんもいます。
ママと保育士さんで良い信頼関係が結ぶことができ、ちょっと体調変化が気になるときでもうまくコミュニケーションができていれば、呼び出しを極力少なくできるチャンスはあります。呼び出しのときに嫌な対応をしない、連絡ノートでも密に日頃の子どもの様子を伝えあうことを心掛けて、ママの方からもう一歩踏み込んで保育士さんを味方につけましょう。
4早めの受診・治療を心掛ける

発熱の呼び出しで必死に段取りをして子どもを迎えに行ったのに、自宅に帰ったらケロッと熱が治まってしまった、下痢をしつつも元気に遊んでいる、なんてこともよくあること。
「何のための呼び出し!?」と思ってしまいがちですが、ママと早めに自宅に戻れたことに興奮し、子どもが無理をしているのかも。お仕事を休んで時間ができたのであれば、早めに病院を受診しておきましょう。
早めに治療を受けてしっかりと休ませてしまった方が、子どももママも安心ですし、休みを長引かせないで済みます。
いちいち保険証を取りに自宅に戻るのでは受診に時間がかかるので、働くママは子どもの保険証と母子手帳を常に身に着けておくべし。
病院での待ち時間の短縮や、病院での二次感染を防ぐためにも、働くママは電話で受診予約ができる小児科を主治医にしておくことをおすすめします。
5行けない時のサポート体制を整える

どんなに子育てを頑張ろうと思っても、若いパパやママだけでは限界があります。そのため保育園からの呼び出しに行けなくて、無視してしまうママもいますが、さすがにそれはルール違反。
働くママの場合は、母親業に加えて社会人としての義務も果たすわけですから、1人の体に役割は2倍。無理をせずに済むように実家の両親や義両親とも日頃から良い関係を築いて、協力を求めましょう。
ファミサポ(自治体のファミリーサポート)や病児保育送迎サービス、病児看護OKの民間のベビーシッターなども、呼び出しのときの心強い味方になってくれます。職場の子育て支援で、ベビーシッターの費用の一部を負担してくれる企業もありますので、どんなサポートが受けられるのかを調べ、サポート体制を整えておきましょう。
パパが忙しすぎる場合はシッターを利用!
ママ一人にお迎えの負担がかかってしまう場合は、パパのお小遣いからシッター代を出してもらい、ママだけに負担がかからない体勢を作りましょう。ママが目くじらを立てて夫婦関係が悪化するより、その方がパパにとっても家族にとってもずっと建設的な解決策となります。
賢いママの仕事や職場への6つの対応
「子どもを育てる母親であれば、何があっても子どもを優先させるもの」という考え方もありますが、仕事を持っているママの場合、パパ同様に社会的に果たさなければならない「責任」というものがあります。
そのため子育てに理解を示す優れた会社が増え始めている一方で、「子持ちの女性には、仕事は任せられない」というレッテルを貼られ、いつまでたっても良い仕事を得にくいという会社もあります。
保育園に子どもを預け始めた当初は、急な呼び出しと仕事や職場との板挟みで切ない思いをすることも多いのですが、慣れてくれば次第に上手くバランスがとれるようになります。恐怖の呼び出しコールを乗り越えた先輩ママ達の次の対処法を参考に、仕事も子育ても無理なく両立できる方法を探っていきましょう。
1仕事は常に前倒しを心掛ける
小さな子供が急に体調を崩すのは、仕方がないこと。「もしかしたら、呼び出しがくるかもしれない」と頭に置いておいて、段取りをつけて仕事を前倒しにこなしましょう。
働くママの場合は「明日があるから」と考えていると、いざという時に慌ててしまいます。急に早退しても仕事に穴が開かないように、自分の責任範囲の仕事はできるだけ早めに終わらせることが大切です。
2仕事の引継ぎは確実に

働くママが呼び出されたことで職場が一番困るのは、急なお休みで人員が減ることではありません。担当者がいないことでトラブルが起きることや、仕事の進みが停滞してしまうこと。
これは呼び出しが来たときに同僚や部下に自分が今日やることや、抱えている案件をしっかり引継ぎをすれば回避できます。自分の仕事はいつもコンパクトにまとめておいて、速やかに周りに引き継げるようにしておきましょう。
3上司への報・連・相はこまめに

目途が立った段階で、早めに今後の予定を上司に伝えておきましょう。
呼び出しを受けて早退したあと、子どもの様子がどうなのか、休みが長引きそうなのを知っておかないと、上司は職場の段取りができません。
職場の管理をしている上司にとって、部下が早退すること、子ども看護のために長期に休暇をとることは把握しておかなくてはいけないことです。
4嫌な気持ちを態度に出さない
仕方がないこととわかっていても、ママだって保育園から呼び出しがくれば困りますし、イラっとくるもの。それは周りの同僚も同じです。子供の病気で仕事を休んで周りから嫌みを言われても、仕方がないことだと考えて、スルーする強さを持ってください。
明るい態度自分自身が職場にとって欠かせない人材だとわかってもらえれば、自然と周りの風向きが変わってきますので、挨拶や気配りで他の人から一目置かれる自分になりましょう。
5プロに徹する
働くママにとっては、仕事中でも母親。だからこそ仕事中に保育園から呼び出しが来て、対応を求められるわけですが、どんな些細な案件でも仕事を任せられている以上は責任を持たなくてはいけません。「誰かがやってくれるだろう」と思うのではなく、任された仕事は自分がするというプロ意識を持ちましょう。
職場で子どもや家庭に関する話をしたり、愚痴を言ったりというママ・アピールはほどほどに。日頃から、仕事に対する意欲を示しておくことが大事です。
6もう一言をプラスする

「いつも、ありがとうございます!」と感謝の言葉をしっかり伝えて、理解と協力をアピールしておきましょう。
呼び出しで早退するとき、ストレートに「すみません」だけで済ましてしまうママも多いのですが、ここではもう一言が必要です。
「忙しい時に」や「何度も」という一言を前に加えたり、周りに対する配慮を言葉で挟んでおいたりすると、相手の気持ちをやわらげることができます。子供の発熱で仕事を休んだ後も、何食わぬ顔で仕事に戻るとやはり角が立ってしまいます。
保育園の呼び出しは上手にやり過ごそう
そもそも赤ちゃんを大人に育てることは、女性にとって大変な我慢と苦労を伴う大仕事。さらに仕事を持っていれば、我慢も苦労も2倍であることは当然のこと。
保育園からの呼び出しも、そんな子育ての苦労のその一つ。頭ではそうわかっていても、実際に呼び出しコールを受けるとやりきれなくなってしまうものですが、苦労が多いぶん振り返った時の喜びが大きいのも子育ての醍醐味です。
子育てのつらさや大変さは、長い人生の中のほんの一瞬。子どもはママにとって人生の一部ではありますが、人生の全てではありません。子どもがいつか成長して自分の人生を歩み始めたときに、ママ自身が独り立ちをするためにも、自分を活かせる仕事をもっておくことはステキなこと。どうぞ「苦労はいつか報われる」と前向きに考えて、子育ても仕事もあきらめずに、ねばっていきましょう。