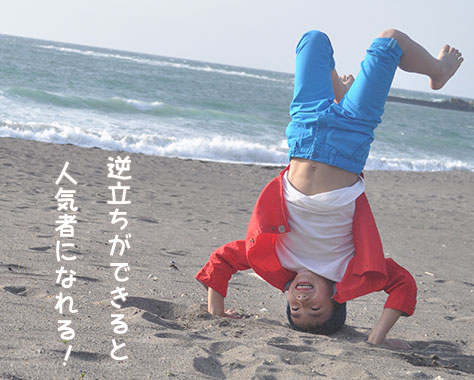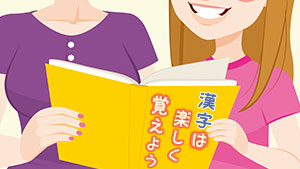逆立ち(倒立)のやり方を覚えよう!保護者でも教えられる練習方法
お子さんが逆立ちをできるようになりたがっているけど、教え方がわからない…とお悩みの保護者の方へ。逆立ちは難易度が高いように思えますが、基礎をコツコツ練習することで誰でもできるようになりますし、できると達成感や自信につながります。ここでは、保護者の方にも簡単に逆立ち(倒立)のやり方を教えられる練習方法をご紹介します。
※本記事では、一般的に「逆立ち」と呼ばれることの多い、両手で体を支える技を、器械運動の専門用語に合わせて「倒立」として解説します。
運動は、技術ができるようになることだけでなく、できるようになるまでのプロセスや達成感を味わうことも大きな目的です。お子さんと一緒に達成感を味わい、自信に満ちたキラキラした姿を見られるように、安全に気を付けて練習してみてくださいね。
倒立ができない理由
まわりには倒立ができる子が多いのに、自分にはなんでできないんだろう…とお子さんが悩んでいたら、なんと声をかけてあげますか。倒立ができない主な原因を理解することで、克服すべきポイントが見えてきます。倒立ができない理由を3つご紹介します。
恐怖心がある

身体が逆さまになると、体のバランスが取りにくくなり、「転んでしまうかもしれない」という恐怖心が生まれます。恐怖心が生まれると、怖くて腕に力が入らず、ひじをまっすぐに突っ張ることができません。また、怖さから腰が曲がったままになり、足を高く上げられないことにもつながります。倒立を成功させるには、まず逆さまの状態に慣れることが大切です。
逆さの状態になること自体が怖いお子さんの場合、まずは布団やクッション、安全マットなどをまわりに敷いて、転んでも怖くないということをわかってもらいましょう。そうすることで転んだときの身の守り方も身につき、マットがない場所で転んだときでも怪我をしにくくなります。
身体を支える腕の力がない
恐怖心がなかったとしても、自分の体の重さを支えるだけの腕の力がなければ、足を蹴っても体が上にあがりません。体の重さで腕がぐにゃっと曲がってしまい、倒立が成立しないのです。腕の力が足りないことをお子さんは意識していないので、何度やってもできないと嫌になってしまうかもしれません。これも「倒立ができない!」と思ってしまう原因の一つです。
手と足の位置が遠い(体重移動ができない)

倒立ができないお子さんが足を上げようとしているとき、やっている本人が思っている以上に足があがっていないことがあります。それは、床についた手と蹴り上げる足の始点が遠く離れているからです。手と足が遠く離れていると、足を上げようとしても体重を手に移動することが難しくなります。
倒立ができるお友達のフォームを見てみると、自分との違いが分かるはずです。練習するときは鏡を見たりビデオに撮ったりして、手と足の位置や体重移動を確認してみましょう。
倒立ができるようになる前の準備
いきなり倒立をやろうとしても、難しくて挫折してしまうこともあります。遠回りのように思うかもしれませんが、まずは簡単な準備運動から順番にできるようになりましょう。ここでは、倒立の練習をする前にやっておきたいことを2つご紹介します。
倒立をしているイメージをする

普段は足を地面につけて立っていますが、この立った状態の感覚を理解することが、倒立をするイメージにつながります。
普通に立ったまま上に手をまっすぐ伸ばしてみます。これを逆さにした状態が倒立です。このとき自分の体がどのようになっているのか考えてみましょう。意外と体幹に力が入っていないこと、背中は少し反っていること、などに気付くはずです。この感覚を掴んでから実践に移ります。
逆さまの状態に慣れる
倒立しているイメージができたら、逆さまの状態に慣れましょう。倒立の動作を訓練する前に、倒立したあとの姿勢に先に慣れておくということです。
腕立て伏せの体勢になり、台などを使って足の高さを徐々に高くしていきます。これによって腕で体を支えるイメージを掴むことができます。その後、壁倒立や補助倒立という段階を踏んで倒立に近付けていきましょう。
最初は3点倒立を練習する
倒立ができないと悩むお子さんには、いきなり倒立をやらせるのではなく、まずは3点倒立をやってみましょう。腕だけで体全体を支えなければならない倒立に対して、3点倒立は支点が多いので難易度が低く、バランス感覚を身につけることができます。
3点倒立とは

3点倒立とは、名前の通り3点(右手・左手・頭)で体を支える倒立のことです。もともとヨガのポーズの一つですが、器械体操や体育の授業で教わることがあります。学校で習ったときのためにも、3点倒立を練習しておくのは予習にもなり良いですね。
3点倒立のやり方
倒立に向けて、まずは3点倒立のやり方をマスターしましょう。3点倒立ができるようになると、倒立までぐんと近づきますよ。
安全な場所で頭と両手をつく
四つんばいの状態で頭を床につけます。床につける部分はつむじ(頭頂部)とおでこの間のあたりです。頭頂部を床につけてしまうと首に負担がかかるため、おでこから少し上がった部分を目安にしましょう。このとき、頭を守るために安全マットや厚手のタオルを敷きましょう。フローリングよりも畳やマットの上で練習した方が、衝撃が吸収されるので安全です。
コツは頭と両手で正三角形をつくること
頭をつけた位置よりも手前(顔側)に右手と左手をつき、頭と両手の位置関係が正三角形になるように気を付けます。手の指を少し外側に向けると倒れにくくなりますよ。
足を上げる練習をする

体重を3点にかけながら足を床から離し、伸ばしていきます。最初は難しいので、3点を床につけたら、軽く跳ぶように足で床を蹴ってみましょう。最初はほんの数センチ、床から足が離れるだけで大丈夫です。
そして、3点で体を支えられる時間を少しずつ長くしていきます。3点をつけた状態でつま先立ち、ひじに膝を乗せる、膝を曲げたままの倒立…のように、徐々に難易度をあげていきましょう。
身体をまっすぐにのばす
足を上げることができるようになったら、最後に体全体をまっすぐに伸ばします。ここまでで、逆さまの状態でのバランス感覚はかなり身についているはずなので、もう少し練習すると、きれいな3点倒立になるはずです。
保護者の方は腰まわりを中心に支える
保護者の方は子どもの足だけを持つのではなく、腰まわり(体幹)を中心に体全体を支えてあげるようにしてください。慣れてくると、足を支えるだけでも大丈夫になってきます。
次は壁を使った練習
3点倒立ができるようになったら、次は壁を使った練習です。倒立のときに重要な「一直線の姿勢」を意識して練習してみてくださいね。
壁にお腹を向けて登る練習
壁にお腹を向けて倒立の練習をします。まずは両腕を床につき、壁につま先だけつけて手と手の間に目線を置きます。壁に足をかけた状態で、腕立て伏せのポーズをするイメージです。
足で壁を押すように下から上へ上る
膝を伸ばしたまま、足で壁を押すように上にのぼっていきます。最初は低い位置でもいいので、膝を伸ばしてのぼっていきましょう。壁を登ることで、足から体幹、腕へと体重を移動させ、腕で体を支える感覚を養います。
両腕を徐々に壁に近づけていく
足を高い位置に持っていきながら、両腕は徐々に壁に近付けていきます。腕立て伏せのような体勢から、倒立に近い体勢になります。
保護者の方は肩を支える
手、肩、腰、足が一直線にならないと倒立はできません。そのためには、肩(体幹)に体重を乗せることが大切なので、保護者の方は子どもの肩や腰を支えてあげるようにしてください。
続いて壁倒立を練習する
壁を上ることができるようになったら、次は壁倒立の練習です。難易度が少し上がりますが頑張って練習しましょう。壁から離れて倒立している気持ちで、一直線に体を伸ばしていきますよ。
壁の近くで両腕を床につく

壁ギリギリの近さに両腕をつくことで、体が反りにくくなります。そして、このときひじが曲がらないことが重要です。どのようにしたら腕にきちんと体重を乗せることができるのかがわかれば、ひじは曲がらないはずです。床に膝をついたままの四つんばいになり、右腕と左腕に交互に体重を乗せる練習をしてみましょう。体重を乗せようとすると、ひじが伸びていることに気付くと思います。
目線は手と手の間におく
壁倒立したときに、目線が壁にあるのはよくありません。床の方、体を支えている両手の間に目線を置くようにしましょう。あごを引いてしまうと、自分の体がどのようになっているのかわからなくなってしまうことがあります。これが恐怖心にもつながるので、目線はしっかり手と手の間に置くようにしましょう。
上に向かって足を蹴り上げる
最初から壁の方に向かって足を蹴り上げるのではなく、まずは上に向かって足を蹴り上げる練習をします。片足ずつ床を蹴り、足を高く上げることを意識します。
保護者の方はお尻と腰を支える

保護者の方は子どもの横に立って、お尻と腰を支えてあげてください。足を高く伸ばすことよりも、まずは腰までをしっかり上げて垂直にすることが先決です。足が伸びていても腰が曲がっていると、倒立の状態を保つことができません。手、肩、腰を一直線にすることで、足もしっかり伸びてきます。
次は壁に向かって足を蹴り上げる
まず片方の足を高く振り上げ、もう片方の足で床を蹴ります。あとから蹴り上げるほうの足は、伸ばした状態で蹴り上げるようにしましょう。最初に上げたほうの足が壁についてから、もう片方の足を蹴り上げて足を揃えます。
保護者の方は膝を支える(安全確保)
上がってくる足を支えるときは、足首ではなく膝や太ももを持つようにします。足首を掴むと、誤って子どもの顔を蹴ってしまう可能性があるので要注意です。手で掴むのではなく、腕全体で抱きかかえるように支えることがポイントです。
そして倒立(壁なし)の練習!
壁倒立ができるようになったら、いよいよ壁のない場所での倒立の練習です。壁がないからといって怖がらないように、保護者の方はしっかり見守り、支える準備をしてあげてくださいね。
少しずつ壁から手を離す
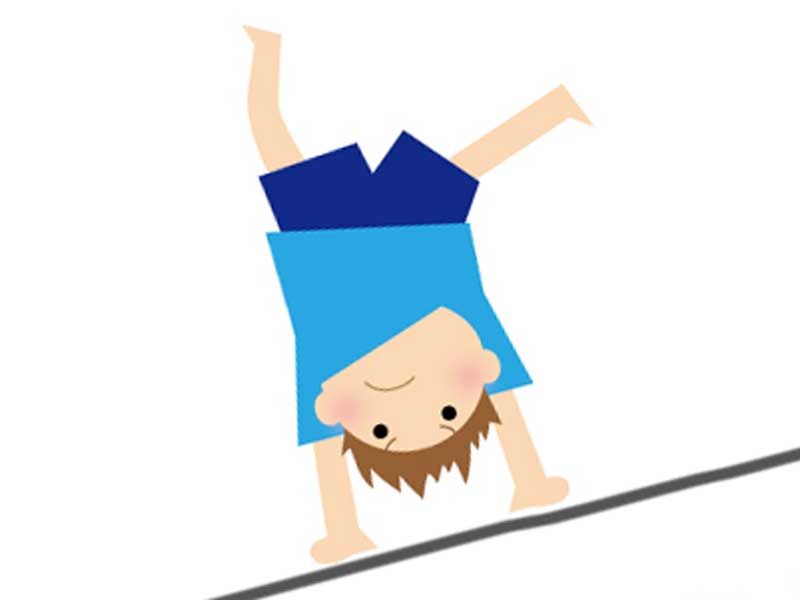
壁倒立は、あくまでも壁ありきの倒立なので、壁から離れても倒立の状態を保てるのとは別段階の練習が必要です。ここからは、壁倒立の状態から少しずつ足を壁から離す練習をします。
壁倒立の時に壁のギリギリに手をついて練習していましたが、手をつける位置を壁から徐々に離していきます。最初は壁に足をつけますが、そこから壁を蹴り、足を離すことで一瞬倒立ができる瞬間があります。この感覚を体で覚え、数秒間静止できるようになり、最後はキープできるようになります。
保護者の方は膝を中心に足を支える
壁倒立のときと同じように、膝を中心に足首側ではなく太もも側を支えます。足首を持つと蹴られる可能性があるという同じ理由からです。このときも、腕全体で抱きかかえるように支えてあげてくださいね。
腕の力をつけるには?
練習方法やコツはわかってきましたが、そもそも腕の力が弱くて体を支えきれないという場合は、腕の力をつけることが必要です。どういう訓練をしたら腕の力がつくのでしょうか。ここでは2つご紹介します。
鉄棒にぶら下がる
時間がかかってしまうかもしれませんが、足の届かない高さの鉄棒にぶら下がって数秒間耐えてみたり、懸垂(斜め懸垂含む)をやってみることで、自分の体重を支えられるようになります。
手押し車をする
子どもが腕立て伏せの体勢になり、保護者の方が子どもの足を持ちます。そのまま腕立て伏せの体勢の子どもは、腕の力で前に進みます。これが手押し車です。一見ただの遊びのようですが、楽しみながらしっかり腕の力をつけることができますよ。
倒立を練習する時の注意点
子どもは早く倒立ができるようになりたいと思うかもしれませんが、練習するときには注意しなければならないことがあります。倒立は少し間違うと危険を伴うので、これを守って安全に練習しましょう。
子ども一人だけで練習しない

保護者の方が忙しい場合でも、時間がないからといって子ども一人だけで倒立の練習をさせてはいけません。転んでしまって打ち所が悪いと大変危険です。特に首や頭を打つ可能性があるため、必ず目の行き届く場所で、補助ができる状態で練習をさせるようにしましょう。
安全マットや布団などを敷く
倒立の練習をしていて、首から転んでしまったり、かたい床に頭を打つと、怪我をしてしまいます。予防のためには布団やマット、座布団などを敷いて安全に練習するようにしましょう。可能であれば体育用の安全マットを使用することが最も安全です。
倒立ができるまで何度も練習しよう!
倒立ができるようになる練習法やコツをご紹介してきました。体力や筋力、恐怖心の程度は一人一人違います。クラスの子がみんなできるのに、自分の子どもだけできないからといって焦らず、ゆっくり練習に付き合ってあげてください。お子さんなりのペースで倒立ができるようになるはずです。何度も楽しく練習してみてくださいね。