授乳中に泣く原因と対処法!先輩ママが教える「授乳拒否」の乗り越え方
赤ちゃんにおっぱいをあげているママにとって、ゴクゴクと元気に飲んでくれる姿は、至福のひとときですよね。しかし、実は、赤ちゃんが授乳中に泣いてしまったり、授乳を拒否したりして悩んでいるママがたくさんいらっしゃるんです。
そこで、先輩ママ15人から体験談を集めました。赤ちゃんが「授乳中 泣く 理由」や、ママたちがどんな工夫で授乳拒否を乗り越えたのか、きっと、参考になる知恵が見つかりますよ。
赤ちゃんが授乳中に泣いてしまう主な原因は、以下の4つのパターンに分類できることが多いです。
- 生理的な不快感: おむつが濡れている、暑い・寒い、姿勢が合わない、眠い。
- 母乳の勢い・量: 母乳の出が良すぎる(噴射が強い)、または量が足りない・出が悪い。
- 飲みにくさ・痛み: 鼻が詰まっている、口の中に痛みがある(口内炎など)、中耳炎などの病気。
- 赤ちゃんの気分・環境: 遊びたい、集中できない(周りが気になる)、授乳以外の理由で泣いている。
「あれ?泣き止んだ!」赤ちゃんが授乳中に泣いていた原因と工夫
眠気によるぐずり泣きには、一度気分転換を
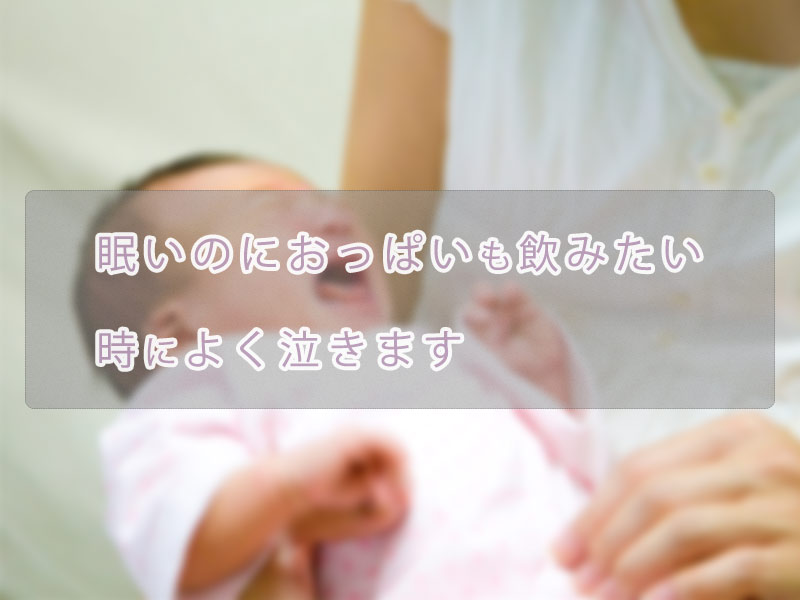
授乳中に赤ちゃんがよく泣くと感じたのは、生後6、7ヶ月くらいです。現在も、眠たいけどおっぱいも飲みたい時によく泣きます。
授乳中に泣いてしまったら、一旦授乳をやめて、縦抱きにしてトントンします。それでも泣き止まなかったら、違う部屋に行ったり外に行ったりして、赤ちゃんの興味をそらすようにします。これは「眠いのに飲みたい」というジレンマからくるぐずり泣きへの有効な対処法です。
授乳は、泣き止んでから再開しますが、基本的にお腹が空いたら必ず飲むと思うので、無理矢理おっぱいを飲ませることはしません。
授乳中に泣いて困ったのは、夜、添い乳している時です。こっちもすごく眠たいのに、一度起きてしまって、抱っこなどして、あやしてからおっぱいをあげないといけないのが辛いです。
なるべく空腹になるまであげないようにして、お腹が空いたらゴクゴクと一気に飲めるように工夫しています。チビチビ飲みは泣きやすくなる傾向があります。
抱っこで反り返る授乳拒否には、添い乳や四つん這いで対応
娘が3ヶ月頃から6ヶ月頃まで、授乳中に、のけ反って泣くようになりました。なぜ泣くのか原因不明だったのですが、抱っこでの授乳のときは、のけ反って乳首から離れて泣いてしまっていました。
泣いてしまった時は、これ以上のけ反ってしまうのを防ぐため、寝っころがらせて、四つん這いか添い乳をしていました。もともと体重増加が緩やかな子だったので、寝っころがらせて飲ませる事を思いつくまでは、痩せてしまうんじゃないかと心配でたまりませんでした。
常にお腹が空いていたためか、寝ぐずりがひどかったです。おっぱいも張ってしまって、白斑ができたりと大変でした。泣き出すとなだめるのも大変なので、抱っこでの授乳はお休みして、初めから寝っころがらせて与える事を3ヶ月ほど続けました。
お座りが少しの間ならできる頃に、たまたま抱っこしてたら、服の上からおっぱいを吸いたそうにしていたので、くわえさせてみたら、泣かずに飲めるようになっていました。授乳中の反り返りは、抱き方を変えることで改善することがあります。
強めのトントンで安心感を!ママの笑顔も大切に

生後3か月くらいの時は、理由もわからずよく泣いていました。それは、授乳中であっても頻繁に泣いていました。
再チャレンジでおっぱいをあげようとしても嫌がるので、そんな時は抱っこをして強めにトントンするようにしていました。強めのトントンは、胎内にいる時のお母さんの心臓音を思い出すそうで、よく使っていました。これは赤ちゃんの原始反射を刺激し、安心感を与える方法の一つです。
うちの娘の場合、授乳中泣いていたのは、眠い時が多かったように思います。でも、眠れなくてイライラして、授乳中でも泣いていたようです。
しばらくトントンしていると落ち着いてくるので、それから再度おっぱいをあげるようにしていました。私の場合、おっぱいがよく出たので、娘が授乳を嫌がって泣いている間も母乳が出てしまい、服が濡れてしまったのでその点は困りました。授乳の際は、極力娘と視線を合わせて、笑顔で授乳するように心がけていました。
不快感のサインを見逃さない!授乳前のオムツチェック
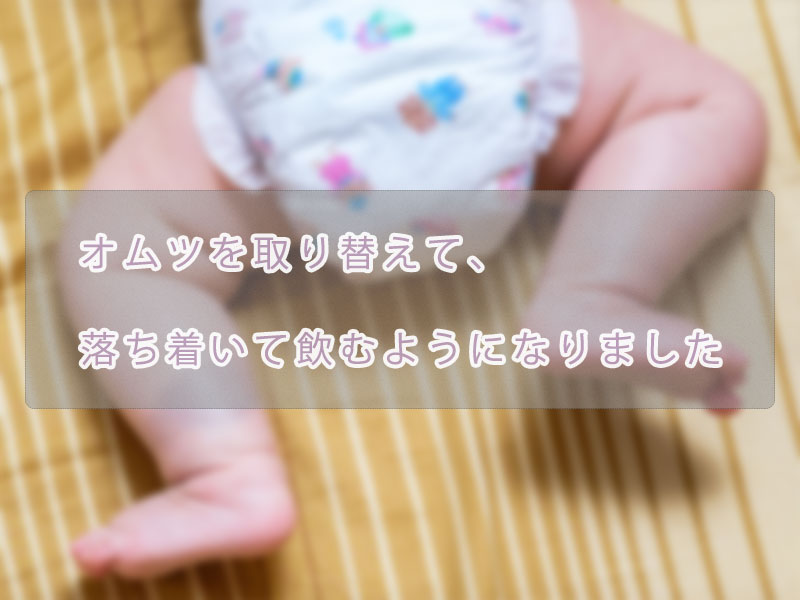
授乳中に赤ちゃんが良く泣くと感じたのは、赤ちゃんが3ヶ月の頃でした。どうやらオムツが濡れていたために泣いているようでした。
授乳中に赤ちゃんが泣いてしまった時は、一度授乳を止めて、オムツを取り替える等して、落ち着いてからまた授乳を再開していました。
授乳中に泣いてしまうと、もう飲むのを止めてしまったり、泣いてミルクを吐き出したりしてしまって大変でした。
授乳中に赤ちゃんが泣いてしまわないように、授乳の前には必ずオムツを取り替えて、落ち着いてから授乳をするようにしていました。生理的な不快感を取り除くことは、スムーズな授乳のために非常に重要です。
周りの音等にも敏感だったので、なるべく静かな環境で授乳できるように、工夫して過ごしていました。赤ちゃんが泣いて授乳を嫌がっていた時は、少し時間が経ってから飲ませるようにしていました。
母乳不足の疑いには、ミルクも併用し安心感を
生後3ヶ月の時、夜間の授乳で泣きながら暴れていました。オムツも交換していましたし、おっぱいを離せば離したで泣くので、最初はなんだろうと悩んでいましたが、色々試した結果、母乳が足りていないことで泣いているのがわかりました。
なので、できるだけ、母乳を飲ませてからミルクを与えることにしました。おっぱいをくわえるとすぐに泣き出すので、背中を規則的に優しく叩いて、落ち着いてくれるように祈りながら、おっぱいを飲ませていましたね。
効果があったのか、これで少しの間おとなしく飲んでくれました。授乳中に泣いてしまうと、暴れて反り返るので、抱えるのが大変だった記憶があります。とにかく子供が怪我をしないように気を遣いました。
授乳中、なるべく泣かないように気を付けていたことは、にこにこ話かけながらおっぱいをあげること。お母さんの気持ちは赤ちゃんに伝わると思って、動揺しないように気をつけました。ママがリラックスすることも、赤ちゃんが安心して飲むための大切な要素です。
左右差への対応:飲みたいだけ飲ませたら解決
右側のおっぱいの張りが悪く、あまりおっぱいが出なかったせいか、生後6か月ぐらいからよく泣きました。
最初のころは、両方同じように出たのですが、少しすると、右側は、おっぱいがたくさんできてあふれるようになりました。でも、左側はどんどんたまっていきました。左右で母乳の出が異なることはよくあります。
なので、おっぱいマッサージをしたり、少し出してから飲ませたり、抱っこの仕方を変えたり、右と左と交互にあげたりと工夫をしました。
そうしたら、逆に、右側が出なくなってしまったのです。右側は、口に含んだだけで嫌がったので、右を少し飲ませたら、左をたくさん飲ませるようにしました。
赤ちゃんが飲みたいだけ飲ませるようにしたら、泣くことはなくなりました。赤ちゃん自身が、飲みやすい方のおっぱいを選んでいると考えられます。
他の理由での泣きを授乳と勘違いしない配慮
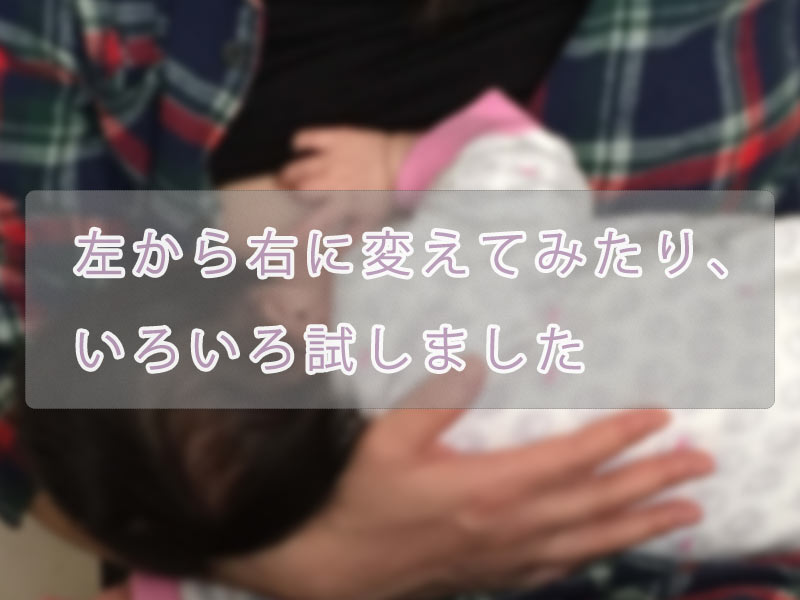
授乳中に赤ちゃんがよく泣くと感じたのは、生後2ヶ月くらいのときです。授乳中に泣いていたのは、今思うと、飲みたくないのに飲ませていたから、ということが多かったような気がします。
うちの子供は、よく泣く赤ちゃんだった為、泣いたらすぐおっぱい、ということが多かったのですが、きっと、他の理由で泣いていたのに、無理矢理おっぱいを飲まされて、いやだったのかもしれないなと思います。
授乳中に赤ちゃんが泣いてしまった時は、とりあえず左から右に変えてみたり、抱っこの仕方を変えてみたり、少しゆらしながら飲ませてみたりといろいろ試しました。
授乳中に泣いてしまって一番困ったのは、やはり、自分がテンパってしまうことです。また、特に自宅ではなく、実家や義実家での授乳中に泣き止まないと、だれか(夫ではなく義母とか実父とか)が覗きにくるんじゃないかと気が気ではありませんでした。
授乳の際、赤ちゃんが泣かないようにしていた工夫は、やはり、抱っこの仕方を変えることです。たまに抱き方を変えると、飲んでくれることがありました。授乳のたびに抱き方を変えることも、授乳拒否の対策の一つです。
機嫌を損ねない工夫!こだわりへの対応と飲まない時の見切り
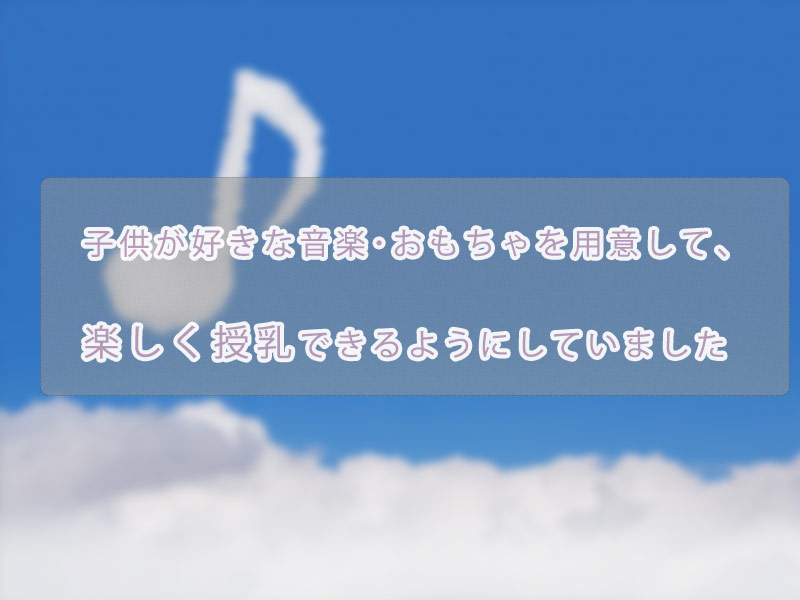
生後6ヶ月の頃、授乳中に突然泣き出しました。泣き始めて間もない頃は、2分くらいは機嫌よく飲んでいて急に泣き出し、そのあとは飲みませんでした。
そのうちだんだんひどくなり、授乳の準備を始めると泣き出し、拒否されることが続きました。この頃は、気分じゃない時や抱っこの仕方、授乳場所、おっぱいかミルクかなど、子供なりのこだわりがあり、それが少しでも違うと泣いていました。
泣き始めたらとりあえず、抱っこや場所などを変え、飲ませていました。あまりひどく泣くときは授乳は止め、機嫌が良さそうな時に再度飲ませるようにしていました。無理強いをしないことが、授乳拒否を防ぐポイントです。
一番困ったのは、一日近く飲まなかったことです。無理に飲ませると、泣きながら吐き出したり、バタバタ暴れて困りました。
授乳時の工夫は、無理やり飲まさないようにしていました。子供が好きな音楽やおもちゃを用意して、なるべく機嫌をそこねないようにしていました。飲まなかったり、泣き出すとイライラするけど、常に笑顔で楽しく授乳できるようにしていました。
空腹すぎると飲むのに苦労!スケジュール管理の重要性
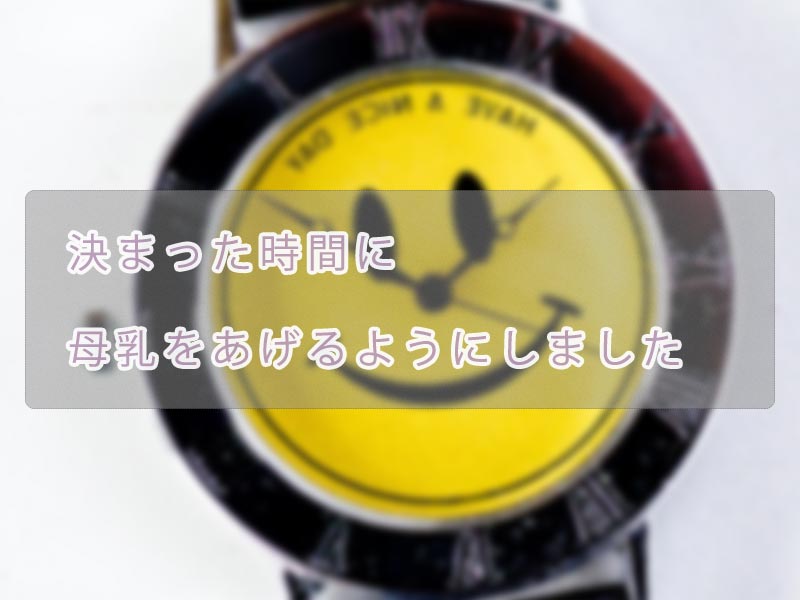
赤ちゃんが生後3ヶ月くらいの頃、授乳中でもよく泣いていました。昼寝等が原因で、授乳の感覚があいてしまい、お腹をすかせ過ぎていたにもかかわらず、私の母乳の出が良くないため不満だったようです。
とりあえず興奮していたので、抱っこで赤ちゃんを落ち着かせつつ、飲ませるようにしました。そうすれば大抵泣き止んで飲んでくれました。
しかし、一度だけ激しく泣いてしまい、なかなか泣き止まないことがあって本当に困りました。お腹がすいているのは明らかなのに、母乳を飲もうとせず、しばらく泣いて、その後疲れたように眠りました。
もちろん少しして起きたあとに、母乳をあげましたが、このまま泣き止まなかったらどうしようと怖かったです。
それから、なるべく授乳中赤ちゃんが泣かないように、決まった時間に母乳をあげるようにしました。間が空きすぎたりしないよう、昼寝中や遊びに夢中になっている間でも、時間をつくって授乳しました。授乳間隔の管理は、空腹による泣きを防ぐ重要な対策です。
また、母乳の出をよくするために、白米をたくさん食べました。すると、最初から勢いのいい母乳が出るようになりました。母乳の分泌や質には、特定の食品を多く摂ることよりも、栄養バランスの良い食事と十分な水分摂取がより大切であると言われています。
母乳の勢いが強すぎる!事前に搾乳で調整
よく、母乳育児が軌道にのるまで3ヶ月といいますが、まさに、3ヶ月になるまでは、ある意味戦いの日々でした。出産直後は出が悪かった私のおっぱいも、2週間程度で1回の授乳量が安定するようになりました。
これで安心!と思ったのもつかの間、なぜか、息子が授乳中に度々泣くようになったのです。なんでだろうと原因をネット検索などで調べに調べていたところ、ひとつ思い当たる点がありました。
それは、息子が欲しがる量よりもずっと供給量が多すぎたこと。「ひーん!」と泣きながらおっぱいに溺れ、顔を離せば、顔が乳まみれになることが多々ありました。これは母乳の噴射が強く、赤ちゃんがむせたり、飲みきれなくなったりする状態です。「母乳 勢いよすぎ 対処」 を探すママは多いです。
これはかわいそうだと思い、出来る限り、先に洗面所で軽く手で搾乳してから授乳するようにしたら、少しだけ落ち着きました。
それでも月齢があがるにつれて飲み方が上手になるので、溺れることはなくなっていきましたが、息継ぎをする時の顔中乳まみれは続きました。7ヶ月となったいまでは、その時を懐かしく感じるくらい、上手に元気に飲んでいます。
食生活の乱れから「おっぱいの味や匂いが変わった可能性」を考慮
うちの子が生後3ヶ月くらいの時、授乳中によく泣かれていました。まだ3ヶ月ですから、すべての栄養はおっぱいからしか摂れません。泣かれて飲まなくなると、今度は空腹で寝なくなるので困ってしまい、結局ミルクを試してみることに。
息子は、一度泣くと、もう絶対におっぱいを含みもしません。泣かれることが多かったのは、その時期、育児にいっぱいいっぱいで、自分の食生活にあまり気を使ってなかったことが原因で、おっぱいの味や匂いが変わってしまった可能性があると思います。
オムツが濡れていないか、部屋の温度が寒くないか、首の後ろが汗で湿っていないか、息子の周囲になにか刺激するようなものはないか、そして、私の機嫌も様子も特に変わりないですし、そういった環境にとても気を遣っていたんです。
完母にこだわっていたわけではなかったし、良質な母乳が出ないなら、ミルクを併用したほうがかえっていいと思ったので、迷わずミルクを導入しました。母乳とミルクの併用(混合栄養) も、赤ちゃんにとって大切な選択肢の一つです。
もちろん良質な母乳をあげられたら、それが一番いいとは思いますので、泣く原因に思い当たってからは、なるべく食事に気をつけて、授乳の際は息子の目を見て、笑いながら話しかけたり歌を歌ったりして、泣かないように機嫌を取っていました。
母乳の勢い泣きへの無策な解決の難しさ

産後1か月くらいまでは、おっぱいの出が悪く、おっぱいが足りずによく泣かれました。そんな時は、ミルクを足せば解決できたのですが、月齢3~4か月でおっぱいの出がよくなってきた時期にも、授乳途中にギャン泣きすることが何度もありました。
最初の何度かは、泣く理由がわからず困っていたのですが、ある時、おっぱいから口を離した時に、おっぱいが勢いよく出てきたことに気づき、ネットで調べました。
おっぱいが勢いよく出ると、赤ちゃんが飲める以上におっぱいが出てしまい、赤ちゃんがおっぱいにおぼれる状態になって、泣くことがあると知りました。「母乳 勢いよすぎ」 は、赤ちゃんにとって苦痛の原因となることがあります。
自分でおっぱいの量はコントロールできないのと、勢いよく出ても、私自身おっぱいの量が多い方ではなく、たぶん少ない方だったので、搾乳して与えるということもできず、あまり解決方法がなかったです。このような場合は、助産師や専門家に相談し、授乳姿勢の工夫などについてアドバイスをもらうことも大切です。
オムツの不快感による嘔吐に注意
私が授乳中赤ちゃんがよく泣くと感じたのは、生後一ヶ月ぐらいでした。2人目ですが、母乳で育てることは初めてだったので、わけがわかりませんでした。
授乳中で一番泣いていたのは、オムツが濡れている時です。その時は、必死すぎて気づかなかったのですが、旦那や母親に「オムツがぬれていて気持ち悪いんじゃないの?」と指摘されてから気づきました。
授乳中泣いてしまった場合は、一旦授乳することを辞めて、あやしてから授乳するようにしました。
授乳中に泣いてしまって一番困ったことは、泣きすぎて嘔吐してしまったことです。服を取替えて洗ってとやっていて、授乳どころではなかったです。
それからは、授乳の際、赤ちゃんが泣かないように、オムツを取り替えてから授乳するようにしました。泣きすぎると嘔吐につながるため、不快感の原因を早急に取り除くことが大切です。
母乳の出が良すぎる時の「縦抱きスタイル」
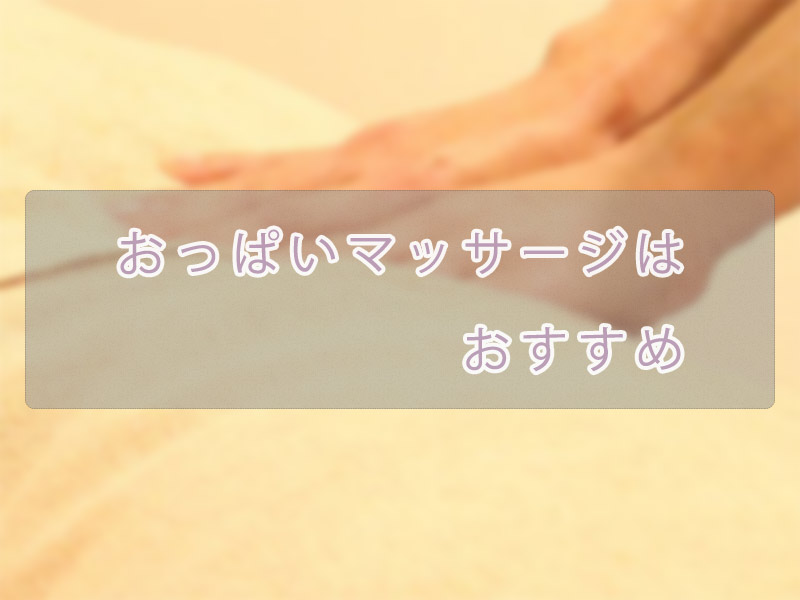
生後3カ月ごろになるまで、授乳中に、しばしば赤ちゃんが泣いていることがありました。私は、よく母乳が出る方で、いつも胸が張っている状態でした。
泣いているときは、だいたい午前中で、よく母乳が出る時間帯でした。赤ちゃんは、まだ吸って飲む力が弱かったので、母乳が飲みきれずにむせて泣いていました。
泣いては飲んでの繰り返しで、吐いてしまうことがありました。急に口を離してしまうので、赤ちゃんの服や顔が母乳で濡れてしまって、全部着替えるなんてことがしょっちゅうでした。
これではかわいそうだな、と思い、胸が痛いほど張っている時は、事前に、おっぱいをマッサージして、少し母乳を出すようにしておきました。絞るとよくないと聞いたので、押し出す方法で出しました。
他には、縦抱きスタイルで飲ませると飲みやすそうでした。縦抱きは、母乳の勢いを和らげる効果があり、「母乳 勢いよすぎ 対処」 としてよく推奨されます。いろいろ工夫して飲みやすくなったのか、泣く回数も減りました。赤ちゃんも大きくなってくると、飲むのがうまくなり、今ではむせることも吐き出すこともありません。
張ったおっぱいは搾乳で調整し、オルゴールでリラックス
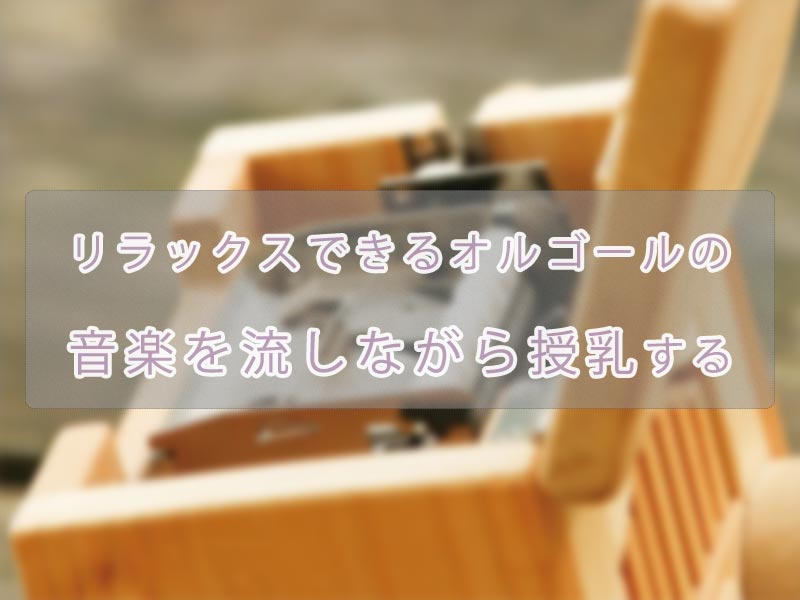
生後3ヶ月くらいのときは、授乳中にしょっちゅう泣かれました。泣くのは決まって母乳を与えていた時。なぜ母乳を拒否するのかがわからず、イライラしたこともありました。
実家が遠いために、親は頼れず、さらには一人目の子供だったこともあり、一人で悶々と赤ちゃんと接する日々でしたが、ある日、なぜ授乳中に泣くのか気づきました。
授乳間隔は、おっぱいが張った時にだいたい3時間おきにあげていたのですが、どうやらこれが原因だったかも。おっぱいが張りすぎて、飲みにくかったから泣いていたのかもしれません。「生後3ヶ月 授乳 泣く」 の原因として、飲みにくさはよくあることです。
これに気づいてからは、少し搾乳してから飲ませると、赤ちゃんはもちろん、私自身も楽に授乳できました。授乳中に泣かれると、なにがなんでも飲まない!という感じになるので大変でした。
搾乳してから飲ませても、グズって飲まない時も、テレビを消して、リラックスできるオルゴールの音楽を流しながら授乳すると、私も赤ちゃんもリラックスした気分になって、泣くのをやめることがありました。
赤ちゃんもひとりの人間。親子とはいえ、同じ人間同士の関わりあいの中で、思うようにいかないこともありますが、あとから、必ず大変だったねと笑って言える時がくるので、授乳の辛い経験もいい思い出です。



