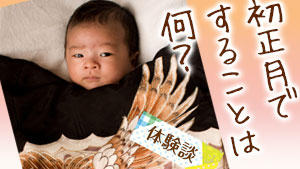おせち料理の種類と由来~子供に伝えていいきたい縁起物
お正月に家族でいただくおせち料理。かつては、母から娘や嫁に各家庭の味が引き継がれていましたが、現在ではデパートやインターネットなどで豪華なおせち料理を購入できるようになり、手作りされないご家庭も増えていますね。
忙しくて手作りされないお母さんも、おせち料理の由来や各料理に込められたいわれについては、ぜひお子さんに説明してあげたいものです。今回は、おせち料理の意味や種類、いわれなどを、お子さんにもわかりやすく解説していきます。お子さんに人気のおせち料理も紹介していますので、お子さんが好きそうなものだけ手作りしてあげるのも喜ばれるかもしれません。
おせち料理の意味

おせち料理は、元々は、季節の区切りである「節日(せちにち)」に食べる料理、「御節供(おせちく)」に由来しています。節日の中でも特に重要なのが元旦です。
奈良時代には、宮廷の行事で出されるものでしたが、次第に庶民にも伝わり、江戸時代には、新年のお祝いと豊作の願いを込めて、今私たちが食べているようなおせち料理の形になりました。
おせち料理は、年神様(としがみさま)を迎え、お供えするために、大晦日までに用意されます。そして、元旦の朝に、年神様からのお下がりとして家族でいただくという風習があります。年神様は、新しい年の幸福や恵みをもたらす神様とされています。
おせち料理はいつ食べる?

昔の人たちは、おせち料理を元旦から3日までの三が日に食べていました。これには、お正月期間は火の神様を怒らせないよう、台所で料理をすることを控えるという風習と、お正月くらいは女性が日々の食事の支度から解放されるようにという配慮が込められています。そのため、おせち料理には、日持ちがするように味付けの濃い料理が多くなっています。
ただ、現代のお子さんは、三が日もおせち料理を食べ続けるのは飽きてしまうかもしれません。元旦だけいただくように、食べきりサイズのおせち料理を購入したり、1日分だけ作ったりするご家庭も増えています。
子どもが好きなおせち料理は?
おせち料理は、お子さんが普段食べているハンバーグ・コロッケ・から揚げなどと味付けや食感が異なるため、お箸が進まないお子さんも少なくありません。ですが、お祝いの料理ですから、お母さんとしては、少しでも食べてほしいですよね。伊達巻・栗きんとん・黒豆などは、甘めの味付けで比較的お子さんにも食べやすくなっています。また、エビの料理も人気があります。
無理せずにおせち料理を楽しみましょう

せっかく頑張っておせち料理を作ったのに、お子さんがあまり食べてくれなかったら、お正月早々がっかりしてしまいますよね。最近は、バラエティー豊かなおせち料理がデパート・スーパー・ネットショップなどで販売されています。年末は食材の値段も高くなるため、手作りするのも意外と費用がかかることがあります。無理して全て手作りせずに、美味しいおせち料理を購入して楽しむのも良い方法です。
お子さんと一緒に食べるものですから、おせち料理を購入する際は、原材料などには気を配りたいですね。生協の宅配でもおせち料理を取り扱っているところもあります。
最近は、おせち料理を全て手作りするご家庭は少なくなっています。数品だけ家で作って、残りは市販のおせち料理を楽しむご家庭が多いので、「手作りしなきゃ」とあまり頑張りすぎないでくださいね。
おせち料理の種類といわれ
20~30種類あると言われるおせち料理。その一つ一つに、きちんと意味が込められています。また、おせち料理は、「幸せを重ねる」という意味を込めて、お重に詰められますが、それぞれのお重にどの料理を詰めるかという役割も決まっています。
ここでは、代表的なおせち料理とその意味についてご紹介します。今年のお正月は、お子さんとおせち料理の意味についてお話をしながら、にぎやかに食卓を囲んでください。
一の重
一の重には、祝い肴(いわいざかな)と口取り(くちとり)を詰めます。祝い肴は「三つ肴」とも呼ばれ、関東では黒豆、数の子、田作りを指し、これがないと正月の祝いが始まらないとされる重要なものです。代表的な祝い肴と口取りは、以下の通りです。かまぼこは、お子さんにも人気があります。市販のおせち料理に入っているものだけでは足りなくなることもありますので、別に購入しておいても良いでしょう。紅白のかまぼこは、切り方を工夫するだけで、とっても豪華なお重になります。
紅白のかまぼこ

紅は魔除け、白は清浄という意味があります。かまぼこの半円の形は日の出に似ているため、初日の出に例えられ縁起が良いとされています。また、かまぼこが板に乗せられていることから、「檜舞台にあがる」という例えに通じ、勝負運がつくとも言われています。
伊達巻
伊達巻は、昔の手紙や書物に使われていた巻物の形に似ているため、勉学ができるようにとの願いが込められています。まさに、お子さんに食べてほしい料理ですね。また、反物(たんもの)の形にも似ているため、一生衣類に困らずに生活できるようにとの願いも込められています。市販の伊達巻は甘すぎることもあります。砂糖が気になるようでしたら、手作りしてあげるのも良いでしょう。
栗きんとん

栗きんとんは、その「金色」から連想されるように、金運の上昇を願う料理です。家族がお金に困ることのないように、家族揃って栗きんとんをいただきましょう。栗きんとんは、甘くてお子さんに人気のあるおせち料理の一つですが、サツマイモは意外と傷みやすいので、冷蔵庫にきちんと入れるなど、保存方法には十分に気をつけてください。
昆布巻き
昆布は、「喜ぶ(よろこぶ)」という意味に通じることから、古くから縁起の良い食材としてお祝いごとに使われてきました。おせち料理でも、喜びごとが多い1年になりますようにとの意味が込められています。また、「こぶ」の音から子宝に恵まれ子孫が繁栄しますようにという意味も込められています。昆布だけを巻いたものと、中に鮭などの魚を巻いているものがあります。
黒豆

豆は、節分にも使われるように邪気を払うと言われています。また、「まめに働く」という語呂合わせから、黒く日焼けするほど勤勉に働けるようにとの願いが込められています。黒豆を自分で煮ようと思うと、前の晩から水につける必要があり、時間と手間がかかりますね。また、せっかく作ってもシワが出来て残念な思いをすることも多いです。市販の黒豆は、シワひとつなく色ツヤも良く仕上がっていますので、市販品を利用するのも良いでしょう。
田作り
田作りとは、片口イワシの稚魚を乾燥したものを砂糖や水飴などで炊いたものです。江戸時代に片口イワシを田畑に肥料としてまいたところ豊作になったことから、豊作を祝う料理として親しまれてきました。田作りは、「ごまめ」とも呼ばれており、「五万米」という当て字がつけられています。少し固いので、お子さんが喉に詰まらせたりすることのないように注意しましょう。
二の重
二の重には、焼き物と酢の物を詰めます(地域やご家庭によっては、一の重に入れられる口取りの一部を二の重に詰めることもあります)。焼き物に使われる魚は、それぞれの地方や家庭により特色があります。ブリ・鯛・エビが多いですが、中にはウナギを使う場合もあります。もちろん、1種類と決められているわけではありませんので、2~3種類入れても大丈夫です。
えび

エビは、火を通すとお年寄りのように背中が丸まることから、「背中が曲がるまで、元気で過ごせますように」との長寿の願いが込められています。おせち料理では、塩焼きや甘辛く煮ることが多いですが、ご自宅で作るなら、お子さんが食べやすいようにエビフライなどにするのも良いでしょう。お正月くらいは豪華な大きいエビをいただきたいですね。
紅白なます
人参と大根で作られる紅白なます。形が水引に似ていることから、平安や平和を願う意味が込められています。紅白の色がお祝いを表します。小さいお子さんには、酸っぱいので少し食べにくいかもしれません。ご自宅で作る時には、お子さんが食べずに余ってしまう可能性がありますので、作る量に気をつけてください。
数の子

数の子は、ニシンの卵です。小さい卵が沢山詰まっている数の子は、子孫繁栄の象徴とされ、子宝を願っておせち料理に取り入れられています。数の子は、塩抜きをする必要がありますし、塩の抜き加減も難しいものです。塩抜き済みのものを使用したり、市販のものを購入したりするのも良いでしょう。
鯛の姿焼き
鯛の姿焼きがあると、おせち料理が一気に豪華になりますね。「めでたい」という語呂合わせから、鯛は古くからお祝い行事の定番食材として使用されてきました。また、恵比寿様が手に持っている魚としても知られており、縁起が良いとされています。お重に入りきらない大きさの鯛の場合には、大皿に盛ってお重の横に並べましょう。
ブリの照り焼き

ブリは、ツバス(またはワラサ)→ハマチ→メジロ→ブリと成長するにつれて名前が変わっていくことから、出世魚として知られています。そのため、立身出世を願う縁起物としておせち料理に使用されます。九州地方では、ブリを一匹購入して、照り焼きにしたりお雑煮に入れたりするご家庭もあるようで、お歳暮にブリが一匹贈られることもあります。
蛤
蛤は、左右の貝がピッタリと合うのは、その対の貝だけであることから、夫婦円満の象徴とされています。おせち料理やお雛様などのお祝い行事に使われてきました。現在では、煮蛤にしておせち料理に入れられることが多いです。
三の重
三の重には、煮物(煮しめ)を入れます。おせち料理の煮物に使われる野菜は、日持ちがする根菜が中心となっています。普段から食卓に登場している野菜ばかりですが、その野菜の持つ意味を知ると、お子さんもおせち料理を楽しく食べることができそうですね。ご家庭により筑前煮にして一緒に煮たり、それぞれの野菜を別々に調理したりと、特色があります。
たたきごぼう
地面の下深くまで根をはっているごぼうを家庭に例えて、家がしっかりして家庭円満になりますようにとの願いが込められています。また、ごぼうは、細いですがとても丈夫なので、細く長くつつましく生きることができますようにとの意味合いもあります。たたきごぼうは、ごぼうを叩くことで味を浸みやすくしています。酢が入っているので、苦手なお子さんもいるでしょう。お子さんにおせち料理でごぼうを食べさせてあげたい場合には、きんぴらごぼうにすると良いでしょう。
里芋
里芋は、親芋に子芋ができ、子芋から孫芋、そして孫芋からひ孫芋とできる、とても珍しい野菜です。次々に次の世代ができることから、里芋は子孫繁栄の縁起物とされてきました。里芋は、アレルギーを起こすことがある野菜です。離乳食用のおせちを作りたい場合は、里芋は離乳食中期以降からにしてくださいね。
れんこん

れんこんは、穴がたくさん開いていることから、将来の見通しが良くなりますようにという意味を込めておせち料理に使われています。お煮しめにして三の重に入れられることもありますが、酢ばす(酢れんこん)にして、二の重に入れられることもあります。
筑前煮(お煮しめ)
筑前煮は、元々は九州地方の郷土料理です。全国的には「お煮しめ」と呼ばれるものになります。筑前煮には、ごぼう・里芋・れんこんなどの縁起の良い野菜のほかに、干しシイタケ・こんにゃく・人参・鶏肉などを一緒に煮ます。色々な食材を一緒に調理することから、家族が仲良く結ばれますようにとの意味が込められています。
おせち料理は祝箸で食べよう
おせち料理を食べるお箸にも気をつかいましょう。おせち料理を食べる時には、家族それぞれの名前を書いた箸袋に入れた「祝箸」を使ってください。祝箸は、両端が細くなっていてどちらからでも食べられるようになっています。これは、一方は自分が食べて、反対側は年神様が食べるためとされています。祝箸の丸みを帯びたかたちは、妊婦や俵を連想できるため、子孫繁栄や豊作を願う意味合いもあります。