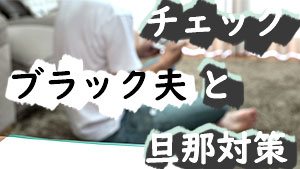育児で旦那さんを頼れないのはなぜ?ママが察して欲しい6つの理由と夫婦の溝
育児を旦那さんに任せられないと思っている奥様は、世間の男性が思っている以上に多いです。「〇〇ちゃんパパ、イクメンだからいいなぁ」といった会話になると、謙遜とは思えないパパ育児の受け入れがたい実態がママ友の口から飛び出すこともあります。
育児に積極的にかかわりたい、妻を助けたいというパパの想いが空回りすると、やがて夫婦間に溝が生じ、次第に溝が大きくなって産後クライシスを招いてしまうこともあるのが現代の夫婦事情です。
子供のためだけでなく夫婦仲を円満に保つためにも、小さな乳幼児がいるご家庭の旦那さんは、ママの信頼を失う6つの理由を知って歩み寄りの育児を心掛けてください。また、ママもまたパパの状況に歩み寄る努力が大切になります。
1スマホゲームに夢中で子供をきちんと見ていない

育児を任せたはずの旦那さんが、スマホゲームに夢中になって子供を見守らなかったり、テレビばかり見せたりしているようでは、妻たちが「任せられない!」と思うのは当然です。「育児 夫 頼れない」と感じる大きな理由の一つです。
自分はスマホゲームをして子供にテレビばっかりみせる旦那
現在子供は3歳。主人はほぼ育児をせず、ワンオペ状態です。主人に育児を任せられないと思ったのは、つい1週間前のこと。私が美容院に行きたいから子供を見ていて欲しいと頼んだときです。
美容院から帰ってくると、子供はソファでテレビを観て、主人はスマホでゲーム。子供に「パパと一緒に遊んだ?」と聞くと子供は「ずっとテレビみてるよ。」と言っていました。
主人には「何故テレビばっかり見せてるの?せっかく一緒に遊べる時間だったんだから、もっと子供と遊んで欲しい」と言いましたが、返ってきた言葉は「(ゲームの)対戦時間だったから」。
話し合いはしましたが、結果主人は「自分が大事、1番」ということだけがわかり、解決まではいたりませんでした。普段仕事が忙しく子供とコミュニケーションを取る時間がないので、もう少し子供とコミュニケーションを取って、一緒に遊んで欲しいと思います。
携帯ばかりいじっているから
娘が一歳を過ぎて歩くようになった頃に、家族で公園へ行きました。歩くようになったものの、まだまだ親は後を追いかけて、きちんと行動を見なければならないのは当然なのに、私がトイレに行っている間に娘が自転車とぶつかりそうになっていたのです。
トイレから戻ると自転車のおばさんに主人が何か言われているようで、何があったか聞いたところ、主人が携帯をいじっていて娘を見ていなかったと言われました。
私は親としての責任と行動に怒りがこみあげてきて、家に帰ってからずっと怒りながらの話し合いでした。携帯ばかりいじるクセをやめるように本人も言ってくれて、今はあまり娘がいるときはいじらなくなりましたが、とても育児を任せるなんてできません。
娘は現在3歳ですが、主人は毎日帰りが遅く、これまでずっとワンオペ育児でした。主人はあまり娘と一緒にいる時間がないため、もっとかまってあげて欲しいといつも伝えていますし、主人も分かってはくれます。
ただ、疲れていたりもするので完璧を求めるのも悪いことと思っています。旦那さんのやるべき仕事は外での仕事。私は育児。ですからお互いの仕事を尊重しながら生活するようにしています。イライラする事も多く疲れる事もありますが、なんとか今を乗り越えて日々頑張ろうと思っています。
泣いていてもスマホばかり見ているから
現在3歳と0歳の子供がいます。旦那は家事育児をちょくちょく手伝ってくれています。それでも2割程でしょうか。ゴミ出しや子供の入浴、皿洗いをたまにしてくれます。私が専業主婦なので、ほとんどは私です。
旦那に育児を任せられないと思ったのは、下の子が産まれてからです。上の子だけの時は、寝かしつけなどもっと協力してくれていたように思いますが、旦那は働いているし、私は専業主婦なので、やはりほとんどを私が担うのが普通なのかなと思ってしまいます。
子供が泣いたりグズッたりした時に、ご飯中のスマホはスマホをやめて欲しいとは言いました。その時は聞いてくれるのですが、その後また忘れるのか何日か後には戻ってしまっています。
ずっと自分ばかりだと疲れてしまうので、1?2時間程の時間でも旦那に任せて、カフェに行ったり、マッサージなどに行ったりして、リフレッシュするようにしましょう。ほんの1時間でも気持ちは楽になると思います。
小さな子供の交通事故や行方不明事件はもとより、赤ちゃんや幼児にテレビやスマホなどの電子機器を与え過ぎることの悪影響は、メディアでもよく取り上げられます。「育児に集中しない夫」は、妻にとって安全面での大きな不安要素となります。
育児に健康や安全への配慮は必須
苦痛に耐えて産んだ我が子に、ニュースでも指摘されるような危険が及ぶ行いを旦那さんがすると分かっていて、安心して任せられる母親はほとんどいません。もしプロに任せたのにテレビばかり見せられたり、スマホゲームに夢中で子供と遊んでくれなかったりしたら、あなたも腹が立つでしょう。パパになったら育児とはスマホを見ながらではできないような、子供の命と健全な発達を預かる重要な仕事だと認識することが大切です。
2小さな子供をすぐ感情的に怒鳴りつける
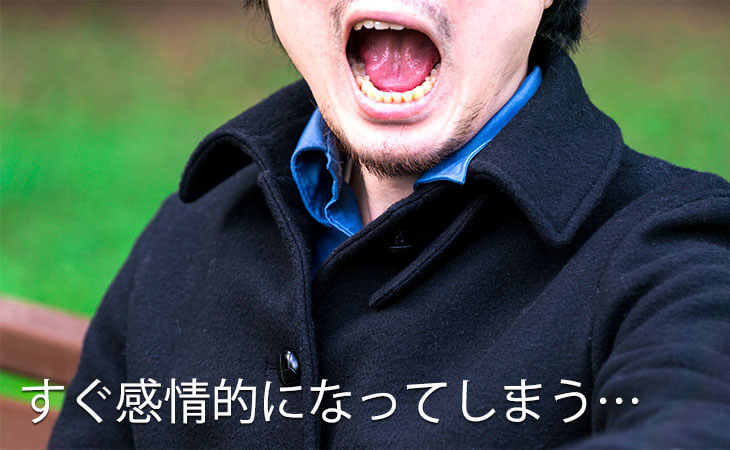
育児を旦那さんに任せられないと思う妻が、夫が思っている以上に深刻に悩むのが、小さな我が子への感情的な言動です。「夫 育児 ストレス」や「怒る」といったキーワードで悩む親御さんは多いです。
旦那さんにしてみれば、筋の通った理由で叱っているつもりかもしれませんが、妻や子供にとってパパは力でかなわない相手であり、安心感を得るべき存在です。あまりにもひどい怒鳴りつけ方をされると、子供は生理的に耐えがたい恐怖を感じることがあります。
子どもに対してすぐに感情的に怒鳴るから
子どもは4歳と0歳です。夫は仕事が忙しく、朝は子どもたちが起きる前に出勤し、夜は子どもたちが就寝してから帰宅することが多いです。休日も仕事に行くことがあるため、家事育児はほぼワンオペの状態、9割5分が私です。
夫に育児を任せられないと思ったのは、上の子が歩き始めるようになった頃です。子どもが夫の眼鏡を構っていてつい壊してしまったのですが、子どもの手に届くようなところに眼鏡を置いていた夫が悪いのに、子どもに対してものすごい剣幕で怒鳴っているのを見たからです。
子どもはわざとしたわけではないし、壊されたくないなら大人であるあなたが置く場所に注意すべきだと話しました。その結果、夫自身気を付けてはいるようですが、気を抜いて再度眼鏡を壊されたときはまた怒鳴っていました。
子どもは今いろんなことを勉強していて、わからないこともたくさんあるのだから、感情的に怒るのではなく、落ち着いて教えてあげてほしいと伝えてはいます。本人もそうだねと言いますが、なかなか実行はできていません。
夫婦といえども違う人間です。言わなくてもわかってくれるではなくて、言わなければきちんと伝わりません。何度言っても伝わらないこともありますが、夫婦二人で子育てをしていくためにも、普段からコミュニケーションをとっておく必要があると思います。
育児中は、子供の自己肯定感を育む接し方を心掛ける母親が多く、従来の「怒鳴ったり叩いたりするしつけ」の弊害を心配して、叱らない子育てや共有型しつけを心掛けるママが増えています。
親が子供を怒鳴ったり暴言を吐いたりすることの悪影響が社会に広まりつつある中で、感情のコントロールができない大人に子供を任せることへの不安は非常に大きいです。
旦那さんとしては「小さなころから公共マナーや善悪を教えなければならない」という父親としての責任感から叱るのでしょうが、感情に任せて怒鳴る行為は、子供への教育的な効果よりも心理的な悪影響を及ぼす可能性が高いことを理解する必要があります。
妻に信頼される育児には忍耐と冷静さが必須
企業でも「共育」を推奨する今の世の中、怒鳴って相手を責める短気さを表に出していては、家庭内でも信頼を得ることはできません。父親の役割は社会で生きる術を子供に教えることですので、時代遅れの感情的な叱り方ではなく、冷静に諭す方法を実践する努力が必要です。
妻としては、夫が子供の過ちにすぐ感情のコントロールができなくなり、静けさを失って怒鳴る姿に問題を感じて、育児を任せられないと思ってしまうのです。子育ては親育てのチャンスですので、パパはぜひ一度自分の行いを客観的に振り返り、アンガーマネジメントの視点を取り入れてみましょう。
3おむつ替えやシャンプーなどの育児が雑すぎるから

育児を旦那さんに任せられない理由として意外と多いのが、雑なお世話への不満です。女性よりも察する能力に長けている女性は、旦那さんの育児の雑さで子供が感じる不快感を見過ごすことができません。
女性に長けている「察する力」は、子供の非言語的なサインを読み取り、育児の質を高めてくれます。子供の愛着形成が順調に安定して進むためには、育児の質の高さが重要ですので、妻は旦那さんの雑な育児を見て見ぬふりなんてできないのです。
無わが子をお風呂嫌いにした
現在我が子は1歳8ヶ月です。生まれた頃から基本的にワンオペ育児ですが、出産が緊急カイザーになったこともあり私自身の回復も遅く、お風呂は旦那さんにお願いしていました。
しかしながら、我が家の旦那さんはとても雑なのです。特にお風呂に関してはシャワーを子どもの頭からジャーっとかけ流し、目に石鹸は入るし水は口に入るし。そのため子どもは生まれてからずっとお風呂嫌いです。
何度か話し合い、今では少しはマシですが、ついここ数日前、お風呂場から大泣きの声が聞こえてきました。それから数日間は私がお風呂に入れていますが、我が子は毎回泣きべそ。もっと我が子に対して丁寧に接してほしいと思います。
やはり旦那さんは奥さんの要望にできるだけ応えることがポイントだと思います。そうすることで日々、ワンオペの奥さんたちは旦那さんに対して信頼できる、任せられるときもあると安心感が得られ、それが夫婦円満につながると思います。
旦那が雑で逆に育児の手間が増える
4ヶ月の息子のママです。基本的にワンオペ育児ですが、私はその方がいいと思っています。正直に言って旦那に育児を任せても負担が増えるだけです。
旦那は消防士なのでお世話とかできる人だと思っていましたが、男の子なのにおむつ替えもまともにできません。
旦那はきちんとやっているつもりなのですが、先日もうんちのオムツ替えを頼んだら雑でうんちが残っていて、オムツかぶれしてしまいました。あやすのも激しすぎるので、怒ってやめてもらいました。
旦那とは話し合いをしていません。機嫌が悪い時はすぐ不機嫌になって意固地になるし、人の話を聞けず自分の主張ばかり大声で繰り返す人だからです。
私は専業主婦ですし、旦那の職業を考えると、育児にまでアレコレ求められないと諦めています。旦那さんも仕事が大変なので、育児がどうしても辛い時は実家やファミリーサポートに頼るといいと思います。
雑な育児をする旦那さんの多くが、一度や二度は妻から注意を受けているはずです。その言葉に聞く耳を持って改善に努めましたか?
言っても変わらない旦那さんの場合、妻は育児を信頼して任せられなくなり、「自分一人でやった方がいい」と旦那さんに頼まなくなります。自ら大変なワンオペ育児を選ぶようになった妻は、心の奥に不満を蓄積させ、ある時あふれだして怒ったりします。こうして次第に溝が深まっていくのです。
何も頼まれなくなった旦那さんは、妻や子供との間にできた溝に気を付けてください。年々母子の絆だけが深まって、家族の輪に夫だけが入れなくなったという家庭は珍しくありません。
育児への妻の信頼を得るには聞く耳が必須
収入を得てくることこそが夫であり父親の仕事だと考えている男性もいるでしょうが、家庭内でも妻や子供の話に聞く耳を持ち、行動を改善する努力が必要です。妻からの具体的な指摘は、育児スキル向上のための重要なヒントだと受け止めましょう。
4育児を放棄して家事分担もきちんとやる気がない旦那だから
育児だけでなく物事の結果はやる気で変わります。もちろん能力も大切ですが、それ以上にきちんとやる気があるかないかは重要です。
育児をしない旦那さんはイクメンが増えた現代にも数多く実在し、やる気がでないからと感情に流されてあっさり子供のお世話を放棄することもあります。命より大切な我が子の育児を、たとえ旦那さんでもやる気のない人には任せられないのです。
期待した方がしんどいので、最初から期待しない。
現在子供は6歳です。普段から旦那はあまり育児に関与しておらず、休みの日も自分優先で行動したり、だらだら過ごしたりしています。家事も私の体調が悪い時には手伝ってくれますが、それ以外は全くです。
旦那に育児は任されないと思ったのは、子供が生後半年の時でした。私が友人の結婚式に参加するときに旦那に預けましたが、案の定、育児は出来ず、オムツもぱんぱん、子供は泣きすぎて顔がぐちゃぐちゃ。服はよだれで汚いし、部屋もぐちゃぐちゃ。
それ以来、旦那には育児を任せられないと思ったのですが、話し合いをしたって逆ギレするだろうと思ったので話し合いはしていません。話し合いをしてないので解決はいまだにしていませんし、主人は私の雰囲気から察することすら出来きていません。
もともと亭主関白だし自分勝手なので、育児に関わってほしくもありませんでした。下手に手を出されると余計に私の仕事が増えてしまうので、期待もしていません。
何もしてくれない旦那さんを持つと疲れてしまうと思いますが、期待してしまうとかえって気苦労すると思うので、ワンオペ育児は大変ですが慌てずゆっくりしたら一人でも対応できるので大丈夫ですよ。
したがらない
子供は2歳でお互い仕事をしているけど、私はパートなのでほぼ育児は私しかしません。旦那は頼んでもノータッチです。
ある日オムツ替えを頼んだ際に、チラッとめんどうそうな表情をしたので、その日から話し合うことなく、もう頼めない、頼みたくないと思いました。
話し合うことはしなくても、めげずにして欲しいことを頼んだりしましたが、疲れているためかしてくれませんでした。喜んで幸せな空間も最初だけだなとショックですが、諦めも肝心なのかなあと思いました。
核家族化が進む現代社会では、妻が専業主婦でも人手が足りません。そのため夫も育児を主体的に行う責任があります。どんなに立派な仕事をし、お金を稼ぎ、会社で評価されても、放任主義のつもりで子供の世話を怠る父親では、妻や子に信頼されるはずがないのです。
家族に信頼される旦那さんにはやる気が必要
何ごとも主体的に行うと楽しさが増しますので、育児を引き受けたのであれば積極的に行いましょう。もし育児を放棄したくなるほど疲れているのであれば、正直な気持ちを妻に伝えて実家やファミリーサポート、ベビーシッターに頼るという代替案を伝えるのも一つの方法です。
5日頃ワンオペ育児で赤ちゃんが懐かないから

育児を旦那さんに任せたくても、子供が懐いていなかったり、育児スキルが低かったりすると、任せられないと思ってしまうママもいます。「パパ見知り」は、ワンオペ育児のご家庭では特に起こりやすい現象です。
赤ちゃんがパパを認識する時期は、パパがどれくらい手をかけてお世話をしたかにもよりますが、仕事が忙しく朝から夜遅くまで働いているパパにしてみれば、それが原因で任せてもらえないなんて切ない話です。
寝かしつけ出来ない
現在9ヶ月の娘の育児に奮闘しています。我が家の場合は、旦那の仕事の時間が不規則なのでほぼワンオペ育児です。仕事が休みの日はゴミ捨てやお風呂に入れてくれたりしていますが、本当に入れるだけで脱ぎ着させるのは私の仕事です。
里帰り出産後は生後2ヶ月のときに自宅に帰ってきたのですが、その時からお昼寝も夜の寝かしつけも全部私がやっていました。その結果からなのか、今でも旦那では寝てくれません。
寝たくて泣いていても、寝かしつけ出来ないので遊ばせようとして余計に泣き、最終的には泣き疲れれば寝るだろうと泣かし続けているので、とてもじゃありませんが育児を任せる気にはなりません。
この事について夫婦の間で話し合いはしていませんが、結果として私が寝かしつけをする代わりに食器を洗ったりオムツ替えを自然としてくれたりするようになりました。
お願いすれば大抵のことはしてくれるので、それだけが救いです。妊娠当時から基本的に褒めて伸ばすようにしようと話し合っていたので、片方が怒ったらもう片方が慰めるということをしています。
とはいえ、これら全て旦那が休みの日にしか出来ないので、普段は7時~23時頃までほぼワンオペ。その分休みの日に2時間くらいの1人になる時間を貰っています。
同じような生活をしている人達も、割り切るところは割り切り甘えられる時は存分に甘えることが大事だと思います。お互いに頑張りましょう!
赤ちゃんの寝ぐずりは不快感や不安の表れでもありますので、日頃から側にいるママの方が上手なのは当然です。旦那さんがそこを任せてもらえなくても仕方がないと理解しましょう。
むしろ体験談のパパのようにおむつ替えや家事などを積極的に手伝ってくれる旦那さんは、いずれ子供や妻に信頼してもらえるようになるはずです。
懐かない子供の育児には手間と時間が必要
赤ちゃんや小さな子供は、手間をかけて不快感を取り除いてくれる人を信頼していきますので、仕事が忙しくて子供に懐いてもらえていなくても、嘆かずできるだけ時間を作って育児に携わりましょう。短時間でも質の高い関わり(スキンシップ、絵本の読み聞かせなど)を意識することが大切です。そんなパパの姿から子供は諦めない強さや思いやりを学べますし、いずれパパを大好きになってくれるはずです。
6旦那が疲れて寝てばかりだから
育児を任せたくても旦那さんが疲れて寝てばかりでは、当然任せられません。寝不足や疲労は仕事上のミスや効率の悪化にもつながるため、家庭での休養は社会人としての責任の一環でもあります。
とはいえ妻側も24時間365日休みなくワンオペ育児をこなすのは至難の業で、精神的に参ってしまいます。核家族なのに育児を任せられない妻の中には「仕事のセーブや転職を真剣に考えて!」と旦那さんに頼む人もいます。
寝過ごすから。
一歳になる子どもの母です。家事育児は一応夫婦で分担制になっています。ですが主人は仕事の日は帰りが遅くなったり、休日は休日で疲れて寝過ごしてしまったりで、私がやることが多いです。
もっと協力して欲しいと何度も話し合いましたが、主人は眠気に勝てません。でも私だけでやっていると疲れるし、ストレスもたまるので、ひたすら起こしてやってもらっています。
自分が倒れてしまったら子どもに迷惑がかかるので、育児を任せられないママは話し合ったり、分担したりして自分を労って下さい。
夫婦共にオーバーワークになっている家庭の場合、外で働く旦那さんに育児を頼みづらくなりますが、その分自分が無理をしてどうにかなることばかりではありません。
2本の手で足りなければ4本、6本、8本の手を用意すればいいのです。お金があればファミリーサポートなどを利用するのも一つの方法ですが、ない場合は子供を保育園に預けて共働きを選択し、夫婦間の負担を対等にするのも一つの方法です。
余裕がなければリモート育児やタスクの明確化を検討
育児負担はお世話だけではありません。予防接種や乳幼児健診などのスケジュール管理、育児情報の収集なども立派な育児の一環です。仕事が忙しくて家でどうしてもゴロゴロしたいのであれば、家にいなくてもスマホで情報収集や育児計画を立てる「リモート育児」の担当になって、精神的に妻の負担を減らしてみるのもよい方法です。タスクの「見える化」と責任分担が重要になります。
育児を任せられない旦那さんには男性の特性を理解して対応しよう
育児を旦那さんに任せられない妻の中には、「何度も話し合いをしたけれど聞いてもらえなった」という人も多いでしょう。女性は察することができない旦那さんにイライラし、「もう頼まない!」とさじを投げてしまいがちですが、男性は女性とはコミュニケーションの特性が異なります。
男性によく見られる特性を受け入れることは、男の子の育児にも役立ちますので、伝えなければ思い通りに動いてもらえないのが男性という考え方を知っておくとよいでしょう。
1男性は察することが苦手で、具体的な言語化が必要

育児が女性に向いていると言われる由縁の一つは、女性にみられる共感力の高さです。一方、男性は一般的に察することが苦手で、その分空間認知能力や客観的に物事をとらえることが得意だと言われています。
もちろん男性にも共感力が高い人はいますし女性にも共感力が低い人はいますが、育児をする旦那さんに「どうして察してくれないの?」と思っている場合は、男性ならではの特性だと理解して接し方を変えた方が、お互いに楽で円満に過ごしやすくなります。
察することが苦手な旦那さんへの対応
旦那さんはできるのにわざとやらないのではなく、「察することができないのだ」と自分に言い聞かせ、毎回言葉でやって欲しいことを伝えましょう。例えばお尻拭きが雑な旦那さんには「うんちが残るとオムツかぶれするから、ベビーコットンを使ってね」「ここ、うんちが残りやすいから特にきれいに拭いてね」と、何度も具体的に伝えてマニュアル化することが効果的です。
2男性を動かすには「役割と責任」の明確化が効果的
女性のモチベーションアップに効果的なのは、「満たされた気持ちになること」や「共感」であるのに対し、男性の場合は「責任感」や「課題達成」がモチベーションにつながりやすい傾向があります。
「私もう限界!頼りにできるのはパパだけ!」「パパの担当はこれとこれ!頼んだよ!」といった、役割と期待を明確に伝えることこそが、モチベーションアップにつながります。「叱咤激励」よりも、「具体的なタスクと達成後の承認」がより効果的です。
やる気がない旦那さんが育児をしたくなる対応
疲れが溜まっている状況であれば休息が必要ですが、呆れて放置したくなるような状況であれば、具体的な育児タスク(例: お風呂担当、週末の午前中の散歩担当)を渡し、「これはパパの仕事だよ」と責任を持たせてみましょう。そして、そのタスクをこなした際には具体的に感謝の言葉を伝えることで、達成感が得られ、次の行動につながりやすくなります。
3男性への提案は比較やデータを使って論理的に伝える
男性には女性が直感的に思いつくことを「思い込み」と思う傾向があります。例えば妻が子供の様子にいつもと違う異変を感じて「体調が悪いかも」と言っても、わかりやすい異常がなければ「大丈夫だよ」と言われてしまうことがあります。
けれど直観力と共感力が強い女性は、話しや体験を自分の人生に置き換えて理解を深めているため「ひらめき」が出やすく、実際に数時間後に熱が出たなんてこともあり、多くの場合は当たります。旦那さんにしてみれば子供のことをいい加減に考えているわけも、妻の話を聞いていないわけでもないのですが、女性に比べると論理やデータを重視する特性があるため、妻のひらめきがどうしても根拠のない思い込みに感じられるのです。
話しを聞いてくれない旦那さんへの対応
できるだけ比較対象や具体的な事実を作って伝えましょう。例えば「この子いつも朝はご機嫌なのに、今朝はひどくグズってる(比較)」「この間熱を出した時も2日前は食欲がなかったけど、今日も食欲がない(データ)」など、比較できるデータがあれば旦那さんに直感を信じてもらいやすくなります。
育児を任せてもらえない旦那さんは女性の特性を知って信頼をアップしよう

育児を自主的にやろうと思っても任せてもらえない旦那さんもまた、女性の特性を知ることで妻からの信頼を得やすくできます。女性のニーズを理解し、共感的な姿勢を見せることが大切です。
1客観的な評価ではなく妻ならではのプロセスを労う
妻を褒めて労うことで、妻は自分を見てくれていることに安心感や信頼感を抱くことができます。ところが「すごいな」「やっぱりママじゃなきゃだめだな」と褒めているつもりなのに、軽スルーされてしまうことってありませんか?
女性は結果よりプロセスを大切に考える人が多いため、結果だけを褒めると逆に落胆してしまうことがあるので要注意です。
褒めたり労ったりする場合は、より具体的に「ママは家の中の整理整頓が上手いから、おむつ替えセットも使いやすくて早くできるんだね」「ママだと泣き止むのは、これまでで一番頑張って育児をしてきたからだね。本当にありがとう。」など、努力の過程や貢献度を認める言葉を選びましょう。
2満ち足りた気持ちを感じられる休息時間を与える
女性に叱咤激励をするのは逆効果です。精神的な余裕と満たされた気持ちを得られる時間を設けてあげることが、育児の活力につながります。昼休みにスイーツを買い、早く帰って妻の自由な時間(自分時間)を作ってあげるなど、ホッとできる時間をできるだけ作ってあげましょう。そうすることで育児をいきいきと行いやすくなりますし、旦那さんへの感謝の気持ちも増します。
3妻が泣く効果を理解して直感には聞く耳を持つ
妻が泣くのは深刻なパニックを回避するための行動ですので「泣けば済むと思って」などと呆れず、心の疲労のサインだと理解しましょう。
妻の直感についても話をよく聞き、「責任は俺がとるから、試してみよう」と言ってあげてみてください。妻は夫に恥をかかせないようにもっと頑張ろうとしてくれますし、信頼感が増します。
4とりとめのない話を軽くあしらわない
男性が嫌うとりとめのない話で、女性は無意識にですが周囲の状況や家族の体調・気力などを把握しています。
このとりとめのない話により、女性は気遣いや失敗を防ぐ手助けをしやすくなりますので、妻が話しかけてきたら軽くあしらわず、自分をアシストしようとしているのだと好意的に受け止めましょう。
旦那さんの育児を信頼できない妻にはコミュニケーションを大切に!
育児で旦那さんを信頼できない妻は、自分の話に耳を傾け、自分の仕事が減る手助けをしてもらうことを求めています。
分かっていても妻が満足するほどの育児は、単身赴任や仕事が忙しくて帰りが遅い旦那さんにとって困難なことです。だからといってあきらめないでください。話しをきちんと聞くだけしかできなくても、育児疲れの妻に旦那さんができるナイスアシストになるんです。
直接話を聞く時間や精神的な余裕がなければ、こまめにLINEで育児の状況を報告してもらうのもよい方法です。できる方法で妻のメンタルを支えて、共に育児を乗り越えて強い夫婦の絆を築きましょう。