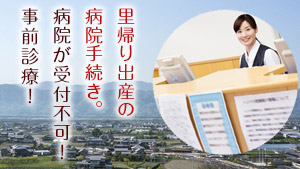【里帰りなし出産】自宅出産を夫婦で乗り切る!産前産後の準備とパパの役割徹底ガイド
「実家が遠いから里帰り出産が当然」と思っている方もいますが、実家が離れていても里帰りせず、ご自宅で出産を乗り切るご夫婦は多くいらっしゃいます。
ところが、旦那さんは仕事で家を空けることが多いケースがほとんどですから、里帰りしないで出産を乗り越えることに、不安を抱いている妊婦さんも多いことでしょう。里帰り出産をしない選択をした場合、夫婦の協力体制と事前の準備が成功の鍵となります。
里帰り出産のメリット・デメリットと夫婦の絆
「何とかなるだろう」と軽い気持ちで里帰りしないことを決めるのはおすすめできません。里帰りしないことにはメリットもありますが、デメリットや出産を乗り越えるための具体的なコツをしっかり把握してから、出産する場所を検討することが望ましいでしょう。
里帰りのメリットは何と言っても「ママにとっての安心と休息」

里帰り出産のメリットは、なんといっても「ママになる女性にとって安心で、楽なこと」があげられます。お腹が大きく重くなってくる妊娠後期の生活は、出産への不安も相まって大変ですが、実家の両親が面倒な家事を肩代わりしてくれたり、不安なときに相談に乗ってくれたりするのは、とても心強いものです。
また、旦那さんには仕事がありますから、「思うように手伝ってあげられない」と心配しているケースも多いです。そのため、「実家なら無事に出産できるだろう」と、実家で出産することで安心できるパパも多いのです。
里帰りは「産後クライシス」を招きやすい?無視できないデメリット
何事にも良い面と悪い面があるのは当然のことですが、里帰り出産には、無視できない大きなデメリットもあります。
「産後クライシス」とは、出産を契機として夫婦仲が悪化する現象です。女性側のトラブルだけでなく、最近は男性側が出産による生活の変化についていけず、育児や家事への協力意欲を失ってしまうという問題がクローズアップされています。
なぜ、子供の誕生を待ち望んでいたはずの男性の気持ちが変わってしまうのでしょうか。それは、男性が親としての自覚(父性)を芽生えさせることができないことが原因で引き起こされるケースが多いようです。
里帰り出産では男性が親として自覚できない!?自宅出産が父性を育む

男性は胎内で子供を育てる女性と違って、親としての自覚を持ちにくいものです。出産直前・直後という里帰り期間にあたる時期こそが、パパの自覚を持つための大事な時期ですが、その期間に子供と一緒に過ごせないことが、父性が芽生えないことの原因になりやすいのです。
この時期に父性が芽生えないと、男性は家族へのかかわりに興味を失くし、女性側も赤ちゃんも切ない思いをすることになりかねません。里帰りしない出産は、パパが最初から育児にコミットせざるを得ない環境を作るため、結果的に父性の早期覚醒を促し、夫婦の絆を深める大事なファーストステップとなります。
里帰りしない出産で得られる「夫婦のメリット」
- パパが妊娠・出産を「自分ごと」として捉えやすくなる。
- 生まれた直後から赤ちゃんとの接触が増え、父性が早く芽生える。
- 育児・家事を夫婦で分担する「我が家のルール」を早く確立できる。
- 産後の生活をシミュレーションしやすく、計画的な準備ができる。
里帰りしない!夫婦で出産を乗り切る5つのポイントと具体的な準備
やはり出産後の体を休めずに一人で乗り切ることは大変です。「(里帰りしなかったから)えらい目にあった」というママもいるほどです。
そのため、旦那さんの協力が不可欠となります。里帰りのデメリットは回避できても、協力が得られなければママに負担がかかりすぎてしまうため、出産前からのパパへの働きかけと準備が必要になるでしょう。
1成功の秘訣は、パパに対する「早期教育」と「意識改革」

産後は体調が優れない時でも、常に赤ちゃんのお世話に追われます。そのため、里帰りしない出産の成功を左右するのは、パパの自覚とスキルにかかっていると言えるでしょう。
ママから早めにパパへの教育を始めることも必要です。ここでいう教育とは、出産や育児全般の知識を与え、「協力するのが当たり前」という意識を教え込むこと、さらには、自分だけでも家事や育児ができるだけのスキルを身に着けてもらうことをいいます。
女性が当たり前に行っていることでも、男性にとっては難しいこともあるかもしれません。あまり厳しくするとやる気をなくしてしまいますので、怒らず褒めて、家事や育児で協力してもらいましょう。妊娠から出産までの期間はあっという間に過ぎてしまいますから、パパの意識を変えるのは早め(妊娠初期〜中期)に取り組むことが大切です。
早い時期にパパに覚えて欲しいこと
- 男性も出産や育児に協力するのが当然という意識。
- 妊娠経過やママの体の状況、産後の回復に必要な時間。
- 掃除や洗濯、簡単な食事の準備など基本的な家事の仕方。
- おむつ替えやミルクの作り方などの基本的な育児の技術。
2買い物の負担は「パパとの共同買い出し」と「宅配サービス」で乗り超える

毎日の食材の買い出しに、かさばる日用品の購入は、お腹が大きくなって負担に感じる、あるいは産後に赤ちゃんを連れて出かけにくい最大の課題の一つです。特に妊娠後期は、赤ちゃんの重みで腰痛がひどくなる時期ですから、買い物が負担になるママは多いです。
買い出しの負担を軽くするため、毎日の買い出しを週末などの定期的なまとめ買いに変えることをお勧めします。荷物がかさばるようになるので、買い出しは必ずパパと一緒に出掛けるように習慣付けましょう。
パパが仕事で忙しい場合は「ネットスーパー」や「食材宅配」をフル活用しよう!
仕事の都合などで、パパが買い出しに付き合えない場合には、コープなどの食材宅配業者や、大手スーパーのネットスーパーを利用するのが便利です。産後は赤ちゃんを連れての外出を控える必要がありますから、これを機に登録しておくと安心です。
重い荷物を自分で運ぶ必要もありませんし、移動をしなくていいので楽なこと間違いなしです。ネットを見ながら自分で好きなものを選べるので、ママにもよい気分転換になります。
パパと買い物情報を共有するコツ
- 買い物メモボードを共有しましょう。必要な物を掻き出して、冷蔵庫などの目につきやすい所に貼っておくと、パパでも買い出しがしやすくなります。
- 自宅の在庫管理をパパと一緒に行い、何がどこにあるかを知ってもらいましょう。
3掃除や洗濯などの家事の負担は「我が家のルール」と「便利な家電」で乗り越える

掃除や洗濯、食事の支度などは、生まれ育った家のクセやこだわりがあるものです。パパに掃除や洗濯をお願いする場合には、ママのこだわりを具体的に伝えておくことが大切です。この時期にパパにしっかり伝授して、我が家のルールを作っておくと産後もスムーズでしょう。
パパに上手に伝えることが大切
どんなに家事にこだわりがあったとしても、やってもらってから「こうじゃない」と否定するのは、パパのモチベーションを下げてしまいます。事前に具体的な手順を優しく伝えておき、はじめのうちは一緒に行うのも良いでしょう。
完璧を目指さない姿勢が大事
少々の汚れや散らかりは大目に見て、気にしないを心がけるようにしましょう。普段から家事を行っていない男性は、いきなり完璧にこなすことはできません。気になるところは目をつぶって、感謝の気持ちを伝えることが大切です。
便利な家電を「最高の育児サポート」として活用しよう!
掃除や洗濯でいかに楽をするかは、家電製品にかかっています。自動でお掃除をしてくれるロボット掃除機に、乾燥機能までついている全自動洗濯機など、家事の負担を大幅に軽減する家電が多数登場しています。これから子育てが始まり忙しくなりますから、これを機に夫婦の協力体制を補う投資として買い替えを検討してみるのも良いでしょう。
パパのモチベーションを維持するコツ
- 一生懸命に家事を覚え、こなしているパパに文句を言ってはいけません。「ありがとう」「助かるよ」と感謝の気持ちを伝えましょう。
- 子供の教育と同じです。パパは褒めて、褒めちぎってモチベーションをアップさせて、家事や育児に協力をしてもらいましょう。
4初産の不安は「父親学級」への参加と「綿密な計画」で乗り越える

初産の場合には、妊娠も出産も初めて尽くしです。ワクワクする反面、実は不安の方が多いことでしょう。不安なことは我慢せずにパパに打ち明けることが大切です。不安を共有して、二人で初産を乗り越えましょう。ただ不安を共有するだけでなく、不安を解消するために、出産を乗り切るための方法(計画)を二人で考えることが大切です。
急に陣痛が始まったり、破水をしたりしても対応できるように、パパにも早いうちから出産時の対応を覚えてもらうことが必要になります。産院や地域では「両親学級」や「父親学級」が開催されているので、夫婦で参加するようにするのがベストでしょう。
出産について知ることでパパの自覚が深まる
妊娠・出産について知識のないパパも、妊娠・出産の経過に寄り添うことでママへの労りと思いやりを感じるようになるでしょう。そして、家族を守る大黒柱の自覚がパパの中に育っていきます。パパにも無理のない範囲で、産院の検診にお付き合いしてもらうといいですね。
パパと一緒に整えたい出産に向けての準備チェックリスト
- 哺乳などの基本的な育児用品やおむつ、衣類の購入・設置。
- ベビーベッドなどの部屋の環境を整える。
- ママの入院バック、陣痛時の持ち出しバックの用意(パパがどこにあるか把握)。
- 出産予定日前後に休暇がとれるようにパパの仕事を調整する。
- パパが不在の時に陣痛が始まった場合の陣痛タクシーや緊急連絡先を手配しておく。
5上の子の面倒は「パパのワンオペ」と「公的サポート」で乗り越える

経産婦の場合、出産は経験していても、上の子のメンタルケアやお世話をどうするかという心配が出て来ます。上の子のお世話がある分、ママは産後体を休めることができません。
上の子の面倒を見ながらの妊娠・出産は、なんといっても慌ただしいです。パパにはできるだけ仕事の調整をつけてもらい、ママに代わって上の子との触れ合いを持ってもらいましょう。
下の子が生まれると上の子は不安定になりやすい
上の子は、赤ちゃんが生まれたことで不安定になりがちです。特に年齢が低いほど、注意して見てあげる必要があります。ママが赤ちゃんのお世話にかかりきりになる分、パパの大きな愛で上の子を包んであげましょう。
また、ママも、赤ちゃんの世話に没頭するのはNGです。多少赤ちゃんが泣いているのは放っておいても、上の子を抱きしめてあげる位の気持ちで上の子の育児に向き合うようにしましょう。
育児のサポートを受けることも大切(パパが忙しい場合の「ワンオペ回避」)
パパの仕事が忙しい場合には、保育園などの公的な育児支援や地域の産後ケアサービスを受けることを考えてみるのも一つの方法です。これは早めの準備が必要になる場合もあるので、事前に問い合わせておくと安心です。
上の子にとっても、安全な施設で同年代の友達とのびのび遊ぶことは、自宅でママや赤ちゃんと引きこもっているより良い影響を与えます。施設の送り迎えも大事な親子のコミュニケーションの時間になりますので、パパに送り迎えをお願いすると、良い親子関係を築いていくことができるでしょう。
パパが忙しい時に頼りになる外部サポート
- 保育園や幼稚園などの一時保育・時間外保育。
- 地域の地域包括センターや子育て支援センターなどの一時預かり。
- 産後ケアサービス(自治体や助産師会)や家事代行サービスなどの民間企業。
里帰りしない出産は親不孝?多様な家族の選択肢を尊重する
里帰り出産にはデメリットもありますが、里帰りしないことで抱え込みやすい、家族の問題もあります。里帰りをしないことで、「親不孝だ!」というレッテルを貼られるのではないかと気にして、なかなか実家に自分の希望を言い出せないというママも多いようです。
確かに多くのママが里帰り出産を選ぶ日本では、里帰りしないことが「非常識」、可愛い孫の世話を祖父母にさせないとは何事だ!という古い考えを持つ人も少なくありません。しかし、家族の在り方は時代によって刻一刻と変化しています。出産や育児の主役はママとパパなのですから、ご自分たちにふさわしくない古い常識などは、どんどん変えていきましょう。
実家の両親に来てもらうというのも一つの方法(産後サポートの活用)
「上の子の幼稚園がある」「パパにそばにいて欲しい」といった理由で里帰りできない場合には、産後だけでも実家の両親に来てもらって、助けてもらうという方法もあるでしょう。
「産後だけ実母に来てもらった」というケースも多いですが、その場合には旦那さんとよく相談して決める必要があります。自分の親が自宅に来ている間は、旦那さんはすごく気を使うでしょう。旦那さんは一緒に生活したことがないのです。
また、自分の親に来てもらってばかりで、夫の両親には来てもらわないということも、相手の両親の印象が良くありません。里帰りしない場合は、両家の協力と理解を得ながら、上手に頼ることが必要です。
里帰りしないで出産しても家族との関係は大切に
里帰りしない理由はさまざまです。「両親との折り合いが悪い」「実家に居場所がない」などの理由で、里帰り出産を選ばない人もいます。しかし、里帰り出産をしないからといって、実家など家族の助力を全く受けてはいけないということにはなりません。
里帰りをするもしないも、出産や育児をすることで大事なのは、家族との良好な関係を作っておくことにあります。頑張れるときは夫婦で頑張り、無理なことは家族の助力を受け入れて素直に感謝する。そんな良い家族関係は、人生できっとプラスに働くはずです。
パートナーとの絆、両親との絆、自分の子ども達との絆を大事にして、出産や育児をみんなで楽しんでくださいね。