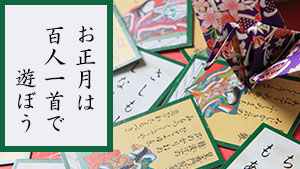ひな祭りをお祝いしよう~雛人形・桃の花・ちらし寿司・雛あられ
3月3日と言えばひな祭り。女の子がいるご家庭では、家族みんなでお祝いしますよね。私たちが子どもの頃は、祖母や母が当たり前のように準備してくれていましたが、いざ自分で準備しようと思うと、意外と知らないことも多く、戸惑うことがあるかもしれません。子どもの健やかな成長を願う大切な行事だからこそ、きちんと準備したいと考える方も多いでしょう。そこで、ひな祭りの由来やお祝いの仕方、食べるものに込められた意味まで、ひな祭りについて徹底解説します。女の子のいるママやパパはぜひチェックしてみてください。
ひな祭りとは

3月3日の桃の節句の日に、女の子の健やかな成長と幸せを願って行われるのがひな祭りです。ひな祭りを知らないという人はほとんどいないくらい定着しており、特に女の子のいる家庭では大切にされている行事です。具体的にお祝いとしては、雛人形や桃の花を飾ったり、ちらし寿司やはまぐりのお吸い物などのお祝いの食事を食べたりして、祝います。
ひな祭りの由来
ひな祭りといえば女の子の成長を願う行事ですが、もともとの起源には、現在とは少し異なる意味合いが込められていました。ひな祭りの由来となった二つの風習を知っておくと、ひな祭りもより一層楽しめます。
流し雛
流し雛(ながしびな)は、ひな祭りの起源の一つとされています。紙や木、土で作った人形(ひとがた)に自分の穢れ(けがれ)を移し、それを川や海に流して厄(やく)をはらうという風習から来ています。
雛遊び
平安時代に貴族の女の子たちの間で流行した遊びの一つに雛遊び(ひなあそび)があります。これは、小さな御殿や道具、人形を使って遊ぶもので、現在でいうおままごとのようなものです。この人形遊びと、前述の「流し雛」の風習が結びつき、江戸時代頃に現在のひな祭りの形へと発展していきました。
ひな祭りは3月3日
ひな祭りは、3月3日に行うのが一般的ですが、なぜこの日になったのでしょうか。それには、まず平安時代を起源とする「五節句(ごせっく)」という行事を知る必要があります。五節句とは、季節の節目となる式日(しきじつ)のことで、邪気を払い、無病息災や豊作を願う年中行事です。ひな祭りは、五節句のうちの一つである3月3日の「上巳の節句(じょうしのせっく)」に合わせて行われるようになりました。上巳の節句は、もともと水辺で禊(みそぎ)をして穢れをはらう日であり、この風習が人形に厄を移して流す「流し雛」と結びついたことが、3月3日に定着した理由とされています。
ひな祭りのお祝いの仕方

ひな祭りの起源を知ったところで、次にお祝いの仕方についてみていきましょう。とても一般的な行事ですが、「雛人形はいつから飾るの?」「どんなメニューを用意すればいいの?」など、いざとなると疑問が出てくるかもしれません。その家オリジナルのお祝いも素敵ですが、本来のお祝い方法を知ると、より奥深いひな祭りにできます。
雛人形を飾る
ひな祭りといえば、雛人形を飾ってお祝いするのが一般的です。お雛様とお内裏様を飾る親王飾り(しんのうかざり)から豪華な七段飾りまで、たくさんの種類があります。子どもの頃は、祖父母や母と一緒に飾っていましたが、自分が準備する立場になると、さまざまな疑問が生じます。雛人形を飾る際に知っておくべきことをチェックしてみましょう。
雛人形を買う人は誰
そもそも雛人形は誰が買うべきものなのでしょうか。ご家庭の事情もありますので一概には言えませんが、一般的には母方の祖父母から贈られることが多いとされています。これは、昔、嫁入り道具の一つとして嫁ぎ先に持っていくという風習から来たものです。現在は、父方の祖父母が購入したがったり、両親が選びたがったりと、家によってまちまちです。そのため、「もう買ったのに、相手側の親も買っていた」といったことにならないよう、両家で事前に話し合ってから購入するのがおすすめです。
いつからいつまで飾る

雛人形には、子どもの厄を代わりに引き受けてもらうという役割があります。そのため、3月3日の一日だけ飾るのはあまり良くないとされています。遅くとも、2月中旬までには飾るようにしましょう。一般的には、節分が終わり、立春(2月4日頃)から2月中旬にかけて飾るのが良いと言われています。早めに準備を始めましょう。
また、ひな祭りが終わってもいつまでも飾っておくと、「婚期が遅れる」と言われることがあります。片づけに良いとされているのは、3月6日の啓蟄(けいちつ)の日などがありますが、天気の良い日に片づけた方がカビなどの心配が少なくなります。日にちにこだわりすぎず、ひな祭りが終わったら天気の良い日を選んで早めに片付けましょう。
処分の仕方
娘さんが結婚したり、大人になって飾らなくなったりした雛人形は、どうすればいいのでしょうか。毎年飾らずにタンスの肥やしになってしまうよりは、適切な方法で処分するのが良いでしょう。粗大ごみとして捨てるという人もいますが、人形には魂が宿ると考える人も多いため、できれば神社やお寺などで供養してもらうのが一般的です。今まで子どもの厄を引き受けてくれた雛人形に感謝の気持ちを込めて、最後までしっかりと見届けてあげましょう。
吊るし雛もステキ
最近は、吊るし雛(つるしびな)も人気が出てきています。たくさんのお人形が吊るされている様子は、とっても華やかで素敵です。吊るし雛は、裕福ではない家庭の子に、親や親戚、近所の人が少しずつ人形を作って贈ったのが始まりとされています。さまざまな人の子どもの幸せを願う思いが込められたお雛様なのです。人形のひとつひとつに意味があるので、購入する際はチェックしてみるとさらに楽しめますよ。
手作りも楽しい
雛人形をいざ買うとなると結構なお値段がします。そんなに費用をかけなくても、雛人形を手作りするというのも一つの方法です。ひな祭りは女の子の成長を願う行事なので、その女の子が喜ぶものを作ってあげるのが一番です。折り紙やフェルト、粘土など、子どもも一緒に作れるものだと、より思い出に残りますし、楽しさも倍増します。
桃の花を飾る

ひな祭りの際に桃の花を飾るのは、単に華やかでかわいらしいからという理由だけではありません。古来中国では、桃の花には邪気を払い、不老長寿の力が備わっていると言われていました。こうしたことから、桃の花を浮かべたお酒を飲んだり、桃の花の浮かんだお風呂に入ったりして、無病息災を願ったと伝えられています。桃の節句と呼ばれるようになったのは、この風習から来ています。
歌を歌う
ひな祭りが近づくと、ついつい「あかりをつけましょ ぼんぼりに~」と口ずさんでしまう人も多いですよね。「うれしいひなまつり」というこの歌は、ひな祭りの定番の曲です。家族で食事をする前に歌うと、よりひな祭りムードが高まって楽しくなりますよ。歌詞は難しいかもしれませんが、子どもにも歌いやすいメロディーなので、ぜひみんなで歌ってお祝いしましょう。
お祝い金
初節句の際にはお祝いを贈るのが一般的です。昔はケースに入った人形を贈るという風習もありましたが、最近はあまり見られなくなりました。代わって、品物を贈ると相手に気を使わせてしまうといった理由から、現金を贈ることが増えました。親族や仲人は1万円~2万円、友人や同僚の場合は5千円~1万円が相場とされています。関係性にもよりますが、あまりおおげさなお祝いを贈ると、お返し(内祝い)が大変になってしまうので、金額にも気を配りましょう。
ひな祭りに食べるもの
ひな祭りのメニューといえば、なんとなくイメージするものがいくつかありますよね。子どもの頃は「ご馳走が食べられてラッキー」くらいにしか思っていなかったひな祭りの食事ですが、ママやパパになり、いざ自分が準備する立場になると、献立を考えるのも大変です。しかし、一つひとつのメニューに子どもの健やかな成長や幸せを願う意味が込められていると知ると、頑張って作りたくなりますよね。そんな奥深いひな祭りに食べるものをご紹介します。
ちらし寿司

ちらし寿司は、ひな祭りのメイン料理の一つです。ちらし寿司自体がお祝いの席にふさわしい料理ですが、中に入れる具材にも縁起の良い意味が込められています。例えば、エビはその姿から「腰が曲がるまで長生きする」、レンコンは穴が開いていることから「先が見通せる人生」、豆は「健康でマメに動ける」という意味があります。そもそも「寿司」は「寿(ことぶき)を司る」で縁起がよく、お祝いにふさわしい料理という意味があります。他にもお子さんの好きな具材や、季節の野菜などを取り入れてもおいしくいただけます。
蛤のお吸い物
はまぐりの貝殻は、対になっている二枚以外とは、絶対にぴったり重なることがありません。このことから、一生ひとりの人と添い遂げられる、絆の強い夫婦になってほしいという意味が込められています。女の子の幸せな結婚ができるように願いが込められているのです。
雛あられ
ひな祭りのお菓子といえば雛あられですね。ピンク・緑・黄色・白の四色が四季を表しているという説もあります。子どもが一年を通して健康で過ごせるようにという願いが込められています。ちなみに、関東と関西では味が異なるのが特徴です。関東では甘い味付けが多く、関西ではしょっぱい(甘辛い)味付けが多いので、機会があったら食べ比べてみると楽しいかもしれません。
ひし餅
緑・ピンク・白の三色のひし形のお餅がひし餅です。これもひな祭りには欠かせない食べ物です。この三色には、それぞれ意味が込められています。緑は「健康・長寿」、ピンクは「魔除け」、白は「清浄」を意味していると言われています。一般的に、緑は増血効果があるヨモギ、白は血圧を下げるひしの実、ピンクは解毒作用があるクチナシで色付けされており、これらの健康効果も「健康・清浄・魔除け」に通じているとされています。
白酒
ひな祭りで飲む白酒(しろざけ)は、もともとは桃の花をつけた「桃花酒(とうかしゅ)」というものが飲まれていました。桃の花は邪気を払い、気力や体力を高める効果があることから、縁起のよい飲み物とされてきました。江戸時代から白酒の方が人気が出て、現在に至るまで白酒が主流となっています。白酒はアルコールが含まれているため、お子さんにはノンアルコールの甘酒を用意してあげるとよいでしょう。
ケーキ

ひな祭りにケーキを食べるようになったのは最近の風習です。もともとはなかった文化ですが、近年、「お祝い事にはケーキ」という文化が広がりつつあります。子どもが大好きなケーキも、ひな祭り仕様になっていると一段と喜ばれます。かわいいケーキを買うのも良いですが、子どもと一緒に手作りするとさらに楽しい思い出になります。女の子なら尚更、手作りケーキのレシピを教えてあげるのも素敵ですね。
ひな祭りは楽しくお祝いしましょう
ひな祭りについて、由来や意味などをお伝えしました。伝統や昔ながらのしきたりも大切ですが、一番大切なことは、ご家族みんなが楽しく、子どもの健やかな成長を願ってお祝いすることです。形式にこだわりすぎず、自分たちの家族にあったひな祭りのスタイルで、素敵な思い出を作りましょう。